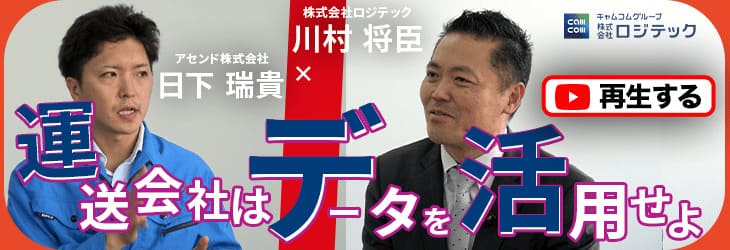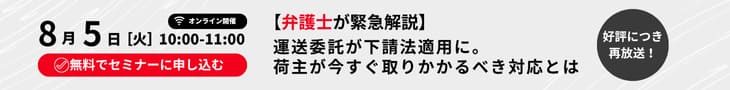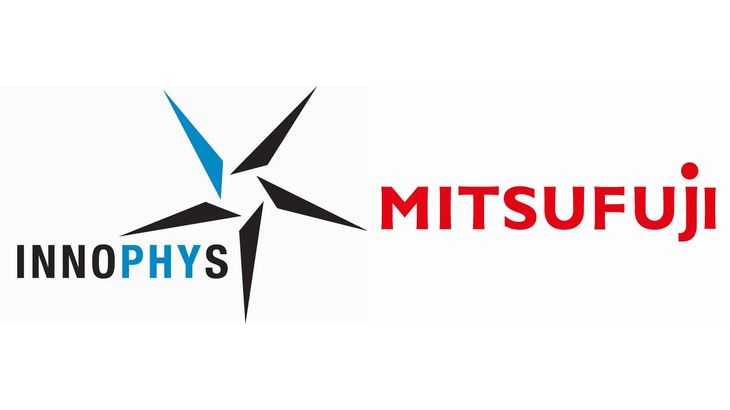国交省が多重下請け構造検討会で調査結果公表
国土交通省は11月28日に開催した「トラック運送業における多重下請構造検討会」の第2回会合で、運送業の多重下請け構造の実態に関する実態調査結果を公表した。
一般的に「水屋」と呼ばれる、荷主企業と元請け運送事業者などの間を仲介する第一種利用運送事業者に関し、運賃と別に徴収するのではなく、運賃から手数料を差し引いている割合が52.7%に達し、常態化している公算が大きいことが分かった。
その理由としては「商慣習」と答えた割合が83%に達し、契約などの明確な根拠がないまま行っている可能性が大きいことを示唆している。
トラック運送業界には、荷物とトラックを仲介するマッチングサービスや水屋の存在が、国交省が設定している「標準的運賃」とかけ離れた安値で車両を確保していることなどから運賃相場を引き下げる要因になっているとの反発が根強い。国交省は調査結果を踏まえ、検討会で水屋の事業に対して何らかの規制を導入するべきかどうかを引き続き検討する。
調査は今年9月30日から10月31日にかけてインターネット経由で実施。第一種貨物利用運送事業の免許を取得している事業者2万7976社を対象に実施、3.9%の1094社から回答を得た。
国交省は回答の割合が低いことや、多重下請け構造の課題認識を伝えた上で答えてもらったことを踏まえ「実態を均等に網羅しているものではなく、当省の課題認識に基づく調査に対して比較的協力的な層の回答から成っていることに留意する必要がある」と注意喚起している。
つながりのあるトラック事業者「5社以下」が過半数
事業者の実態を見ると、倉庫業や貨物自動車運送業など他の業務との兼業が69.3%で圧倒的に多く、専業は25.3%、不明は5.4%だった。事業者の規模は「資本金300万~1000万円未満」が42.2%でトップとなり、「1000万~3000万円未満」は28.7%、「3000万~5000万円未満」は8.5%、「5000万~1億円未満」が9.3%など、小規模の回答者の割合が多い印象を受けた。
担っている下請け次数について尋ねると(複数回答可)、荷主企業と元請け運送事業者の仲介を手掛けている事業者が75.6%に上り、回答者に限ると多重下請け構造の中の上位層を大勢が占めていることが浮き彫りとなった。「元請けと1次下請けの仲介」は16.6%、「1次下請けと2次下請けの仲介」は5.2%、「2次下請けと3次下請けの仲介」は2.0%、「3次以下の下請けと4次以下の下請けの仲介」は0.6%だった。
日ごろつながりのあるトラック事業者数は「1~5社」が53.3%で過半数を占めた。「6~10社」は20.0%、「11~50社」は21.8%、「51~100社」は2.6%、「101社以上」は2.3%だった。
紹介するトラック事業者を選ぶ際に考慮する事項としては(加重平均値を算出)、「輸送可能エリア(発地・着地・方面)」が31.4%でトップ。「運賃」(17.8%)、「車両台数・車種・車両の設備」(14.8%)、「出発・到着時刻(何時までに依頼すれば対応してくれるか)」(12.7%)などと続いた。
運送依頼を受ける場合の連絡方法は(同)、「電話」が41.2%で、「メール」(24.1%)、「ファクス」(17.1%)、「対面」(9.0%)を引き離した。依頼を引き受けた後の求荷・求貨の連絡・探索方法も「電話」(47.7%)が最多だった。
手数料を明示しているかどうかについて聞いたところ、求荷側に関しては、依頼元へ「明示している」が36.8%、「明示していない」が63.2%、求車側も「明示している」が37.2%、「明示していない」が62.8%で、明示していない事業者が過半数に到達した。
手数料の設定方法は(複数回答)、「個別交渉」が28.2%、「方面に応じて」が18.8%、「運賃の一定割合」が18.1%、「トンキロ数に応じて」が15.3%、「品目に応じて」が8.9%など、多様化していることをうかがわせた。
手数料の収受方法は運賃から差し引くが過半数となった一方、「運賃と別建てで求車側に請求」が29.8%、「運賃と別建てで求荷側と求車側の双方に請求」が12.4%、「運賃と別建てで求荷側に請求」が5.0%だった。
運賃から差し引いていると回答した事業者にその理由を聞くと、「契約、規定など」は6%、「事務処理等の手間がかからず精算処理が容易」が4%と、いずれも割合は非常に少なかった。
手数料を運賃の一定割合とすると答えた事業者(602社)に具体的な料率を聞くと、「5.1~10%」が61%で首位。「10.1%~50%」は20%、「0.1~5%」は19%などとなった。
運賃の決定方法について、求車側の依頼時に提示した額と「標準的運賃」を比較していると答えた割合は57.3%、求車側が見つかった場合の提示した額との場合は63.8%だった。
手数料を収受する際、運賃から差し引いていると答えた事業者の割合は、「荷主と元請けを仲介」の場合が契約件数ベースで48%、「元請けと1次を仲介」(174社)が70%、「1次と2次を仲介」(50社)が74%で、総じて下の階層を仲介している事業者の方が割合が大きかった。
「電話などで取次のみを行う者はほとんどいないのでは」
自由回答では、「荷主への請求科目が運賃となっているため、運賃から差し引くというのが慣例になっている」「別建てにすると、手数料部分を荷主に値切られる恐れがあって別建てにできない」「荷主に対しては、実運送事業者が見積もった運賃に手数料相当の額を加算して運賃として見積もり請求している」「運送会社からの運賃を聞いた上で、荷主に運賃の10%程度と別建てで請求している」といった声が聞かれた。
国交省は並行して、求荷求車のマッチングサイトを運営している5社を含む一般貨物自動車運送事業者と利用運送専業事業者の計33社を対象にしたヒアリング調査結果も公表した。「マッチングサイトが出てきたことにより、電話などで取次のみを行う者は今はほとんどいないのではないか」「そうした者は、今は運送会社や荷主などに属して利用運送事業を行っているのではないか。組織を転々としている人が多い印象であり、営業能力の高さや人的ネットワークを買われて、引き抜き合戦もある」との声が多数寄せられたという。
国交省は調査結果を踏まえ、今後、トラック運送の元請け事業者の段階で運送業務を下請けに再委託する際のルール整備などについて是非を引き続き検討する。
(藤原秀行)