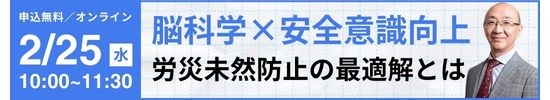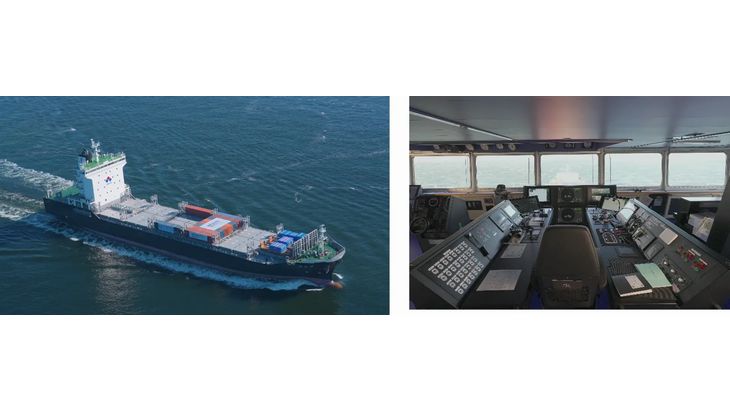初の国際会議で目標設定、製造現場で活用も
日本とブラジルの両政府は9月15日、大阪市で、環境負荷が低く脱炭素を後押しするバイオ燃料や水素、アンモニアといった「持続可能燃料」(次世代燃料)を船舶や航空機、自動車などで幅広く利用していくための方策を議論する国際会議「持続可能燃料閣僚会議」を初めて開催した。
両国が共同議長を務め、34の国と国際機関が参加。2035年までに持続可能燃料の生産・利用を24年実績から少なくとも4倍に伸ばすとの目標を盛り込んだ共同議長サマリーを公表した。
日本からは武藤容治経済産業相が出席した。

会議の参加者(経産省ウェブサイトより引用)
共同議長サマリーは「各国の異なる出発点や状況も考慮しつつ、航空や船舶、道路交通、産業などの様々な分野において、持続可能燃料の生産および利用の拡大に向けて連携すること」が重要と指摘。
船舶や航空機、自動車の燃料として用いるほか、産業分野でも製造現場で利用することを示している。新興国や開発途上国の利用拡大へ技術や資金面で協力することなども打ち出している。
経産省と国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は同日、併せて「第7回水素閣僚会議」も開いた。議論を踏まえて取りまとめた議長サマリーは各国で水素の需要創出を図ることが重要との見解を表明。グローバル規模で各国が協力してサプライチェーンを構築していくことなどを訴えている。
(藤原秀行)