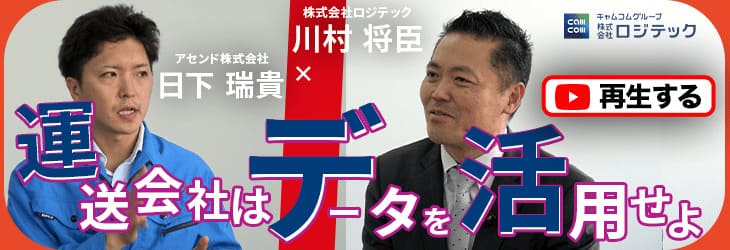Shippio・川嶋氏が展望、サプライチェーン運営の不確実性高まり考慮訴え
米国の大統領選挙で共和党のドナルド・トランプ氏が再選を決めた。現行の民主党・バイデン政権の政策を強烈に批判し、自国の製造業復権や不法移民流入阻止など「アメリカファースト」を声高に主張しているだけに、2025年1月20日の就任と同時に政策は大きく変わり、国内外に相当な混乱をもたらすことが避けられそうにない。
まさに歴史的な転換点を迎える中、日本の企業は今後、どのような動きに備えていくべきなのか。総合物流企業や大手電機メーカーで海外業務やサプライチェーン企画部門などを担当し、現在はShippioでコンサルティングセールスを手掛ける川嶋章義氏に、海運市況をはじめサプライチェーンの動きなどについて、展望してもらった。

川嶋氏(Shippio提供)
「インフレ退治」と政策が矛盾も
――ドナルド・トランプ氏が米大統領選挙で勝利を収めました。物流業界にとっては不可分の通商、関税の面をはじめ、かなりの変化と混乱が見込まれそうですが、日本経済への影響をどう御覧になりますか。
「トランプ氏は大統領選挙の期間中、公約として『Agenda47(アジェンダ47)』を一貫して主張してきました。この中でもインパクトが大きいのはおっしゃる通り、通商・関税で、中国だけではなく日本も含めてほぼ全ての国からの輸入品に、一律で10~20%の基本税率を導入することを示唆しています。特に中国に対しては、最恵国待遇を撤廃し、関税を60~100%へ引き上げることを示しています」
「現在はトランプ政権への移行チームが立ち上がり、閣僚人事などを進めています。閣僚の顔ぶれを見ればどういう政策を取ろうとしているのかがだいたい浮かんできますが、経済・貿易分野などを見ると、やはり中国に対して相当強硬な姿勢を取るメンバーが候補として顔を揃えています。第1次トランプ政権で存在した、政策のブレーキ役となる人がなかなか見当たりません。例えば、関税を管轄している米通商代表部(USTR)の代表には、第1次トランプ政権でも関税の政策を担い、保護主義的な貿易政策を主張してきたロバート・ライトハイザー氏の再登板が取りざたされています。いろいろな規制、ルールを敷いてこようとするのではないかと予想されます」
「また、今回は大統領選挙に加え、上下両院の選挙でも共和党が過半数を占め、共和党のシンボルカラーの赤から『トリプルレッド』と呼ばれる状態になることが確定しました。スムーズな政権運営が可能になり、盤石な体制の下で政策実施に向け、トランプ氏に強力な権限が委任されることになります。スピード感を持ってルールチェンジが成されていくとみられます」
――関税引き上げを含めて、トランプ氏の打ち出している政策はどの程度実現の可能性がありそうですか。
「トランプ氏が再登板すると、何をやってくるのか分からない不確実性が非常に高まってくることが見込まれます。先ほどお話ししたアジェンダ47でもトランプ氏はインフレの退治を最優先に挙げています。しかし、彼が掲げている政策は矛盾するものが少なくありません。仮に法人税減税を実行すれば基本的に景気が上向くので、そうなると消費が刺激されてインフラがさらに続くリスクが出てきます。また、関税を引き上げれば輸入コストが増加し、その分が商品の価格やサービスの料金に転嫁されます。過去最大規模の移民の強制送還に踏み切れば、人手不足を招いて賃金が上昇し、結果的にインフレを加速させることになるかもしれません」
「米銀行のウェルズ・ファーゴは、トランプ政権が中国に60%、その他の国・地域に10%の一律関税を課し、同じ措置を報復された場合、IMF(国際通貨基金)が3.2%と予想している2025年の米国の実質経済成長率は0.6%に落ち込むと試算しています。彼はビジネスマンなので、実際交渉のためにひとまず(極端な)主張をしておいて、やらないというケースも十分考えられます。第1次政権時も政策を実行した割合は2割程度にとどまったとの調査結果もあります。ただし、政策を実施するとなればスピードは速いので、われわれ日本企業はゲームチェンジに即応できる体制を今後築いていかないといけないでしょう。調達先を見直す準備もしておかないといけない」
――トランプ氏の政策による影響は短期的なものと中長期的なものに分かれると思います。それぞれどのように見ていますか。
「短期的な影響としては、もう一部で始まっていますが、関税引き上げを警戒して、その前の駆け込み輸送が増え、運賃が急上昇する可能性があります。長期的な影響としては、中国からの生産拠点の移転、サプライチェーンの再編が加速していくでしょう。中国をサプライチェーンから切り離していく『デカップリング』がトランプ政権下でさらに進んでいくでしょう。中国企業も中国国内から第三国に生産拠点を移していく、あるいは米国に生産拠点を移していくのではないか。トランプ氏は米国で製造業の地盤地下が進んでいる中西部の『ラストベルト(さびた工業地帯)』の再興を訴えていますから、ここに移転させて製造させるというサプライチェーンの流れが出てくる可能性はあるでしょう」
第三国経由した複線化・分散化がより加速
――海上運賃はかなり上昇しそうでしょうか。
「第1次トランプ政権時は2018年7月、中国産品818品目に対して追加関税を課しました。その時は中国発の運賃が大きく上がりました。そうなると日本発もつられる形で一定程度、運賃が上昇しました。ただ、今回は中国を含む全ての国に対して追加関税を設定すると言っていますから、その比にならない運賃上昇が起こり得ます」
「では、どのように関税を引き上げていくのか。急速に上げるとなれば米国経済にも悪影響がものすごく出ますから、そのシナリオは個人的には考えにくいと思います。考えられるのが、中国を中心に、段階的に関税を引き上げていくのか、あるいは実際には導入しないがブラフで主張するというパターンのいずれかではないでしょうか」
「現状、北米も2018年当時とは異なり、かなり状況は悪くなっています。北米の東岸では25年1月以降、自動化問題で港湾労使が妥結せず、港湾ストライキが再び起こることを警戒し、多くの荷主が荷揚げ地を西岸にシフトさせています。さらにカナダの東岸、西岸でもストライキが起きているため、滞留貨物の増加などが起きています。特に荷物を内陸部や中西部へ輸送するため、鉄道の負荷が大きくなっており、滞留時間も伸びています。そこに、さらに関係引き上げ前の駆け込み需要が入ってくると、本当に対応しきれなくなり、最悪の場合は北米の混乱がグローバルのサプライチェーンに影響し、全ての運賃が上昇していく可能性があります」
「米小売業者は、港湾ストや関税引き上げを警戒し、輸入量を引き上げています。今後荷動きが活発化していくと見込まれる中でも、船会社はあえて船腹の供給量を抑制し、タイト感を出しています。25年の長期契約レートの交渉が12月から本格化するため、船会社としては事前に運賃を上げておきたいとの思惑があります」
「また、新型コロナウイルスのパンデミックなどの経験から、米国の小売業者は在庫を必要最低限に絞る『Just in time』から万が一に備えて在庫を積み増す『Just in case』に戦略を変えてきています。やはり、小売業者にとっては棚に穴を空けてしまうのが一番の悪ですから。今在庫は過剰気味になってきています」
――グローバルサプライチェーンの在り方は大きく変わらざるを得ないようですね。
「中長期的にサプライチェーンへの影響を見ると、先ほどもお話しした通り、米中間の直接の物のやり取りが減少する一方、東南アジアからの貿易量は拡大すると見込まれます。新たな潮流として第三国を経由したサプライチェーンの複線化・分散化がより加速するでしょう。より業務が煩雑になるということです」
「ただ、特に今回のような潮流の変わり目では、新興国のインフラ整備が進んでいないため、港が混雑するなど新たなボトルネックになる恐れはあります。例えば、メキシコは中国からの輸入が増えていますが、受け入れるメキシコの港湾のインフラ整備が進んでいません。メキシコの主要4港のコンテナ引き取り時間は平均で4時間44分にも達しています。サプライチェーンの運営が非常に難しくなってきています」
「関税引き上げを見越した動きとして、中国のEV(電気自動車)メーカーはEU(欧州連合)域内のハンガリーや準加盟国のトルコに製造拠点を構え、関税を回避しようとしています。その結果、中国からハンガリー、トルコなどへの貨物輸送量が増え、欧州域内のサプライチェーンの潮流を変えていく可能性があるでしょう」
「トランプショックだけではなく、地政学的リスクなどからグローバルサプライチェーンは激動の時代を迎えています。パンデミック以降、海上運賃の動きは乱高下しています。現行のSCMの見直しが必要不可欠です。サプライチェーン戦略を各社がすごく考えておかないといけない。確実に今後、サプライチェーン運営が複雑化するのは間違いないことですから、今のうちからDXで業務効率化を図り、意思決定をより迅速にできる体制に移行しておく必要があります。いざ本番になってからでは対応できないかもしれません」
(藤原秀行)