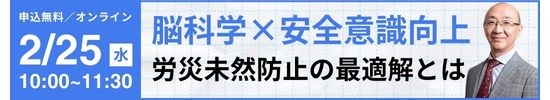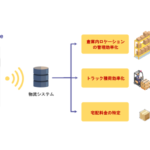協議会がオンライン会議で表明、関係者は必要性を強調
ドローンなどの先進技術を活用した「新スマート物流」を普及させ、人口減少に直面する地方の物流ネットワーク維持を図っている「全国新スマート物流推進協議会」は8月8日、平時と災害時の両方で使える物流システムの実現と普及を目指した「フェーズフリー型物流インフラ実現会議」の第2回会合をオンラインで開催した。
同協議会の田路圭輔理事(エアロネクスト社長グループCEO=最高経営責任者)は、政府が2026年度に防災庁の設置を目指していることに関連し、ドローンを使ったフェーズフリー型物流の早期実用化へ9月以降、より本腰を入れて取り組んでいく方針を強調。他に登壇者もフェーズフリー型ドローン物流の重要性を指摘した。

能登半島地震の際、石川県輪島市でドローンが医療物資を配送する様子(エアロネクストウェブサイトより引用)
会合では、ソフトバンク テクノロジーユニット統括次世代社会インフラ推進室推進部 UAV推進課の小沼愛担当課長が通信会社として災害時のドローン活用を支援している事例を紹介。実例として、災害時に有線で給電するドローンを飛ばし、被災地でも通信可能にしていることなどを挙げた。
2024年1月の能登半島地震を契機に、ドローンによる被害状況把握や孤立集落への物資輸送、道路の状況確認などが進み、防災活用が本格化したと回顧。さらに、エアロネクストと今年7月にフェーズフリー型ドローン物流の基盤整備で業務提携したことにも言及した。
小沼氏は「物流業界のことを今後も学んでいきたい」と語り、災害時の物資輸送に生かせるよう、平時からドローン物流を展開しておくことに強い意欲を見せた。
続いて登場したアスクル新規事業開発室の才田啓三統括部長は、自社のECの物流網運営の経験から「平常時の適切な運用がなければ発災時の管理はできない」と指摘。フェーズフリー型ドローン物流を構築する上で、日常の延長線上で非常時にも機能する設計や、誰でもどんな状況でも迷わず使える「ユニバーサルデザイン」の確保などが要諦になるとの見解を示した。
エアロネクストグループでドローン物流のオペレーションを担っている同社経営企画部の近藤建斗氏は、自治体や民間企業が防災訓練でドローン配送を組み込んでいることなどを報告した。同時に、自らも能登半島地震の被災地でドローンを使った災害支援活動に参加した経験から、ドローン活用が自衛隊や救護の計画に含まれておらず初動段階で活用が遅れたことや、避難所の側で誰が物資を受け取るかやどこにドローンを着陸させるかといった受け入れ体制が整備されていなかったこと、飛行ルートや着地時点が確定していなかったことなどを課題として挙げ、フェーズフリー型ドローン物流を組み立てる上で解決すべきだと訴えた。
BCPの一環として、災害時に備えて平時から、災害時に孤立する可能性がある集落とドローンによる物資輸送対象となる荷受け場所の選定、飛行ルートの事前設定、通信環境の調査と対応などを進めておくことが重要とアドバイスした。また、長野県木曽郡で実際にドローンを防災インフラとして生かすための事前調査・準備が進められていることにも触れ、こうした取り組みが広がることに強い期待を示した。
避難所の人員構成などの情報把握で救援物資の無駄回避可能に
続いて関係者がパネルディスカッションに参加した。同協議会理事でセイノーホールディングス専務執行役員オープンイノベーション推進室長(セイノーラストワンマイル社長兼務)の河合秀治氏は「能登半島地震から1年以上が経ち、だんだんわれわれも記憶が風化している。同地震以降、フェーズフリーというパッケージを早く全国に広めていかないといけないと考えたが、まだまだ社会実装には課題がある」との思いを吐露。
「それぞれの企業の持ち出しだけでは難しい。志だけでは難しく、ちゃんとビジネスとして設計しないと駄目だという思いがある」との見解を示した。
ソフトバンクの今秀昭UAV推進課長は「実証にとどまらず、ちゃんと社会に実装することを目標として活動している。社会の皆様に使っていただく新しいインフラを作りたい」との決意を表明。併せて、「(フェーズフリー型ドローン物流が)ビジネスにつながるのかというところに、今一歩踏み出せていない」と河合氏の発言に応じた。
田路氏は「民間企業と自治体が(災害時の協力)協定を結ぶところで完結してしまい、そこから具体策が進んでいない」と分析。河合氏は「自治体の皆さんは結構部署が分かれていて、2年くらいで異動してしまう。継続してコミュニケーションを取るのが難しい。一定のところは民間で詰めないといけないし、ビジネスモデルを自治体の人が考えられるかというと難しい」と述べ、民間企業が率先して取り組む必要性を提起した。
才田氏は「しっかりビジネスとして成り立たないと、協定もそうだし、BCP全般も継続性の確保がなかなか難しい。事が起こった時に初めて物が動く、というビジネスではなかなか立ち上がりが厳しい。平常時からシステムで物品管理やローリングストック(備蓄分の一定量を消費し、その分は新たに購入することで備蓄全体が古くなることを防ぐ管理手法)、配達や物流の行為をやってもらうことで、発災しても同じことができるようになる」と述べた。
近藤氏は「ドローンは個別輸送になってしまうので、いかにピストンで配送できるのかが肝。運行管理システムが平時でも日本ではまだ整備されていない。災害時はヘリコプターなどが空域内で飛んでカオスなので、空域管理が必要」と自らの経験から取るべき対応を提案した。
今氏は「ないことが起こり得るのが防災の考えであり、事前に先回りして考えておくことが非常に大事。いかに安定的に通信環境を継続して届けられるかが使命」と説明。才田氏は「有事があるので対応が進化していく。防災の切り口で社会は絶対進化していくと考えている」と展望した。
河合氏は、企業や団体、自治体などが集まって対応を検討するオープンイノベーションの形式を採用すべきだと提唱。また、能登半島地震の際、全国から救援物資がどんどん届いたのはよかったが、シニア層が中心の被災者のところに子供用おむつが大量に届くなど、被災者のニーズを捉えられていなかった事例を紹介。
「本当に必要なものが分かっていればピンポイントで届けられる。自衛隊がラストワンマイル配送を担い、被災地に届けてもらったが、需要を聞いていないので(受け取りを拒否されて)持って帰ってきてしまっていた」と振り返り、「こういう無駄が起きないよう、デマンド(需要)の情報をしっかりつかんで、WMS(倉庫管理システム)のようなものに登録し、輸送を発生させる。最初の情報が食い違わないようにして、救援物資が必要なかったというふうにならないようにしないといけない」と述べた。
才田氏も、警察や消防、自治体など関係者が避難所を訪れるたびに、人数など同じような情報を繰り返し聞かれるため、避難所にいる人にとってもストレスになっているとの話を紹介。「一番基本となる構成人員などの情報をつかめる何かが必要と考えている。インフラを準備しておいて人員構成、必要な物が分かると無駄がなくなる」との見方を示した。
最後に田路氏は9月以降、同協議会としてさらに本格的にフェーズフリー型ドローン物流の実現に取り組み意向を再度表明。防災庁の設立に合わせて、パッケージの原型となるものを作り上げたいと意欲を見せた。
(藤原秀行)