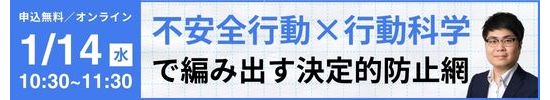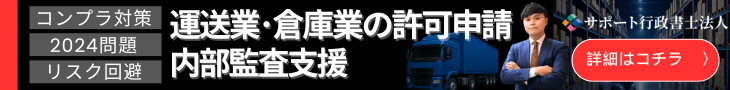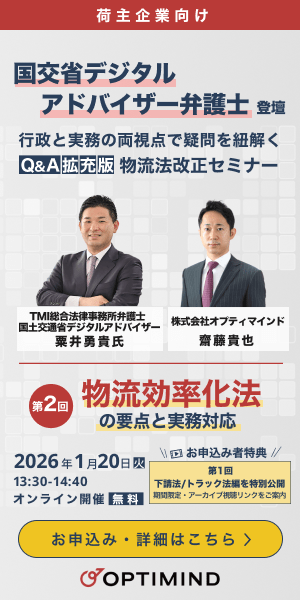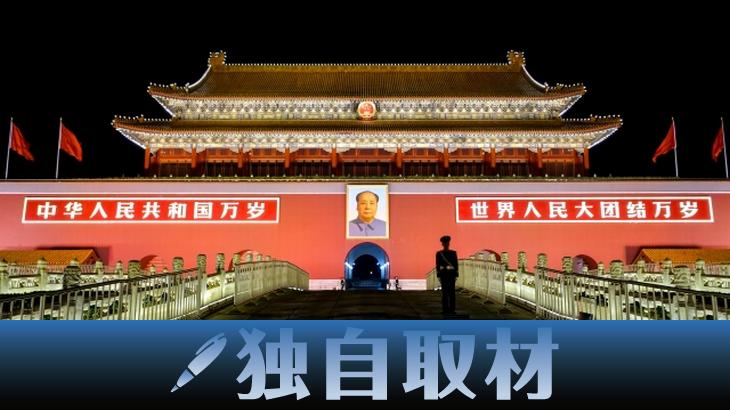研究会も発足、経済・環境効果の評価図る
IHIは10月27日、VHF周波数帯を利用した次世代の海上通信システム「VDES」の実用化を加速するため、東京大学大学院工学系研究科の柴崎研究室(システム創成学専攻)と、VDESの社会実装に伴う経済的効果および環境負荷低減効果を定量的に評価する共同研究を開始したと発表した。
併せて、VDESに関心を持つ研究機関と広く議論し、VDES社会実装の有効性を総合的に評価することを目指すための組織「VDES研究会」を立ち上げた。
VDESは、自船の位置などを通報する装置として普及が進んでいる「AIS」(船舶自動識別装置)の機能を拡張し、船舶や海洋分野を対象に、双方向通信によるネットワーク構築を可能にすることを想定している。
衛星を使うことにより、全地球規模で船舶の安全・安心や洋上業務の連携を実現できると見込まれている。
IHIはVDESを航海に取り入れれば、海上安全の向上、入出港の円滑化、海運の効率化など幅広い分野にメリットをもたらすと想定。安全性向上による流通量増加や、効率化による流通コストの削減など、経済的効果につなげられるとみている。
加えて、航路情報の相互共有により高効率運航が可能となることで温室効果ガス排出量の削減や、排出規制の管理明確化など、環境負荷低減効果も生み出せると考えている。
共同研究と研究会では、船舶から収集した速度や航路といった運航データや貨物データなどを用いて、VDES社会実装時の経済的効果および環境効果を定量的に評価することを予定している。
2028年1月にはSOLAS条約(海上における人命の安全のための国際条約)の改正が予定されており、VDESはAISとともに船舶の法定機器になる見込みのため、各国でも普及に向けた取り組みが進んでいる。
IHIは現在、政府の経済安全保障重要技術育成プログラムでVDESの技術実証を推進するとともに、衛星VDESコンソーシアムの代表幹事としてVDESの利用促進に取り組んでいる。研究会発足により、国内研究機関の協力を得ながら産学官の連携を強化し、VDESの社会実装を推進・加速していきたい考えだ。
(藤原秀行)