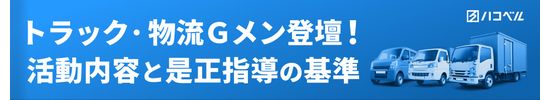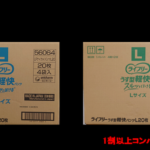第33回:日本企業による対米投資積極化の意義
シリーズの記事はコチラから!
ビニシウス氏(ペンネーム):
世界経済や金融などを専門とするジャーナリスト。最近は、経済安全保障について研究している。
150兆円まで引き上げに意欲
石破茂首相(当時)は今年2月、訪問先の米ワシントンのホワイトハウスでトランプ大統領と会談した。両者は日米関係の新たな黄金時代を追求するとの方針を表明。その際、石破首相は日本が2019年以来、5年連続で世界最大の対米投資国であることを強調した上で、現在は年間約8000億ドル(約120兆円)の対米投資を1兆ドル(150兆円)まで引き上げることに意欲を示した。
こうした政治の動きと連動するように、日本企業の間で対米投資は一種のブームとなっている。例えば、ソフトバンクグループの会長兼社長を務める孫正義氏は昨年12月、2期目就任直前のトランプ氏と米フロリダ州パームビーチで会い、今後4年間で米国に1000億ドル(約15兆円)を投資し10万人の雇用を生み出すと宣言、トランプ氏を大いに喜ばせた 。紆余曲折があったものの、日本製鉄による米鉄鋼大手USスチールの買収は今年6月18日、正式に完了し、USスチールは日鉄の完全子会社となった。日本製鉄による対米投資の行方に注目が集まっている 。
第2期トランプ政権発足の前にはなるが、日清食品ホールディングスの米国法人は一昨年12月、サウスカロライナ州グリーンビルに米国内3カ所目の工場の建設を開始した。ヤクルト本社は2024年7月、100%子会社の米国本社が第2工場の建設をジョージア州バートウ郡で同年10月に開始すると発表した。ヤクルトグループは米国で2014年にカリフォルニア州で生産をスタートさせ、19年には販売エリアを米国全土に広げた。こうした動きは枚挙にいとまがない。
なぜ日本企業が対米投資を積極的に行うのか。その背景にはさまざまな要因があるが、今回は地政学的観点に絞って説明したい。日本企業による対米投資は、戦後から続く日米同盟の基盤を反映し、経済活動を超えた国際政治や安全保障の現実に根ざしている。終戦後に発足した日米安保体制は、日本を米国のアジア太平洋戦略の要と位置付け重視することを柱としており、両国が経済的結び付きを強める原動力となった。
米国は日本にとって唯一の軍事同盟国であり、中国の台頭や北朝鮮の脅威といった地政学的緊張の中で、この同盟の戦略的価値は時間の経過とともに増す一方だ。日本企業による対米投資は、単なる市場拡大の手段だけでなく、同盟国との相互依存を強化する役割も同時に担っているのだ。
そして、経済のグローバル化の時代が終わりへと向かう中、日本は米国との関係を多角的に強化する必要性に迫られている。米中貿易摩擦の激化は、グローバルサプライチェーンの再編を促し、一部の日本企業は中国依存からの脱却を進めている。米国は地政学的な観点から中国への警戒感を強めており、日本に対して純粋な安全保障分野だけでなく、レアアースや半導体など戦略物資の調達という経済安全保障の観点からも対中国で連携を求めている。日本企業には経済安全保障をこれまで以上に意識し、政治と経済が表裏一体の関係にあるという前提で経営戦略を検討する重要性が増している。
米国は友好国を自国市場に引き込む政策を展開している。地政学的な観点から言えば、この動きは日本経済にとってリスクヘッジの1つとなる。例えば、南シナ海や台湾海峡での軍事的緊張は日本にとって直接的な脅威となる。日本は輸出入の100%近くを海上貿易に依存しているが、その大半は南シナ海や台湾近海を通る。日本のシーレーン(海上交通路)はインド洋からマラッカ海峡、南シナ海、台湾とフィリピンの間に位置するバシー海峡を通っているため、台湾有事などが勃発すれば即、日本の経済安全保障を揺るがす。
また、日本は石油の9割を中東諸国に頼っている。シェールガスの産出などでエネルギー大国となった米国から石油や天然ガスを輸入することは中長期的に見て、常に揺れ動く中東情勢からの影響を軽減できることにつながる。前述した今年2月の石破首相とトランプ氏の会談の際、アラスカ産の石油・天然ガス事業に言及があったのは、その証左である。
このように、日本企業による対米投資は、経済的な利益だけでなく、日本の経済安全保障を維持・強化する戦略的手段であり、米国の軍事・外交的影響力を間接的に支援する行為でもある。企業自身にとってもメリットは大きいはずだ。
一見すると傍若無人なトランプ氏の振る舞いに恐れをなして、米国での生産拠点開発などを打ち出しているかのように見えるが、実際にはその重要性と価値を理解し、戦略的に対米投資拡大に踏み切っている企業も多い。ロシアのウクライナ侵略にもなかなか歯止めがかからず、2026年以降も地政学的リスクが沈静化することは見込みにくい中、ここは冷静な判断をする日本企業がさらに増えることを期待したい。
(了)