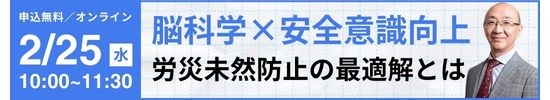第27回:「トランプ関税」の今後を予想する
シリーズの記事はコチラから!
ビニシウス氏(ペンネーム):
世界経済や金融などを専門とするジャーナリスト。最近は、経済安全保障について研究している
新たな協力の模索を促す契機にも
「今日はアメリカの『解放の日』として永遠に記憶される」。4月2日、アメリカのドナルド・トランプ大統領はかねて導入を表明していた、貿易相手国に同水準の関税を設定する「相互関税」の詳細を発表した際、その意義を高らかに宣言してみせた。全ての国・地域に一律10%の基本関税を課した上で、さらに貿易黒字を持つ国々に対して追加の税率を適用することが柱だ。
日本に対しては合計24%の関税を設定しており、4月5日に基本税率が、4月9日に追加税率が相次ぎ発効する予定。さらに、相互関税に先立つ4月3日には、これも既にトランプ大統領が表明していた、輸入自動車全般を対象とする25%の追加関税がスタートした。
一連の「トランプ関税」は明らかにアメリカの対外貿易赤字削減と国内産業保護を目的としており、世界経済に打撃を与えてアメリカ発の不況が広がることを懸念する声が高まっている。さらには同盟国であるはずの日米関係を大きく揺さぶることが避けられない。世界中に「トランプショック」が広がる中、今回の関税政策が日米間の経済的・外交的関係にどのような及効果をもたらすか、最新の動向を基に分析する。
まず、経済的観点から見ると、トランプ関税は日本にとって深刻な打撃となり得る。日本は対米輸出に大きく依存しており、特に自動車産業はアメリカ市場がメーンターゲットだからだ。
自動車関税の引き上げは日本車も対象に含まれる。これまで日本の自動車メーカーは、メキシコやカナダに生産拠点を置くことでコストを抑えつつアメリカ市場に製品を供給してきた。両国にも25%の関税を課すため、自動車業界全体で生産戦略の見直しを迫られている。
例えば、トヨタ自動車や日産自動車はメキシコ工場の稼働を調整し、米国での現地生産拡大を検討する動きを見せている。しかし、アメリカの人件費はメキシコより高いため、コスト増は避けられず、収益への影響が懸念される。
さらに、相互関税の24%に関し、米メディアは日本の非関税障壁を加味した結果だと伝えている。トランプ氏は演説で「日本はコメに700%の関税を課している」「トヨタは米国で100万台以上の海外製自動車を販売している」と不満を表明した。これに対し、日本政府は非関税障壁の緩和を交渉材料として検討している。例えば、コメ市場の規制緩和や電気自動車(EV)の規格統一などが議論に上がっているが、国内農業や産業への影響が不可避の項目だけに、慎重な対応が求められる。経済産業省は関税による輸出減少が日本の実質GDP(国内総生産)を最大1.4%押し下げる可能性があると試算しており、特に自動車や鉄鋼業への打撃が大きい。
外交的観点からも日米関係の行方が懸念される。トランプ政権の「アメリカ第一主義」は、同盟国に多くの不安を与えている。実際、トランプ氏は「敵よりも友の方がひどい」と述べ、日本やドイツを名指しで批判している。この発言は、日米同盟の信頼性に疑問を投げかけるものであり、従来の協調関係に亀裂を生みかねない。
その一方、日本側はトランプ第一次政権時に構築した「自由で開かれたインド太平洋戦略(FOIP)」を再活性化させることで、関税回避の交渉カードとする案を模索している。FOIPは中国への対抗策として日米が共有する戦略であり、取り組みを深化させることで対中姿勢の足並みをそろえ、アメリカが日本に向ける圧力を少しでも緩和しようとする意図がうかがえる。
しかし、トランプ政権の関税政策は、他の政策と同様に一貫性がなく、予測が難しい側面もある。相互関税の発表前の3月、米政府関係者がSNS上で「相互関税は的を絞ったものになり、一部の国は除外される」と示唆したと報じられたが、具体的な除外基準は不明だ。
トランプ氏がこれまで、相互関税で譲歩する姿勢を見せていないことなどを考慮すると、日本が相互関税のうち「上乗せ分」から除外される可能性は低く、むしろ貿易黒字国として厳しい扱いを受けかねない情勢だ。
トランプ氏自身が発表した相互関税のリストを見ると、トータルの関税率が日本は24%、中国は34%、EU(欧州連合)は20%などと国・地域ごとに違っている。そもそも、追加関税の税率を決めた根拠について合理的な説明はなく、日本のエコノミストなどからは、貿易赤字額をアメリカの輸入額で割っただけではないかとの指摘が出ており、アメリカの恣意的な判断が働いていることは明白だ。この不透明さが、日米間の交渉をさらに複雑化させる要因となろう。
これまで見てきた経済・外交両面の影響を踏まえると、日本は短期的には関税によるコスト増と輸出減に直面し、長期的にはアメリカとの関係再構築を迫られる。企業レベルでは、現地生産の拡大や第三国への輸出シフトが対策として考えられるが、いずれも時間と投資を要する。一方、政府レベルでは、関税緩和を求めるアメリカとの交渉で、どの程度譲歩するかが焦点となる。過度な譲歩は国内産業や国民生活に悪影響を及ぼすため、バランスが求められる。また、EUやカナダが報復関税を表明する中、日本も同様の措置を検討する可能性があるが、これは貿易戦争の激化を招きかねない。
結論として、トランプ関税は日米関係に経済的・外交的な緊張をもたらすのが確実だが、異なる視点で見れば、新たな協力の模索を促す契機ともなり得る。日本はアメリカの圧力に屈せず、戦略的な交渉を通じて影響を最小限に抑える必要がある。4月3日時点で状況は流動的であり、今後のトランプ政権の動向と日本の対応が注目される。日米関係の行方は、双方の利害調整と国際環境の変化に大きく左右されるだろう。
(了)