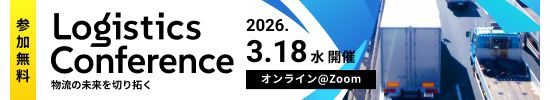MBOで両社社長が会見、強靭な物流インフラ構築と意義アピール
日本郵便の千田哲也社長とトナミホールディングス(HD)の髙田和夫社長は4月16日、東京都内で記者会見し、両社が連携してトナミHDのMBO(経営陣が参加した買収)を実施する件について説明した。
両社長はMBOにより、日本郵便が全国で展開している宅配事業とトナミHDが得意としている特積み事業の相乗効果を発揮することが可能と展望。長距離輸送で地盤としているエリアの重複が少ないことから業務の効率化やサービス内容強化を推進できるとの見通しを語った。

会見する(左から)トナミHD・髙田社長と日本郵便・千田社長

会見後の撮影に応じる両社長
日本郵便は2~4月、トナミHDにTOB(株式公開買い付け)を実施。トナミHD株式の87.24%(議決権ベース)から応募があり、4月17日付で日本郵便がトナミHDを子会社化することが確定した。
最終的には、TOBのために日本郵便が立ち上げた会社が今夏にも日本郵便とトナミHDの経営陣、創業家代表が共同出資する形の「JPトナミグループ」に社名変更し、トナミHD株式を100%保有する形に移行する予定だ。トナミ経営陣は引き続き経営に当たる。2026年にもJPトナミグループがトナミHDを吸収合併することを念頭に置いている。
千田社長は「幹線輸送に強みを持つトナミと日本郵便が協業することで、より強靭な物流インフラを構築し、付加価値を創出することが可能になる。BtoBのお客様にもっと総合的なサービスを提供できる」と意義を強調。両社グループで幅広い領域の物流サービスを展開することにより「価格交渉力の強化も目指す」と語った。
具体例として、西日本を軸に長距離輸送を展開しているグループのJPロジスティクスと、関東・北陸・中部に強みを持つトナミ運輸が協業することで、全国規模で幹線輸送網を強固なものにできるとの見方を示した。
髙田社長はMBOに踏み切った背景として「上場を維持するメリットが相対的に低下していると考え、非上場化の道を模索していた。中長期のさらなる成長、企業価値向上を実現するには外部の経営資源を活用することが必須と判断した」と解説。
さらに、「2024年問題で日本郵便と連携することにより強力な幹線輸送ネットワークの構築につながる。当社グループと親和性が非常に高い」と期待を表明した。
今回のMBOの投資額はトータルで926億円に上る見通しで、日本郵便がそのうちの750億円を担う。日本郵便としては2015年のオーストラリアの国際物流大手トールホールディングスを約6200億円で取得して以来、10年ぶりの大型M&Aとなる。
トールはオーストラリア経済の減速などで4000億円の減損損失を強いられ、その後も一部事業の売却に追い込まれるなど業績は想定ほど伸ばせていない。千田社長はトール買収の件について問われ「両社のコミュニケーションがしっかりと取れておらず、シナジーを作り出していくのが非常に難しかったのが反省点。そういう教訓を踏まえ、われわれは特積みの分野では初心者なのでトナミさんに教えてもらおうという気持ちでしっかりコミュニケーションを取っていきたい」と述べた。

(左から)トナミHD・佐藤公昭取締役、髙田一哉取締役、綿貫雄介創業家代表、髙田社長、日本郵便・千田社長、美並義人副社長、小池信也常務執行役員
(川本真希、藤原秀行)