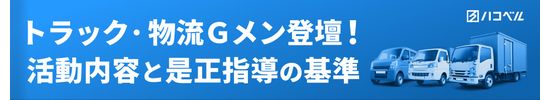Coral Capitalメディア向けセミナーでスタートアップ企業トップら予測
独立系のベンチャーキャピタル、Coral Capitalは10月10日、東京都内で、自社で企画・製造した商品を大手の通販サイトなどを介さず消費者に直販する「ダイレクト・トゥ・コンシューマー(D2C)」の動向に関するメディア向けセミナーを開催した。
Coral Capitalの西村賢パートナーが、米国の成功事例を紹介し、D2C分野で活躍するスタートアップ企業が増えていると指摘。日本でD2C分野に進出しているスタートアップ企業3社のトップも参加し、それぞれが活動している分野でD2Cの取り扱いがさらに成長していく姿を予測した。
併せて、D2Cの事業者向けにロジスティクスを支援するLOGILESS(ロジレス)も登場し、ニーズが非常に多く事業の将来性に自信を見せ、物流面でD2Cを支援していく機会が増えていく可能性を示唆した。物流業界にとってもD2Cは有望な分野といえそうだ。

セミナー会場
米国ではD2C企業の買収相次ぐ
勉強会は冒頭、西村氏がD2C分野の概況を説明。D2C先進国の米国では、ウォルマートが男性衣料品のオンライン販売を手掛けるBonobosを3・1億ドル(約3300億円)で買収するなど、有望なD2C企業を対象とするM&Aが続いており、D2C企業への投資額も上昇傾向にあると解説した。
D2Cが消費者に支持されている背景として、プロモーションにSNSを活用するなどして低価格を実現していることや、単に購入するだけではなく、購入のプロセスを楽しむといった顧客体験を求めていることなどを挙げた。
米国では他にも、一律95ドル(約1万300円)でメガネの通販を行っているWarby Parker、ウールを使い超軽量化したスニーカーを提供しているAllbirdsS、安価なかみそりを定期的に宅配するDollar Shave Club、商品の原価や生産地なども公開しているオンラインのアパレル販売Everlane、子ども服を定期的に宅配するRockets of Awesome、実店舗開設をサポートするUppercaseといったスタートアップ企業が活躍していると強調。
日本でも、オーダーメードスーツの注文をオンラインで受け付けるFABRIC TOKYOが事業展開していることを挙げ、小売業界の中で存在感が着実に高まっている現状に言及した。

解説する西村氏(Coral Capital提供)
続いて、D2C分野で起業した日本のスタートアップ企業の代表がそれぞれ、自社の事業展開をプレゼンテーションした。
化粧品の販売などを担うスマートフォン向けアプリを展開し、自社独自開発のヘアケア商品も販売を開始したNOINの渡部賢代表取締役、体にやさしいユニークなお菓子を継続的に宅配するサブスクリプションのsnaq.me(スナックミー)の服部慎太郎代表取締役、オリジナルのアパレルブランド立ち上げを支援しているpickiの鈴木昭広代表取締役の3人が登壇。D2Cの利点として、ユーザーに商品のビジョンや思想を明確に伝えられることなどを挙げた。
D2C事業者をサポートする立場から、LOGILESS(ロジレス)の西川真央代表取締役が参加。商品を最適なタイミングで出荷することや、配送先ごとに複数拠点の中から最適な出荷元を設定することなどを自動で行い、D2Cを始めたばかりの事業者の初期投資軽減などに効力を発揮していることをアピールした。現状は30程度の倉庫事業者と連携し、複数拠点を確保しているという。
西川氏ら創業メンバーはいずれもECで創業した経験があり、その際に日々出荷に追われた経験からロジスティクス支援サービスを思いついたという。西川氏は「D2Cであっても事業者の方々が(フルフィルメントの)支援サービスを使いこなすのが非常に大変だけに、そもそも自動で出荷させるという世界観を実現している。そこでD2Cの事業者の方々はコアビジネスの商品開発や顧客体験の創造、マーケティングにフォーカスし、出荷の部分をアウトソースすることで、最適化していくような使い方をされている」と分析。
最適な倉庫を探したり増強したりするのも柔軟にできるとのメリットを示し、今後も需要獲得に自信をのぞかせた。梱包やカタログなどの同梱が必要な場合にも対応可能な倉庫を押さえているという。


(左から)鈴木氏、服部氏


(左から)渡部氏、西川氏
新たな顧客体験への対応で物流サポート
最後に、4人が参加したパネルディスカッションを実施、Coral Capital代表兼創業パートナーのジェームズ・ライニー氏が進行役を務めた。服部氏は、ニッチだがこれまで市場に存在しておらず、“かゆい所に手が届く”オリジナリティーのある商品などがD2Cで取り扱うのに向いていると指摘。「基本的にはビジネス的にイケてるかどうかを軸に判断する」との見方を示した。
渡部氏は、化粧品メーカーにユーザーの声をフィードバックすることで、メーカーに直接顧客のことを知ってもらい、より最適なマーケティングや商品開発に生かせるよう協力したいとの考えを強調。ユーザーに支持される商品を自社で作るなどして、通販プラットフォームとして魅力を高めたいとの思いを示した。鈴木氏もアパレルが売れていない今だからこそ、市場のニーズを十分踏まえた「プロダクトアウト」型のブランドを生み出していきたいとの思いを力説した。
西川氏は「D2Cのお客さまが増えている中で、特に事業の立ち上げ期は商品の物量が今後どうなるかを考える余裕がないので(事業の成長に伴い)物流をどうしようと悩む方からの問い合わせが多い」と説明。D2C独特の傾向として、最近は顧客体験を生み出すため、商品を独自の包装でくるんだり香りを付けたりして箱を開けた後まで感動をもたらそうと工夫するケースがあることから「そういうことができる設定、システムを使い、そうした作業に対応可能な倉庫を利用したいという話が増えている」と指摘。物流をサポートする企業の出番も増えていることを示唆した。

パネルディスカッションの模様