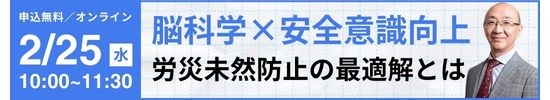郵政3社トップ謝罪会見詳報①
日本郵政の長門正貢社長とかんぽ生命保険の植平光彦社長、日本郵便の横山邦男社長は12月27日、東京都内で記者会見し、かんぽ生命が保険商品の不適切な販売を続けていた問題で金融庁や総務省から行政処分を受けたことを踏まえ、そろって2020年1月5日付で引責辞任することを発表した。会見の詳報を4回に分けて掲載する(発言内容中の敬称略)。

会見に臨む(左から)日本郵便・横山社長、日本郵政・長門社長、かんぽ生命保険・植平社長
深堀りしたグループガバナンスの在り方を検討
冒頭発言:
長門氏
「私ども日本郵政、日本郵便、かんぽ生命保険の3社は本日(12月27日)、総務大臣および金融庁より保険業法などに基づく行政処分を受けた。このような事態を招いたことを深く反省している。お客さまをはじめ関係する皆さまに多大なご迷惑をお掛けしたことについて、深くおわび申し上げる」
「グループの全役職員が今回の行政処分を厳粛に受け止めている。今後、二度とこのような事態を起こさないよう、再発防止に向けて内部管理体制のより一層強化とコンプライアンスの徹底に取り組むとともに、1日でも早く皆さまからの信頼を取り戻せるよう、グループ一丸となって全力を尽くす」
「12月18日の記者会見で、私から責任の取り方について、しかるべきタイミングで報告すると申し上げた。その報告を本日申し上げる。2020年1月5日をもって私と(日本郵便の)横山、(かんぽ生命の)植平、(日本郵政上級副社長の)鈴木康雄、(日本郵便会長の)高橋亨が退任する。後任社長は先ほど各社の取締役会でそれぞれ、日本郵政は東京大公共政策大学院客員教授の増田寛也氏、日本郵便は日本郵政の衣川和秀専務執行役、かんぽ生命は千田哲也代表執行役副社長が20年1月6日付で就任することを決定した。これに加え、3社の関係役員の報酬減などを実施する」
「12月18日に公表した再発防止策について、1点追加でご報告する。日本郵政にタスクフォークを立ち上げることとした。グループ全体の計画を取りまとめ、第三者によるモニタリングを受けつつ、着実に実行、その進捗状況を定期的に報告する。併せて、日本郵政の取締役会において、持ち株会社として果たすべき役割についてより突っ込んだ本質的議論を行い、もう一段深堀りしたグループガバナンスの在り方を検討する」
質疑応答:
――辞任を決意した時期はいつごろか。あの時こうしておけばよかったというような後悔はあるか。
長門氏
「郵政民営化は日本のナショナルプロジェクトであり、参加することでお国に貢献できると思って社長を引き受けたが、このような事態を招き、貢献できるどころか迷惑を掛けている。多くのお客さまからの信頼を毀損し、お国に迷惑を掛けることになり大変断腸の思いだ」
「個人的には8月上旬には責任を取らねばならないと覚悟していた。ごく少数の関係者にその旨をご報告させていただいた。しかし、これは個人的な決断であり、私はグループの経営を担っている責任があるので、その意向を発表できるタイミングは3つくらい条件があるなと感じていた。お客さまに大変なご迷惑と不利益をお掛けしてしまったので、一刻も早く現状をしっかりと調査し、お客さまに不利益をお戻しし、再発防止策をできるところから作って構築していくことを自らのリーダーシップでリードしていくことが大事であり、これをしっかりやらないうちに自分だけ逃げていくわけにはいかない。それが1つ目」
「2つ目は、7月24日に第三者委員会、特別調査委員会を立ち上げ、しっかりと、非常に複雑で広範囲に及ぶ問題と思っていたので、きっちりと厳しい、中立的で厳正な第三者委員会に根本原因、再発防止策を打ち出していただく前に辞めるわけにはいかないと。3つ目は、グループとしてしっかりとした後継者を選ばないうちに辞めるわけにはいかない。本日申し上げたように、大変重い処分を頂戴し、この時期が発表する時期だと思っており、今日に至ったのが正直な、私の心の中のプロセスだ」
植平氏
「6月末に、問題についてマスコミなどで取り上げられて以降、退任ということは常に頭の中にはあったが、まず不利益を被られたであろうお客さまがおられれば、不利益解消にしっかり努めなければいけないということをまず大前提に、特定事案調査の18・3万件の調査と、お客さまが1900万人おられるので、そのお客さまに逐次、ご不満の解消に努める全契約調査の2つを意思決定し、進めてきた。しっかり仕上げることが私およびわがグループの責任ということで、これまでやってきた。12月半ばに調査についても一定のめどが立ってきて、不利益解消についてのお客さまのご要望と対応の体制、必要な不利益解消の手続きなども進めており、募集人の処分の前提となる調査についても、順次進めている。こうした調査のめどがおおよそ立ってきた、それに加えて特別調査委の方で報告書が出されて、内容も確認できた。それから本日付で行政処分の内容が明らかになったということをもって、今般退任の決断をさせていただいた」
「業務推進は常に試行錯誤を繰り返しながらやってきたので、いろんな思い、後悔はあるが、総合対策という品質を引き上げるための推進策をさらに強化していく流れを今般作らせていただいているので、これを今後会社としては継続して進めていくことが大変重要だろうと考えている」
横山氏
「6月末にこの問題を認識して、まず何よりも不利益を生じさせてしまったお客さまに謝罪し、不利益解消に努め、再発防止策を講じていくことが弊社としてやるべきことということだった。再発防止策をある程度のところまでまとめ、そして特別調査委の中間報告などがまとまり、そして今日、行政処分を受けた。やはり、いろんな報告などのけじめの中で、12月くらいから辞任というけじめをつけることは意識していた」
「高齢者のお客さまとの取引について苦情が増えてきているというようなこと、中身については説明が不十分でお客さまが勘違いされるということも多かったので、植平と対策本部を作り、いろんな対策を打ってきた。そういう中で、高齢者のお客さまへの説明の在り方についてはできてきたというふうに認識しているが、かんぽの募集全体について、全部それができていたかというと十分ではなかった、道半ばだったということについて、後悔をしている」

大勢の報道陣が詰め掛けた記者会見場
「ユニバーサルサービス」は制約外して
――郵政のトップはこれまでも有能と言われている方たちが民間や官界から来て、一生懸命やったにもかかわらず、皆さん挫折し、不本意な退場を繰り返してきた。長門氏で6人目になる。その原因は何と考えるか。個人の能力なのか、構造の問題なのか。横山、植平両氏は横から見ていて、郵政という組織はどうしてこのようにうまく行かないと感じるか説明してもらいたい。
長門氏
「経営は結果責任なので、今回こういう形で辞任になっている。なぜ自分自身の思惑通りに動かず、うまく行かないのかというご質問だが、特別調査委が日本郵政をめぐる問題点を分析されている。そこになったのは、グループをめぐるいくつかの問題点、いろんな要因がありこういうような環境ができていた、直接的な理由とか助長した要因とか、構造的問題とかいろいろあるので、ここでは繰り返さないが、いろいろな事情があって、なかなか難しい経営環境があったというのが1点ある。だた、どんな組織や会社にも難しい問題点はあるので、これがあるから負けたのだというのでは経営にはならない。そういう問題をしっかりと本来は把握してやるべきだった。力が及ばず、こういうことになったと感じている」
「2つ目はあえて特別調査委の調査などでいろいろ指摘された問題点のほかに、先ほど申し上げた自身の反省点の関連で申し上げると、戦略的に目指していた方向性は大きく違ってはいなかったと思っている。民営化を進める中で最大の問題点はゆうちょ銀行、かんぽ生命の株を切り離す、100%分かれているが、ビジネスモデルはゆうちょもかんぽも郵便局ネットワークなしには決して立ち行かない組織なので、引き続き郵便局ネットワークと密接に連なって、やっていかなければならない。彼ら自身の問題点があって、新商品や新業務、海外での買収など、これはこれでやっていけばいい。郵便はおととしに172億通、昨年は167億通と毎年2・5%くらい(取扱量が)落ちていく中で、どうやって食っていくのか、かつゆうちょ、かんぽの売り上げも失う宿命がある、新たな時代の流れに乗って売り上げなり収益なりを作るというのは、郵政グループの大きな課題との認識の下に、現在の中期経営計画を作った。そんなに戦術、戦略が間違っているとは思わない」
「従って、私も新しいレベニュー、新しい収益をどうやって作るのか、M&A、投資、いろいろと考えて、企業との提携、日々全身全霊で尽くしてきたつもりだが、大きな経営者としての欠陥があったとすれば、肝心の足元を見ていなかった。日ごろからコンプライアンス重視、築城3年落城3日、これで一瞬に失うと言ってきた本人が、全くそのへんがチョンボだった。何か大きな環境があって、それが今回経営に失敗したんじゃないかという問い掛けだと思うが、やるべきことをやるという経営の基本路線を踏んでいれば非常に難しい環境にある会社の経営だったとは思うが、十分にやれたはずなのに、こういうことで皆さまにご迷惑をお掛けし、大事件となり国民に迷惑を掛けているのは、ひとえに私の経営力のなさだと思っている。環境のせいではないと深く反省している」
横山氏
「経営上何が難しいかという観点で申し上げたい。私どもの仕事は、全国2万4千の郵便局でゆうちょ、かんぽ、そして郵便の(全国一律に提供する)ユニバーサルサービスを行うことを国から託されている。しかしながら、実際にビジネスをやっていく上では、長門も申し上げた通り、商品性の問題などなど、いろんな制約、手かせ足かせもある。従って、こうしたユニバーサルサービスを行うのであれば、制約を外していただくことが筋だと考えている。そういう中で、私どもの仕事で見れば、制約のない宅配事業はこの2 年くらい、ビジネスの抜本的な評価を行い、いろんな観点で商品性をアップさせ、戦略も再構築した。その結果、3~4年前と比べると宅配ビジネスが経営全体に奏功し、営業利益で見れば従来とは異次元の2000億円近い利益を上げるような会社になったということは、やはり制約がないビジネスをしっかりやればこういう状態にあるということではないかと思う」
植平氏
「先ほど来、話が出ているように、既に特別調査委の方で直接的な原因、助長した原因、あるいは構造的な要因を取り上げられており、こうしたものが複合的に絡み合ってなかなか難しい状況になっているとは理解している。この場で何が理由でどれが、ということを1つ1つ取り上げて言うのは少しせんないものがあると思うが、私としては商品供給を行う保険会社としての立場だったので、大変痛恨の極みは、限度額の付いていない商品ラインアップが豊富な、そういう商品を日本郵便の優秀な募集人の方々に広くあまねく提供できる状態に早く持っていきたい、持っていければと考えている。これからさらにわれわれも精進をして、そういう時代を早く迎えるべく、頑張っていただきたい」
(藤原秀行)