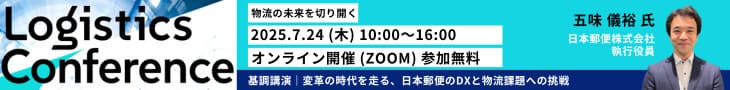ラクスルとロジビズ・オンラインが共同ウェブセミナー開催
ラクスルとロジビズ・オンラインは7月29日、『先行事例に学ぶ アフターコロナのDX』と題するウェブセミナーを共同で開催した。
両社がセミナーに先立って実施した、新型コロナウイルス感染拡大が物流現場に及ぼしている影響などに関するアンケート調査結果を基に、ラクスルの鈴木裕之ハコベル事業本部ソリューション推進部長とロジビズ・オンライン編集長の藤原秀行、ゲストとして登壇した日通総合研究所の井上浩志リサーチ&コンサルティングユニット4ユニットリーダーの3人が物流領域のDX(デジタルトランスフォーメーション)実現に向けた進め方などについてプレゼンテーションを実施。
併せて、パネルディスカッションも行い、コロナ禍に見舞われている現状を踏まえ、物流現場の安全確保に不可欠な「密回避」のためにもDXによる業務効率改善を積極的に推進すべきだとの認識で一致した。
当日は物流企業、荷主企業の管理職や経営層を中心に約190人が参加した。
※この場を借りまして、セミナーにご登壇、ご協力いただきました各位とアンケートにご協力いただいた皆さま、セミナーにご参加いただきました皆さまに、あらためまして厚く御礼申し上げます。

パネルディスカッションに臨む(左から)鈴木氏、藤原編集長、井上氏
アナログ作業が招くセンター停止の危機
セミナーは冒頭、日通総合研究所で倉庫業務の“見える化”実現を後押ししてきた井上氏が「コロナで露呈したアナログ業務のリスク」について講演した。
井上氏は事前のアンケートで物流企業の85%がコロナの影響があったと回答したことに言及し、「おそらく緊急事態宣言で急激に荷物が減り、外部環境の変化で間接的に影響を受けたケースが多いと思う。今後、コロナ感染者が拡大していく中である程度直接的な影響も考えていかなければならないフェーズに来ている」と解説。その具体例として、首都圏のある物流センターでスタッフ1人が感染した結果、同僚24人が自宅待機を余儀なくされた事例などを挙げた。
「各物流施設で1つのチームを2つに細分化して感染リスクを下げるといった取り組みが行われているが、人手に頼った作業、ベテランに依存した作業が多い現場は必然的にハイリスクになる。特にセンターのキーパーソンが自宅待機となったりクラスター(集団感染)が起きたりすれば出荷遅延にとどまらず、最悪の場合は倉庫の稼働停止もあり得る」と指摘し、コロナがもたらす現場混乱のリスクへの警戒をあらためて喚起した。
物流業界でデジタル化が進まない原因について井上氏は「日々取扱量の波動が生じたり、荷主企業から出荷先ごとに個別の対応を求められたりと、物流業には自社でコントロールが難しい要素が多い」と分析。そうした環境下で自動化した場合に取扱量が現場の能力を超え対応しきれなくなることを非常に恐れ、「人でできることは人で何とかした方が安心」という考え方に陥りがちだと述べた。
デジタル化に向けた第一歩としては、まずはイレギュラーな業務や属人化した業務を洗い出し、標準化に向けて自社でできる改善をすぐに行うとともに、必要な場合はエビデンスをそろえて荷主とも論理的に良い方法を話し合うことが必要だと語った。また、費用対効果にあまり固執せず、少額でもデジタル化へ挑戦するための予算を確保し、まずは割安なクラウドサービスを使うなどしてトライ・アンド・エラーを図る風土を醸成していく重要性も強調した。

井上氏
輸配送デジタル化の鍵は協力会社の参加
続いてラクスルで求荷求車と車両管理のプラットフォーム「ハコベル」事業を手掛ける鈴木氏が登場。「ネットワーク型TMS(運行管理システム)による協力会社のデジタル化支援」と題した講演を行った。
鈴木氏は輸配送のデジタル化の課題は主に作業の標準化と企業間連携の難しさだと明言。特にサプライチェーンの中で一番下流の工程に位置している輸配送業務には多くの協力会社が関わっているため「個別化、属人化に陥りやすい」と井上氏の意見に同調した。
その上で、ハコベルが推し進めてきた、荷主と協力会社の双方が同一のプラットフォームを利用する「ネットワーク型TMS」の取り組みに触れ、運送会社にシステムを利用してもらうため、関係者に必要な支援策を適宜提供し、迅速に慣れてもらう「オンボーディング」を重視していることを紹介。
「協力会社や委託先の全てにきっちりとシステムを使っていただける段階まで電話や訪問でサポートしている。そういったプレーヤーをネットワーク化していくところに当社の強みがある。荷主企業だけでなく、協力会社の業務工数も削減できて皆が楽になる仕組みを提供している」と説明し、「DXは人が担っていくものだ」との信念を力説した。
さらに、ネットワーク化でつながったデータを利用してコストを可視化し、最適化する仕組みの構築を進めており、具体的な成果も徐々に現れてきていることを明かした。

鈴木氏
EC物量急増をロボットの大々的な活用で乗り切った
最後にロジビズ・オンラインの藤原編集長が登壇。最近の取材で対峙した事例を交えて「倉庫作業の自動化とこれからの物流施設」について持論を語った。
藤原編集長は「コロナ問題で注目は増しているものの、そもそも物流業界には深刻な人手不足という土壌があり、自動化・省人化は既に必須の課題だった」と指摘。今後20年間でおおよそ1500万人の人口が減るという推計などに触れ、その切迫感を前提として共有する必要があると提言した。
藤原編集長は物流施設デベロッパーによる自動化支援の動きを紹介。大和ハウスグループのアッカ・インターナショナルがナイキの物流センターでロボットを大々的に活用し、スタッフ約2000人分に相当する業務をこなしてコロナによるEC利用の急拡大を乗り切った事例などを挙げ、「こういった事例が出てくると、もはや機械化は必須とも思える」と強調した。
その上で「施設を貸すだけではもはや差別化を図ることはできず、人手不足に悩むテナント企業のニーズにも答えられない。デベロッパーによる自動化支援は間違いなく広がっていくだろう。その潮流はテナント企業にとってもDXを進める上で大きなチャンス」と話した。

藤原編集長
この2年でDX進めた会社がリーダーシップを取る
最後に、「アフターコロナの物流業界-デジタル化へのロードマップ-」と題し、登壇者3人でパネルセッションに臨んだ。
井上氏が「物流センターをいくつか回ったが、食堂の席についたてを設けたり、消毒箇所のチェックリストを作ったりしていて、皆さん意識が高い。しかし一方で、投資をしてまで何かやるまでには到っていない印象だ」と発言。鈴木氏も「このまま喉元を過ぎるとデジタル化まで行かず、目先の対策だけで終わってしまうかもしれない」と同意した。
井上氏は、内閣府の「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」の中で日通総研が参加している医薬品・医療機器物流のスマート化の取り組みを紹介。「一番驚いたのは、治具やドリルのような機器など医療機器に関して重量、容積といったデータがほとんどなかったことだ」と語り、DXの大前提として関係者が共有できるよう入出荷などのデータを整備する必要性をアピールした。
鈴木氏も「荷物の三辺データや重量データがWMS(倉庫管理システム)には入っておらず、別に管理されていることは多い。データをきれいにそろえていくプロセスを必ず噛ませてからDXプロジェクトの実際が始まる」と自社の経験に言及しながらデータを使いこなす環境の整備を訴えた。
セッションの終盤には、3人が今後の物流DXの進展について持論を展開。井上氏は「コロナでデジタル化が2年くらい前倒しに進んだと言われている。自分は特にソリューションの連携が始まりだしたことに期待している。いろいろな部分が連携しながらデジタル化する動きがぐっと進めば、2年くらいでかなりの進展があるのではないか。しかし、現状の仕組みで何とかなってしまった場合はもっと時間がかかるかもしれない」と展望した。
一方、鈴木氏は「逆にこの2年という時間軸でDXを進めた会社が足回りの物流でリーダーシップを取るのではないか」と先行者利益の大きさを予想。藤原編集長は「記者としての個人的な願望も大きいが、ドローン(無人飛行機)やトラックの自動運転といった先端技術活用を含めた完全自動倉庫は5年くらいでできると思っている。それくらいの意識を持って物流業界の皆さんには取り組んでいただきたい」と述べ、物流業界の積極的な姿勢に強い期待をにじませた。
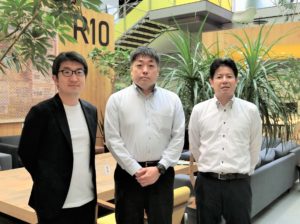
ラクスル本社での記念撮影
(川本真希)