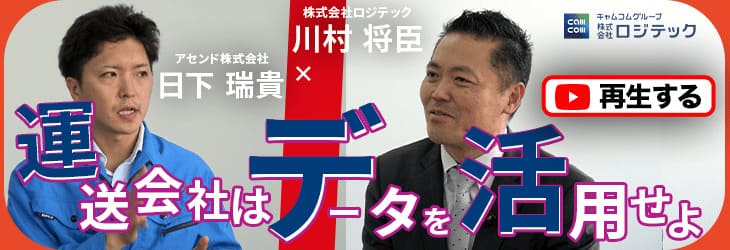Shippioがリポート公開、可視化・標準化・連携を強く提言
輸出入業務を効率化するクラウドベースの貿易業務ソフトを手掛けるスタートアップ企業のShippio(シッピオ、東京都港区西麻布)は2月4日、「サプライチェーンの課題と必要なこと」と題した独自のリポートを公表した。
この中で、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、企業はより安定的かつ柔軟性の高いサプライチェーンを構築するため、在るべき姿や戦略を再度見直し、抜本的に変革する必要があると指摘。DX(デジタルトランスフォーメーション)を念頭に置いて早急に取り組むよう強く呼び掛けた。
同社は今後、貿易やサプライチェーンのDX推進のための必要な要素について定期的にリポートを公表する予定。
「貿易にかかわるビジネス環境、日本は米国や中国、韓国より下の57位」
Shippioはリポートで、日本のサプライチェーンが抱えている課題として、
①特に若年層の人材不足
②カスタマイズされたサプライチェーン
③属人的・労働集約による非効率
――を列挙。
①についてはECの利用増加などでトランザクションの数量や仕事量が増えている半面、「恒常的な労働力確保が期待されるが、特に若者にとって物流業界は魅力的な業界に見えていないこともあり、人材確保に苦戦している」と指摘した。若い労働力が足りない一方で従業員の高齢化が進み、「新しいサービスが生まれにくい業界風土に落ちっている可能性もある」との危惧も示した。
②は、「日本のサプライチェーンは、カスタマイズを念頭にした設計思想が強い。コモディティーとも言える物流サービスの差別化として、個社に合わせる形でサービスを展開・提案してきた」と分析。コロナ禍のように急な調達先変更や生産量調整などへ柔軟に対応する点で課題があると解説した。
さらに、各事業者間の商流や物流の一部は電子化などで効率化が図られたものの、全体最適を推し進めるための抜本的な対策が遅れていると強調した。
③は、貿易・物流業界の働き方は属人的かつ労働集約的な側面が強く、文書による情報共有や意思疎通が前提・慣習となっているため非効率につながっていると懸念を表明した。貿易にかかわるビジネス環境の調査結果では、日本は57位で米国や中国、韓国にも抜かれていることに言及、国内の産業別労働生産性を見ても卸売・小売業や物流業界は他産業に比べても低く、効率的に収益を上げられる体制構築に至っていないと明言した。
3点を踏まえ、「日本の国際競争力のさらなる向上、国内経済活動へのさらなる貢献、より一人一人が働きやすい環境の整備などの観点から、引き続きより効率的・効果なサプライチェーン設計、商流・物流の追求が必要」と訴えた。
「テクノロジー導入はあくまで手段、目的ではない」
リポートはその上で、解決策となるポイントとして、
①可視化
②標準化
③連携
――を打ち出した。
①は各業務プロセスを組織内外で明確に定義し共通認識を持つことや、KPI(重要業績評価指標)を策定して責任と権限を明確にすることなどを挙げた。
②は①とも関連し、業務プロセスやデータを徹底的に可視化した上で各業務プロセスの内容を明確にし、規格を統一するよう提言した。
③はサプライチェーンに関係する当事者が多岐にわたり、複雑化している中、「各プレーヤーとの効率的な連携がなければサプライチェーンが成立せず、商流や物流が止まってしまう事態にもなりかねない」と警鐘を鳴らすとともに、連携の前提として可視化や標準化が必要とアピールした。
締めくくりとして、「日本のサプライチェーン戦略はもう少し経営に近い位置付けに置かれるべきだと考える。そのような意識が薄い企業だとサプライチェーンに関する取り組みは各々の現場任せになり、個別最適を重視した取り組みにならざるを得ず、上述で述べた可視化、標準化、連携が実現叶わず頓挫するケースが多い」と警告。トップダウンとボトムアップの両方のアプローチで迫るようアドバイスした。
併せて、可視化と標準化、連携を関係者の間で十分に浸透させた上で、IoT(モノのインターネット)やブロックチェーン、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などの技術活用を検討するよう提言。同時に、「テクノロジー導入はあくまでも手段であり、目的ではない。その意識が不十分だとせっかくのテクノロジーの効果が限定的にとどまってしまう」と総括した。
(藤原秀行)