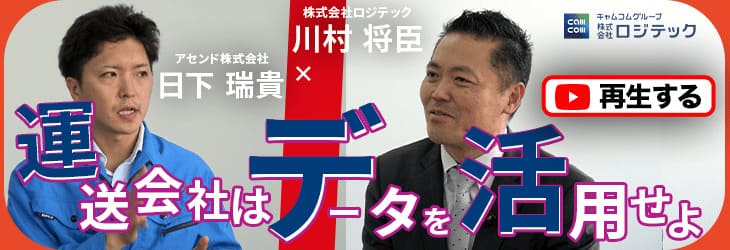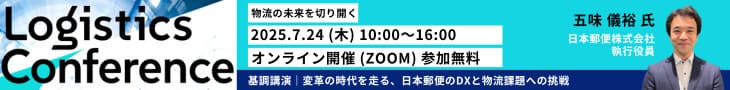ONE・塩見氏、パワーエックス・伊藤氏、ゼロボード・渡慶次氏が持論展開
Shippioは3月2~3日、オンラインで大規模なカンファレンス「Logistics DX SUMMIT2023」を開催した。
国際物流とDXをメーンテーマに設定。登壇者は物流業界に加え、シンクタンクやロボットメーカー、大学、IT企業、ベンチャーキャピタルなど様々な領域から知識や経験が豊富なメンバー30人以上が集まり、物流業界が直面する人手不足やデジタル化の遅れなどの諸課題にどうやって立ち向かうか、処方箋について活発に意見交換した。
ロジビズ・オンラインでは、各セッションを順次、詳報している。第4回は3月2日に実施した、「カーボンニュートラル実現に向けた物流の役割とは」と題したパートを紹介する。
邦船大手3社が2017年にコンテナ船事業を統合して誕生したOcean Network Expressの塩見寿一バイスプレジデント、EV(電気自動車)用充電器の製造・販売などを手掛けるパワーエックスの伊藤正裕社長、企業の温室効果ガス排出量測定サービスを展開しているゼロボードの渡慶次道隆代表取締役が参加。進行役はローランド・ベルガーの小野塚征志パートナーが務めた。
4氏はカーボンニュートラル(温室効果ガス排出実質ゼロ)実現へ物流がどのような役割を果たしていくべきかについて意見を交換。塩見氏は物流を担う最前線の立場から、船舶の代替燃料導入など技術面の取り組みと併せて、船舶の運航効率化など現行のオペレーション変革を徹底して推し進めていくことの重要性を指摘した。
渡慶次氏は物流業界も含めて、サプライチェーンからの温室効果ガス排出算定などのルール設定の場にも積極的に携わっていくことで日本の産業競争力が高まると主張。伊藤氏は再生可能エネルギーを港湾でも普及させていくことが重要と強調した。
さらに、脱炭素を展開していく上では経済合理性を踏まえた「ファイナンシャルな持続可能性」を重視すべきだとの見解を示し、関係者がそれぞれ利益を得られるような形で推し進めていくことの必要性を訴えた。

(左から)小野塚、塩見、渡慶次、伊藤の各氏(オンライン中継画面をキャプチャー)
ガントリークレーンやリーファーコンテナにも再エネ活用を
冒頭、小野塚氏は物流領域からのCO2排出が全体の7~8%を占めているとの推計結果を引用し「物流を無視していたらカーボンニュートラルは実現できない」と強調、脱炭素の取り組みの重要性に言及した。
渡慶次氏は脱炭素化の原点となるサプライチェーンからの正確な温室効果ガス排出量算定を進める上で、物流業界の多重下請け構造が課題になっていると説明。「協力会社から(配送量などの)情報をもらわないと正確な排出量が見えないが、中小事業者は知見を持ち合わせておらず、データが出てこない」と語った。
塩見氏は、海運領域の脱炭素の実態として、海上コンテナ1本の輸送当たり、どの程度温室効果ガスを出しているかを算出するのは、陸上輸送の部分も含まれる上にそれぞれ行き先や積み荷が細かく異なることなどから非常に難しいと説明。「コンテナは常に実(荷物)が入っているわけではないので、空のコンテナは誰のところに(排出量を)計上すべきかという議論もある。いろんな形で試行錯誤している」と明かした。
渡慶次氏は温室効果ガス排出のシステムに関し「どういうデバイスを(船やトラックなどに)積んでもらい、どのように(データを)吸い上げていくのか、このへんの共有基盤的なものが、確実に必要だろうなというのが、われわれがやろうとしているプラットフォームの中で見えていること。今業界団体で、かなりグローバルに規格作りが進んでいるので、そのへんのリサーチもしながら、ソフトウェアの実装をしていこうとしている」と現状を解説した。
伊藤氏は「脱炭素をちゃんとやるためには、エネルギー、つまり燃料と電源をクリーンにすることが大原則。ガントリークレーンの電源を系統(の電力)から引くと7割は火力になってしまう。さらに港へ置いたリーファーコンテナへの給電も7割が火力になる。そこにソーラーや風力(由来の電力)を持っていきたい」と主張。船の運航計画に従い、再生可能エネルギー由来の電力で蓄電池を充電しておき、積み降ろしの際の作業に活用することで港湾の脱炭素を推進できるとの考えを示した。
渡慶次氏は「費用対効果が高いソリューションを皆さん導入したいと考えており、ベストはコスト削減とGHG(温室効果ガス)削減が同居するもの。燃料価格が上がっていると当然投資回収(を目指す期間)が早くなっているから、取り組みが増えている。少しでも経済的なメリットを出しながら排出量を下げてもらうのが、全体的には効率の良い削減になる」と説明。脱炭素を進める上で、経済合理性を重視する必要があると持論を展開。そのために、物流事業者らにとって最も経済合理性がある脱炭素のソリューションをマッチングすることに注力していることを明らかにした。
伊藤氏も「スコープの1、2、3のいずれの段階にしろ経済合理性が重要。再生可能エネルギーの方がもうからないと駄目だ」と渡慶次氏の主張に賛同。「どういう設備投資をすると何年で回収できて、CO2もどれだけ減らせて、といったリアルな見積もりが全部出た上で、この設備投資はこれだけコストが下げられて、ちゃんとしていればリースで組もうとか、これにローンを付けようとか、これは補助金でこういうものが申請できるとか、ワンストップで行ければ便利だなと思う」と語り、渡慶次氏が展開しているような温室効果ガス排出算出のサービスが、効果的な脱炭素の施策提言と導入支援までカバーしていくことに期待をのぞかせた。
ルールメイクの側に回るべし
塩見氏は海運の脱炭素を進める上で留意すべき点として「外航海運の場合、水素で長距離を走らそうとすると、エネルギー密度の問題でどうしてもタンクをたくさん積まないといけない。そうすると荷物を積めなくなり、経済性が阻害されてしまう。蓄電池も同じで、少なくとも今のテクノロジーレベルだとおそらく電池を運ぶことでていっぱいになってしまうだろう」と説明。
「よく国際系の環境会議に出ると、皆さん一足飛びで、じゃあ代替燃料の話をしようということになるが、その前にやれることは実はたくさんある」と述べ、具体策として、船舶の船首に風防を取り付けることで風圧の抵抗を減らし、燃料費を2~3%削減できた事例などを紹介。「新しいテクノロジーは必ず必要で、このままやっていても(温室効果ガス排出は)ゼロにはならないが、ゼロにする前に、まず精いっぱいダイエットすることが大事。その後おそらく、新しい燃料やテクノロジーが開発されていくということになろうかなと思っている」との見解を示した。
ONEでは20,000TEUの超大型船
🚢ONE TRUST (2022年10月)
🚢ONE TRADITION (2022年11月)の2隻に対して"Bow Wind Shield"
(風防)を取り付けましたBow Wind Shieldは当社のグリーン投資の一つであり、二酸化炭素排出量の削減と環境に優しいサービスの実現を目指していきます! pic.twitter.com/9DDXy3zZ9s
— オーシャン ネットワーク エクスプレス ジャパン 株式会社 (@ONE_LINE_JAPAN) March 10, 2023
(TwitterのONE公式アカウントより)
渡慶次氏は、温室効果ガス排出抑制のルール設定などで欧州が先進的に取り組み、主導しようと努めていることに言及。「当然、再生可能エネルギーが豊かな国、ポテンシャルが高い国は特に有利になりやすく、そういう国が主導することでルールが作られていく。ここで後手に回らず、きちんと(脱炭素の施策を)やることでプレゼンスを上げていく。それによってルールメイクの側に回っていく。この仕組みを作っていくことがすごく重要だし、ルールは統一されていく方向だと思うので、その中で可視化がすごく重要」と、日本の先行した対応が不可欠と指摘した。
誠実な会社が利益を得られる社会目指そう
塩見氏は、水素やアンモニアといった代替燃料について、現行の燃料より価格が4~5倍程度と説明。「だいたい平均的なコンテナ船会社の費用に占める燃料代の割合が3~4割なので、その部分が4~5倍になるのは、コストが2倍以上ということ」と語り、費用面で代替燃料の活用が非常に厳しいことを報告した。
その上で「一般的にサステナブルはGHGの削減を指すと思うが、僕らはファイナンシャルにサステナブルでなければいけない。すなわち、海運会社、物流会社は水や電気、ガスといったインフラと同じく、続けられる形にすることが大事なので、全てはクリーンな物流のために、行くべきところにお金が行く仕組みが必要」と説明。
一例として、船会社側が港湾のターミナル運営会社側に到着時間を正確に伝え、ターミナル運営会社側も受け入れ可能な時間を連絡することで、船の待ち時間がなくなり余計なエネルギー消費が解消されると指摘した。その上で「船は波などのいろんな要件があり、速度の3乗に比例してエネルギーを使っているといわれる。消費量を10%減らせればすごく効果がある。(船会社とターミナル運営会社が)お互いが正直に言い合うことで、お互いにエネルギーを減らせる。やれることはいっぱいあるし、細かいマネージ、素直に正直にきっちりやっていくのは日本の得意なところなので、こういう取り組みが世界に広がっていけばいいと思う」と語った。
渡慶次氏は「ESGがそもそも(環境負荷低減努力など)財務諸表に表れてこなかったものの透明性を高めて評価していこう、きちんと誠実に会社をオペレーションしている会社を評価していきましょうという流れなので、まさにおっしゃった通り、オネスト(誠実)な会社が利益を得ていくことを社会全体として達成していくのが非常に重要だ」と主張、塩見氏に同意した。
伊藤氏は「海外より日本のソーラーの方が安いというようなソリューションがどんどん生まれつつあり、われわれのようなサービスが伸びて産業創出が起きている。皆さんが経済合理性に基づいて、脱炭素をするという約束の下で意思決定されていけば、自然と進んでいくものだと思っている。日本は今ポジションとして悪くないのではないか」との見方を示した。
塩見氏は「脱炭素の話は、1つの荷物が最終的に流れていくまでの過程をいかに効率的に、いかにエコなモードで、安くするかという大変難しい課題を全部達成していかないといけない。物流事業者に任せるではなくて、荷主さん、受け取り手さんもそうだが、そこまで含めたものが物流のチェーンであり、その中でそれぞれご自分の役割を果たしてほしい」と語った。
渡慶次氏は「プラットフォームを作っていく上で、ルールはギブン(与えられる)なものではなくて、自分たちで作っていくもの。特にカーボンニュートラルは今まさにルールが作られているところなので、怖がらずに、ルールづくりに参加していくということが非常に重要なんじゃないかと思う」と、物流業界などの自発的な行動に強い期待を示した。
(藤原秀行)