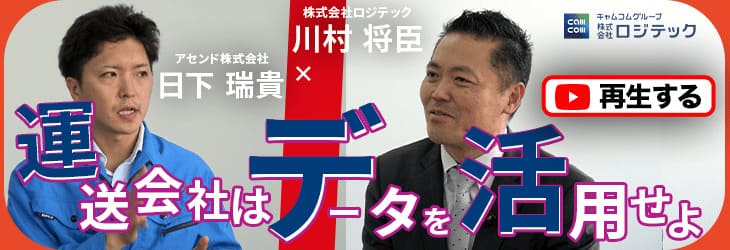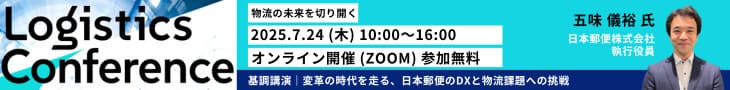関係3省が審議会の取りまとめ公表、政省令交付など経て25年度から2段階で施行へ
経済産業、国土交通、農林水産の3省は11月27日、「物流2024年問題」対策のため荷主企業や物流事業者にトラックの荷待ち・荷役時間短縮を図るよう義務付けることなどを柱とした改正物流総合効率化法(施行後は名称を物資流通効率化法に変更)に関し、業務効率化推進に関する基本方針などの詳細部分について、3省関係審議会の合同会議による取りまとめ内容を公表した。
基本方針として、荷主や物流事業者ら関係者が協力して業務効率化を図ることで、2028年度までにトラックの運行全体の5割で、1運行当たりの荷待ち・荷役などの時間を計2時間以内に抑えることと積載効率50%を達成することを目標に設定。車両全体では積載率を44%まで引き上げる方針を示している。
そのため、荷主や物流事業者らに対し、積載効率向上、荷待ち時間短縮などに取り組むよう要請。政府としても再配達削減や通販の「送料無料」表示見直しなどについて国民の理解を増進していくことを打ち出している。
また、荷待ち・荷役時間短縮に向けた具体的な方策を盛り込んだ中長期計画の作成と進捗状況の定期報告を義務化する「特定事業者」の条件を決定。特定事業者に指定された荷主と連鎖化事業者に選任を義務付けるCLO(物流統括管理者)の業務内容や選任する人材の条件も設定している。
3省は取りまとめ内容に沿って政省令の交付などを順次進め、改正法のうち基本方針などの部分は25年4月、特定事業者の指定や中長期計画の提出・定期報告、CLO選任などの部分は26年4月にそれぞれ施行、制度をスタートさせる予定。
取りまとめ内容の概要は以下の通り。
・物流は国民生活や経済活動、地方創生を支える不可欠な社会インフラ。担い手の確保に支障が生ずる状況でも将来にわたって必要な物資が必要な時に確実に運送される必要があることを明記する。
・物流は、物資の生産や製造の過程、消費と密接に関連し、かつ荷主(発荷主・着荷主)、物流事業者(トラック、倉庫、鉄道、内航・外航海運、港湾運送、航空運送、貨物利用運送)、施設管理者、消費者などの多様な主体により担われていることに鑑み、物資の生産や製造を行う者、物資の流通の担い手その他のサプライチェーン全体の関係者が連携を図り、その取り組みの効果を一層高める必要があることを明記する。
・目標として以下を設定する。
①令和10年度(2028年度)までに、日本全体のトラック輸送のうち5割の運行で荷待ち・荷役等時間を1時間削減し、トラックドライバー1人当たり年間125時間短縮する
②トラックドライバーの1運行当たりの荷待ち・荷役などの時間が全国平均で計2時間以内となるよう削減する
③荷主などは1回の受け渡しごとの荷待ち・荷役等時間について、原則として目標時間を1時間以内と設定しつつ、業界特性その他の事情によりやむを得ない場合を除き、2時間を超えないよう短縮する。既に1時間以内の荷主等は継続・改善に努める
④令和10年度までに、日本全体のトラック輸送のうち5割の車両で50%を目指し、全体の車両で44%への増加を実現する。トラック輸送1運行当たりの輸送効率の向上は重量ベースだけでなく、容積ベースでも改善を図る
⑤目標達成に向けた取り組みを通じてフィジカルインターネットの実現を図るとともに、地球温暖化対策推進法に基づく地球温暖化対策計画に対策・施策として位置付けられている脱炭素物流の推進に貢献する
▼荷主・物流事業者などの判断基準
・全ての発・着荷主、連鎖化事業者(フランチャイズチェーン運営事業者)、物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課す。政府は取り組み例を示した判断基準・解説書を策定する。盛り込む内容の例は以下の通り。
①積載効率の向上など
・共同輸配送や帰り荷の確保
・適切なリードタイムの確保
・発送量・納入量の適正化 など
②荷待ち時間の短縮
・トラック予約受付システムの導入
・混雑時間を回避した日時指定 など
③荷役等時間の短縮
・パレット等の輸送用器具の導入
・タグ等の導入による検品の効率化
・フォークリフトや荷役作業員の適切な配置 など
・国はトラック運送サービスの持続的な提供の確保に資するトラッ クドライバーの運送・荷役などを効率化するのに必要があると認める場合、荷主などの判断基準に関して取り組み状況の調査を行い、結果を公表する
・「荷待ち時間」と「荷役等時間」の算定方法を国が省令で定める
▼「特定事業者」の指定基準や「CLO」の条件など
・一定の基準以上の荷主、連鎖化事業者、貨物自動車運送事業者、倉庫業者らを「特定事業者」として物流業務効率化の中長期計画の作成や定期報告などを義務付け、実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施する
・特定事業者の条件は以下の通り。
特定荷主・特定連鎖化事業者
=取扱貨物の重量9万t以上(上位3200社程度を想定)
特定倉庫事業者
=貨物保管量70万t以上(上位70社程度を想定)
特定貨物自動車運送事業者等
=保有車両台数150台以上(上位790社程度を想定)
・特定事業者に選任を義務付ける「物流統括管理者」(CLO)は、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある役員らから選任する
(藤原秀行)