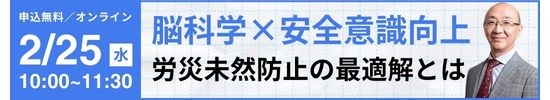東西両エリアで、競合ながら共通取引先多い環境を有効活用
7月1日に創業70周年を迎えた老舗の医療機器・医療用消耗材料メーカーのアルケアが、同業他社との共同配送を促進している。主力としている人工肛門や人工膀胱を装着している人など向けの医療用品の安定供給が「物流2024年問題」で脅かされることを懸念し、現在は2社と展開している。競合相手であるがゆえに共通の取引先が重なっていることを有効活用し、東日本と西日本の両エリアで取り組みを拡大している。
アルケアは他にも、取引先の販売店と輸送を担うトラックドライバーの双方にとって負荷を減らせる物流改革も検討している。近年物流領域で盛んに叫ばれている、「競争より協調」をまさに体現する取り組みだけに、多くの荷主企業や物流事業者にとって参考になりそうだ。
※この記事は弊社「月刊ロジスティクス・ビジネス(LOGI-BIZ)」2025年6月号に掲載したものを一部加筆・修正しました
主要製品は3カ月分を常に在庫
アルケアは1955年創業の医療機器・医療用消耗材料メーカーだ。73年に現在の株式会社へ移行した。事業は当初から手掛けてきた骨折や関節疾患をケアする「整形外科」に加え、患者の傷が早期に治るようサポートする「褥瘡(じょくそう)・創傷」、患者の皮膚を保護するとともに、看護業務の標準化・省力化につながる製品を提供する「看護」、ストーマ(人工肛門や人工膀胱)を装着している患者をサポートする「ストーマ」の計4領域を軸に展開している。
骨折などの治療の際、それまでは看護師が包帯に石こうを直接塗り込んで固めていたため非常に重労働だったギプスの作成作業の負荷を減らそうと、最初から石こうを織り込んでいるギプス包帯を開発、国産化に成功したことなどで知られる。取り扱っている製品数は2024年6月末時点で約300種類・2000アイテムに及んでおり、24年6月期の売上高は161億円だった。
メーカーとしての供給責任をより強固に果たしていくため、千葉市の自社工場は医療機器産業に特化した品質のマネジメントシステムに関する国際規格「ISO13485」を取得し、安定的に原材料を調達する体制を確立。加えて、機械と合わせて人による目視検査を徹底するなど、高品質の維持に努めている。
さらに、旧来は自社工場から製品を東京都江戸川区の日本積運拠点内に置いているアルケア東日本物流センターに保管した上で、全国の販売店などに出荷していたが、大規模災害が起これば安定供給を脅かされる可能性があるため、BCP強化の一環として、22年2月に大阪府豊中市で新たな物流センターを開設、東西2拠点体制を立ち上げた。
西日本のセンターは日本通運の物流拠点「豊中ロジスティクスセンター」内に設けている。名古屋エリアは東日本のセンター、北陸エリアは西日本のセンターがそれぞれ所管している。
並行して、近年は災害が頻発かつ激甚化していることを教訓として、東日本大震災が起こった2011年以降、人工肛門や人口膀胱を付けている患者(オストメイト)が排泄物を溜めるための専用装具、下肢の静脈の血流を促すための弾性ストッキング、皮膚を清潔に保つ保湿・清浄クリームといった主要製品は厚めに在庫を確保している。直近では24年の元日に起きた能登半島地震でも被災地に向け、弾性ストッキングなどを無償で提供した。

アルケア主力製品の一例。下肢静脈血流を促進する「弾性ストッキング」(左)と、ストーマを装着している人をサポートする「ストーマ装具」(アルケア提供)
現在は東西両センターで合わせて3カ月分の在庫を常に持つよう努めている。併せて、被災地でこうした主要製品が必要とされるケースを念頭に置き、通常の販売分に加えて自治体などから要請があればすぐに供給できるようキープしている。
アルケアで物流政策などを担当している谷口充弘流通政策部長は「災害などのいかなる状況であっても、医療現場で製品を途切れさせるわけにはいかない。西日本のセンターが稼働を開始した後はさらにBCPを強化してきた」と決意を語る。
23年に新たな変革スタート
「物流2024年問題」など物流領域が抱える課題が深刻化している状況を考慮し、安定供給維持のため、23年から新たに他の医療機器メーカーとの共同配送に踏み切った。まず、整形外科用医療機器・医療用品の開発・販売などを担っている日本シグマックスと東日本エリアで共同配送をスタートした。
さらに、アルケアの西日本物流センターと、日本シグマックスが従来の千葉県柏市に続く2カ所目の物流拠点として24年3月に大阪市内で稼働を始めた「大阪物流センター」を連携させ、25年1月に対象エリアを西日本に拡大した。
また、2社目の共同配送相手として、ストーマ装具などを手掛けるコンバテックジャパンと今年3月、東日本エリアで共同配送を始めた。
アルケアにとって日本シグマックスは整形外科領域など一部でライバル関係にあるが、準備はそれほど長期化せず、7カ月程度で共同配送の開始にこぎ着けられたという。同じ国内メーカーで互いに物流課題に対する危機意識が高かったのが背中を押した。両社と取引関係にある販売店が重なっていることが多い点も共同配送を進める上で追い風になった。
谷口部長は「商売の上では競争相手だが、お客さまがほとんど同じなので、物を届ける先の調整はそんなに大きな障害にはならなかった。ただ、両社間で受注から納品までのリードタイムや数量が異なっているところがあるため、そのすり合わせに少し時間がかかった。物流だけでなく営業などの担当者も交えて調整を重ねてきた」と振り返る。
共同配送を始める前は、両社がそれぞれ運送会社に委託し、個々の取引先に製品を届けていた。共同配送の開始後、東日本エリアはまずアルケアの千葉工場から出荷製品を東日本センターにいったん搬送し、在庫に計上した上で、千葉・柏の日本シグマックスのセンターでSBS東芝ロジスティクスが両社製品を混載して10カ所弱の取引先を回っている。

日本シグマックスとの共配の概要(プレスリリースより引用)
谷口部長は「年間を通してだいたい毎日注文があるところを共配しようということでやっている。うまくインフラを組み合わせることができた」と説明する。共同配送に踏み切ったことで、アルケアと日本シグマックスそれぞれが必要なトラックを大きく減らせるなどの成果を上げている。商品を受け取る販売店にとっても、両社の製品が一度に届くため、作業負荷を減らせるのがメリットだ。
東日本の共同配送が軌道に乗ったのを受け、西日本でもSBS東芝ロジスティクスの拠点を生かして混載、共同配送をスタートさせた。納品先は東日本と同様に順次増やしていくことを視野に入れている。
2社目のコンバテックジャパンは、アルケアが東日本センターを運営している日本通運の物流施設を有効活用しやすい環境にあったことなどが共同配送に着手する上でプラスに働いた。また、1社目と同様、アルケアとコンバテックジャパンの両社も創傷ケア、オストミーケアの一部で競合しているが、共通の取引先も多いため、共同配送のスキームを組み立てやすかった。納品先は6カ所でスタートしており、こちらも順調に行けば拡大していくことを目指す。3社目以降の展開も既に視野に入っている。

コンバテックジャパンとの共配の概要(プレスリリースより引用)
「全製品が共配対象になり得る」
「物流2024年問題」は当然ながら今後も続いていく上、人手不足が劇的に改善する見通しは全く立っていないだけに、アルケアは中長期的な観点に立ち、取引先の理解を得ながら共同配送以外の物流効率化も進めていくことを検討しており、まずは配送先の集約を念頭に置いている。現在はアルケアが販売店まで製品を届けているが、取引相手の物流センターにアルケアが納品し、その先の店舗までの配送は取引相手に担ってもらうことを考えている。
また、配送頻度についても従来の週5回から、可能であれば減らしていくことを取引先と交渉、模索していく構えだ。併せて、注文を集約し物量をまとめてもらい積載率向上につなげることなども今後の課題として、取引先と協議を本格的に進めていく見通しだ。ドライバーと販売店それぞれの負担を減らせることを志向している。
谷口部長は「当面は共同配送を含む4点を推し進めることで、サプライチェーンを安定的に運営、維持していきたい。当社の300製品、2000アイテム全体が共同配送の対象になり得る。お客さまが必要とされるものは全て安定供給のために、共同配送を検討していきたい」と力説している。
(藤原秀行)