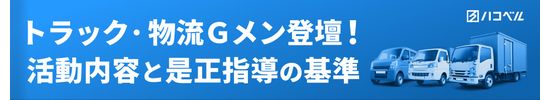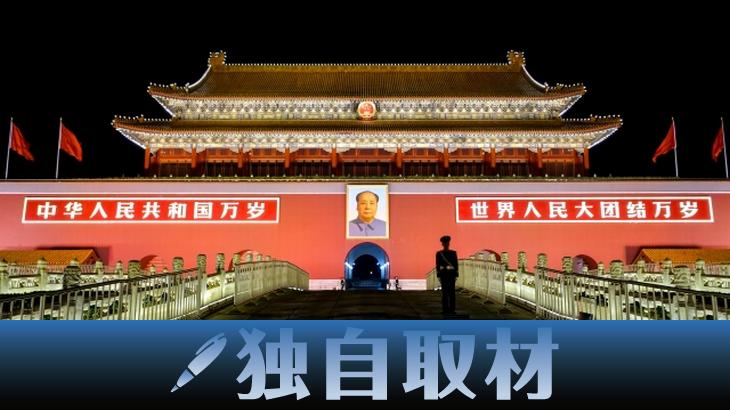第31回:中国で邦人拘束リスク回避へ今取るべき行動
シリーズの記事はコチラから!
ビニシウス氏(ペンネーム):
世界経済や金融などを専門とするジャーナリスト。最近は、経済安全保障について研究している。
駐在員の人数はできる限り減らそう
中国で2023年3月、アステラス製薬の日本人男性社員が「スパイ行為」の容疑で拘束され、今年7月に北京の地裁で懲役3年6カ月の実刑判決を受けた事件は、中国における反スパイ法の運用がもたらすリスクを強烈に印象付けた。14年の同法施行以来、日本人を含む外国人の拘束事例が相次いでおり、23年7月の改正によってさらに取り締まり対象が拡大した。
同法はそもそも内容が非常に不透明で当局の恣意的な運用が可能になっているため、今後も中国に駐在する日本人が拘束される危険が否定できない。中国に進出する日本企業はトラブルを避けるため、駐在員の人数をできる限り減らしておくことを検討すべきだ。
中国の反スパイ法の最大の問題点は、そもそも「スパイ行為」の定義が極めて曖昧なことだ。改正前は「国家機密」の窃取や提供が主な対象だったが、改正後は「国家の安全と利益に関わる文書、データ、資料、物品」の窃取や提供も含まれるようになった。しかし、「国家の安全と利益」の具体的な基準は明示されておらず、当局の裁量によって広範な行為がスパイ行為とみなされる可能性がある。
一例を挙げれば、企業が市場調査や取引先の情報収集を行う際、日本企業の常識としては通常のビジネス活動であっても、中国当局が「スパイ行為」と解釈することは十分にあり得る。実際、前述のアステラス製薬の社員のケースでも、具体的な違反行為の詳細は公開されておらず、企業側が危ない行為を事前に予測し回避することが困難だ。この不透明さは、企業活動における法的予見可能性を著しく損なう。
さらに、反スパイ法の改正により、中国当局の捜査権限が大幅に強化された。新法では、身分証明書の検査、電子機器や施設の調査、財産情報の照会、出入国禁止措置など、広範な権限が当局に付与されている。これにより、企業や個人が意図せず法に抵触する可能性が高まっている。
例えば、軍事施設や重要インフラに関連する情報を扱う企業は特に注意が必要だが、どの情報が「国家の安全」に抵触するのかは判断が難しい。2015年以降、少なくとも17人の日本人がスパイ容疑で拘束されており、うち5人が現在も解放されていない。このような事例は、企業にとって駐在員の安全確保が喫緊の課題であることを如実に示している。
現下のような状況で、日本企業が中国に駐在員を派遣し続けることは、従業員の安全と企業全体のリスク管理の観点から大きな課題となる。駐在員の拘束リスクは、個人の人権侵害だけでなく、企業の事業継続にも深刻な影響を及ぼす。
拘束された社員の解放交渉には時間とコストがかかり、企業イメージの毀損や現地でのビジネス展開の制約にもつながる。実際に、中国に進出する一部の日系企業の間では、反スパイ法の影響で駐在員の派遣を控える動きが広がっている。
加えて、反スパイ法は中国国内だけでなく、国外での行為にも適用される可能性が指摘されている。24年12月には、日本国内で尖閣諸島に関する情報を日本政府関係者に提供した日本人女性が、中国入国時に拘束される事件が発生した。このケースは、反スパイ法の「域外適用」が現実の脅威であることを示しており、駐在員だけでなく、日本国内で活動する社員や出張者もリスクにさらされる可能性がある。
こうした状況を踏まえ、外務省は中国への渡航者に対し、スパイ行為とみなされる可能性のある行動例を公表し、注意を促しているが、具体的なガイドラインが不足しているため、企業自らがリスク管理を強化する必要がある。
以上を考慮すれば、日本企業は中国での事業継続を模索する一方で、駐在員の数を最小限に抑える戦略を採用すべきである。具体的には、以下のような対策が考えられる。第一に、リモートワークや現地採用の強化により、駐在員の派遣を減らすことが有効だ。また、駐在員に対しては、反スパイ法のリスクに関する徹底した研修を実施し、情報収集や現地での行動における注意点を教育する必要がある。さらに、危機管理マニュアルを整備し、現地の法律事務所や専門家との連携を強化することも重要だ。各対策は、企業がリスクを最小化しつつ、中国市場での競争力を維持する一助となる。
最後に指摘しておきたいのが、反スパイ法の運用は中国政府の国家安全保障を優先する姿勢を反映しており、今後さらに取り締まりが強化される可能性がある点だ。日系企業は、ビジネスチャンスを追求する一方で、従業員の安全を最優先に考えるべきである。駐在員の削減は、コストや効率の観点からも合理的であり、企業としての責任を果たすための現実的な選択肢である。中国での事業環境が不透明な中、各社には慎重な判断を求めたい。
(了)