「運転席に座ってみて初めて分かることをお伝えしたい」
今年の3月に刊行された『トラックドライバーにも言わせて』(新潮新書)が、アマゾンの流通・物流(本)ランキングで第1位を獲得するなど、物流業界の内外で強い関心を集めている。本書は社会を支えるインフラとして重要な仕事のはずなのに勤務実態は厳しく、周囲からの視線も必ずしも暖かいとは言えない残念な状況を打破しようと、トラックドライバーの真実を解き明かしていることが大きな特色だ。
フリーライターとして活躍する著者の橋本愛喜氏自身、過去にドライバーを務めた経験を持つだけに、本書で語られる話は説得力を持って読み手に迫ってくる。「なぜトラックはノロノロ運転しているのか?」といった、運送事業に携わる人以外ではほとんど知られていないドライバーの常識も分かりやすく解説しているところが、他の物流業界解説本と一線を画した、圧倒的な読み応えにつながっているのだ。
ロジビズ・オンラインでは、橋本氏に本書をまとめることになったきっかけや、ドライバーという職業に対するアツい思いなどをインタビューした。3回に分けて紹介する(インタビューは今年3月に実施)。

インタビューに応じる著者の橋本氏
家業を継ぐ覚悟を示すため、ドライバーの世界に飛び込む
――ご自身もトラックドライバーの経験をお持ちです。そもそもドライバーになったきっかけは本書にも詳しく書かれていますが、なりたくてなったわけではなかったそうですね。
「その通りです。きっかけはプラスチック金型の研磨工場を経営していた父親が病気になったことです。小さいころから父親が業務の一環でトラックを運転している姿を見てきました。父親は私に工場経営の跡を継いでほしいと考えていたのですが、私自身は幼少時からいろいろと習い事をさせてもらっている中でやりたいことが増え、将来は音楽関係の仕事に就きたいと思うようになりました。本来は全く工場の経営に関心はなかったのですが、父親がくも膜下出血で倒れたため、急きょ大学卒業直前に継ぐこととなりました」
「今でこそ工場を経営されている女性の社長さんはたくさんいらっしゃいますが、当時は本当に、工場に最盛期で35人在籍していましたが、清掃担当の方を除いて全員男性でした。父親はカリスマ性で社員の皆さんを引っ張るタイプだったので、自分もそうならなければいけないという焦りはずっと持っていました。最も重要な業務の1つがトラックで金型を引き取ったり得意先へ納品したりすることだったので、工場で働くという覚悟を職人さんや得意先に示すためには自らその厳しいドライバーの世界に飛び込むことがベストだと思ったのです」
――ドライバーだった期間はどれくらいですか。
「工場で他の仕事もありましたから、月曜から土曜まで毎日トラックに乗っていたわけではないのですが、断続的に10年ほどですね。実はその間に1年間、米国のニューヨークに行ったりしていました。10年間の特に後半はトラックに乗る頻度が高かった。そのころは家業と併せてライターや日本語教師の仕事もしていました。ドライバーの仕事を毎日されている方がいるというのはすごいことだなと感じていましたね」
――その10年間を振り返って、トラックドライバーという仕事に対して率直にどう感じていますか。
「ドライバーをしている時は本当に、心の底から無駄な時間だと思っていました(笑)。自分がやりたいと思っていたことを断ち切ってドライバーの世界に飛び込んだので、まさに詩のような話ですが、仕事の合間に空を見上げてはため息を付いていました。ただ、今、こうした本も書かせていただいたことを考えると、ドライバーをしていた時に出会った1人1人の方々にすごく感謝の気持ちもありますし、本当にやっていてよかったと思います」
「当時はいやいやで仕事をやっていましたから態度も悪かった。先輩のドライバーを『おっさん』と呼んだりしていました(笑)。ご迷惑をお掛けした方々にはごめんなさいと謝りたいですし、今こうしたライターのお仕事もさせていただいている中、今度は自分が恩返しとしてブルーカラーの人たちの環境を良くしていきたいというのが率直な気持ちです」
――ドライバーの経験があったからこそ、こういう本を書き上げることができた?
「それは間違いありません」

トラックに乗っていたころの著者(新潮新書『トラックドライバーにも言わせて』より・一部加工しています)※クリックで拡大
トラックが私に厳しい時間から解放する機会を与えてくれた
――ドライバーを10年続けられた中で仕事の負荷に変化はありましたか。
「トラックに対しては最初のインパクトがすごかったので、しんどい、という環境がずっと10年続いてしまった感じですね」
――そんなにきつかったのですか?
「そうですね。ただ、私は工場の中の業務が一番つらかったので、トラックドライバーは工場の外に出られる唯一の手段だったんです。1人になって頭をちょっと整理したい、考えたいと思った時にトラックを運転していると、真っ直ぐな高速道路と、時々路面の段差でがたんと振動するリズムが脳をシャッフルしてくれるので、すごく思考が最適化するような感じになりました。工場の仕事は本当に苦しかった。あのドライバーとしての時間がなかったら恐らく私自身はつぶれてしまっていたでしょう。無駄だと思っていましたが、今から振り返れば、トラックが私に厳しい時間から解放する機会を提供してくれた。そういう意味でも私はトラックに助けられたと思いますね」
――ライターや日本語教師の仕事と並行してドライバーをされていたのですか?
「1日の睡眠時間が2時間ほどしか取れず、本当に大変な生活でした。居眠り運転にならないよう、コーヒーを飲むなどいろいろな工夫をしていました。まさに分刻みで動いていたんです」
――どうしてそんな過酷な状況で働かれたのですか。
「工場にいれば名前ではなく『(社長の)娘さん』と呼ばれ、どうしても職人さんたちとの間に壁がありましたし、両親は私を経営者として見るようになったので家にいてもずっと仕事の話で、落ち着いて過ごせる居場所がなかった。日本語教室には多い時で20カ国語くらい言語が異なる学生がいたので、共通語が日本語でした。そこではどんな下手なギャグを言ってもめちゃくちゃ受けたんですよ(笑)。とても楽しかった。私がずっと憧れてきたニューヨークのような多様性があり、居心地の良さに工場が忙しくてもやめるにやめられなくなりました。教室には大きな日本地図があり、私はトラックで関東から大阪まで乗りますと説明したら、学生から『オーマイゴッド!』『マンマ・ミーア!』のような世界中の感嘆詞が飛び交うような、ものすごく面白い世界でした」
「ライターの仕事に関しては、小さいころから文章を書くことが好きで、学校の作文コンテストで優勝したこともありました。ニューヨークに1年間滞在していた時、日本のテレビ局の米国総局の記者やアナウンサー、カメラマンの方々と仕事で触れる機会があり、ジャーナリズムに触発されました。私は絶対に記事を書きたい!と思うようになったんです」
――本書以外にも、さまざまな媒体でトラックドライバーの仕事の実態などを精力的に執筆されていますね。ニューヨークの体験を通して記事を書きたいと思われてから、実際にドライバーの話を書くようになった経緯は?
「日本に戻って初めてのライターの仕事が東日本大震災の取材でした。被災地に行き、いろんな人たちの話を聞く中で、ああやはり、私は現場をきちんと取材し、人をベースにした記事を書きたい、と強く思うようになりました。そうした背景が、私が直接、接してきた人も含めてトラックドライバーさんの第一線で働いている方々のお話をまとめられたらいいな、という思いにつながっているんじゃないかと思います。こんなに面白いネタは他にないだろうとずっと心の中に感じていましたから」
――本書でも、どのエピソードを入れようか、みたいな葛藤があったのでは?
「ありました! 泣く泣く割愛した話もいっぱいありましたよ。ただ、版元の新潮社の皆さんがえりすぐりのネタをピックアップしてくださったので、すごく素敵な本になったのはうれしいですね」

執筆の動機などを語る橋本氏
歩行者や自転車が知らない“死角の多さ”
――本書はいろいろと見どころがありますが、特に「態度が悪いのには理由がある」と題した第2章は、「なぜトラックがノロノロと走っているのか?」や「どうしてドライバーはハンドルに足を上げて寝そべっているのか?」といったような、トラックに乗っている人にとっては常識でも、乗っていない人にとっては全く新しい世界を紹介した、非常に斬新な内容です。そうした話がここまで詳細にかつ分かりやすい形で紹介されているのはこれまでなかなか見られなかっただけに、まさに本書の肝の部分だと感じます。
「そう言っていただけると本当にうれしいですね。本書で実は一番地味だけど、一番思いを込めて書いたのがお話のあった2章と3章(「トラックドライバーの人権問題」)なんです。2章は本当に、トラックに乗ってみないと分からない話が満載、という内容になっています。TBSラジオの番組に出演した際もパーソナリティーの久米宏さんが、乗ってみないと分からないから皆さん1回乗ってみるべきだということをおっしゃってくださったんです。まさにその通りだと思います。私自身、今度教習所へごあいさつに伺おうかなと思っているくらいです(笑)。普通車の教習を受けている人に、トラックの運転席に座り、こんなところに死角があるんだとご自身の目で気付いてもらうことだけでもぜひ体験してほしいですね」
「第2章でも触れましたが、一部のマナーが悪いトラックドライバーがイコール全てのトラックのマナー、みたいな印象になってしまっているのが腑に落ちないんです。プロのくせに、みたいなことを言う人もいますが、私自身はトラッカーでなくてもハンドルを握っている人はみんな運転のプロであるべきだ、というのが信念なので、トラックだからプロ、というふうに安易に片づけてしまうのも何かちょっと違うかなと思います。一般の乗用車のドライバーさんたちが、ほらまたトラックドライバーが荒い運転をしている、みたいな反応をしてしまうのを、本書で何とか払拭するお手伝いをできたらいいなと強く思っています」

ハンドルに足を上げるのにも理由がある(新潮新書『トラックドライバーにも言わせて』より)
――私も普通車ですが運転しますので、トラックの運転席からの死角の話はある程度イメージができます。自転車がトラックにとって最も見えにくい「左後方から真横」をすり抜けていくという話は、確かによく考えてみればぞっとすることですよね。
「特にやはり、自転車は左側を走っていきますから、乗用車にとっても危ない存在です。そこの部分については結構、共感してくれる読者さんが多かったですね。運転席からの死角となるとやはり、トラックは普通の乗用車以上に死角が多いですから、そこをどうにかして伝えたい、伝えたいと結構頑張ったつもりです」
――自身のトラックドライバーとしてのヒヤッとした経験もかなり反映されているように感じました。
「もちろんです。いっぱいありましたね。死角の問題もそうですし、自転車だけではなくて例えば歩行者の皆さんも、急いでいるからだとは思いますが、交差点の角の、道路に面した頂点のところに立って、信号が青に変わったらスタートダッシュしようと待ち構えて待っている人がいますし、自転車のタイヤの先が道路側にはみ出てしまっている人も見かけますよね。そうした行為がどれほど危ないか。歩行者の皆さんは本当にトラックへ乗ってみないと分からないんだろうなと頻繁に感じていましたよ」
――トラックに乗っていれば、機能的にもそうならざるを得ない部分もありますよね。
「そうなんです。先ほどの話と関連しますが、私のツイッターアカウントのフォロワーさんは8割方がトラックドライバーさんなんですが、彼らが2章を読んで『橋本さん、当たり前だよ、こんなこと。何でこんなのわざわざ文字にしているの?』みたいな反応をメッセージで送ってくることがとても多いんです。それに対して、3章はちょっと熱いこと、『ドライバーは底辺職なのか?』みたいな問題意識に基づいていろいろと考えを書いているので、2章と3章のギャップがすごいという話も聞きます。読者の皆さんからは結構、賛否それぞれの声が寄せられています。2章はドライバーさんにとってみればごくごく普通の内容なんですが、そこを一番、一般のドライバーさんには読んでほしいところです」
(中編に続く)
インタビュー中編:「ドライバーへの転落人生? 何だその表現は!」
後編:「女性の活躍促進は大歓迎、でも『トラガール』は間違い!」

『トラックドライバーにも言わせて』(新潮新書、税別760円)
(藤原秀行)
新潮社のサイトはコチラから

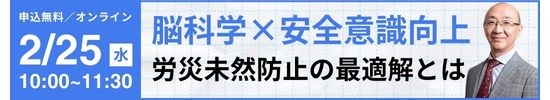









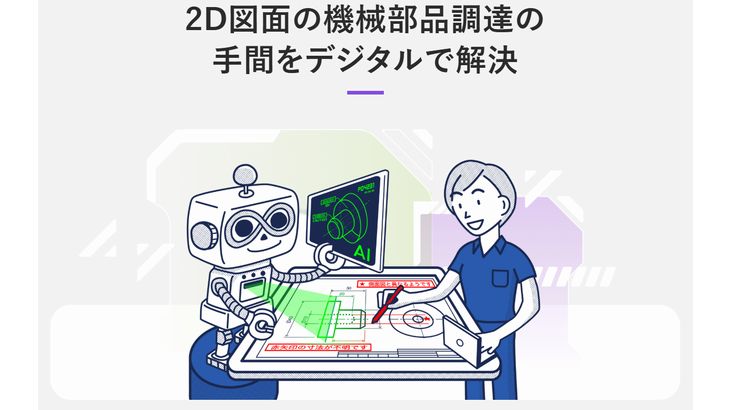





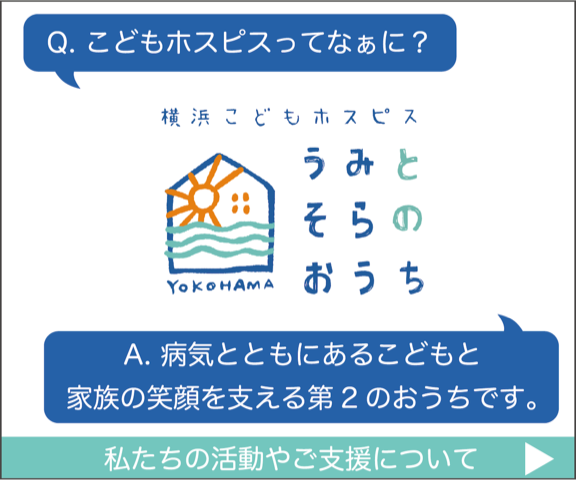
![EVトラック展示などスマート物流EXPO開催!1/21~23@東京ビッグサイト[PR]](https://online.logi-biz.com/wp-content/uploads/2026/01/ffc5f385608e470e62598597bdbb161c.jpg)


![[PR]事前登録ラストチャンス!10/24(金)開催「中部ミライノ物流EXCO 2025」](https://online.logi-biz.com/wp-content/uploads/2025/10/EXCO_banner_1002-730x410.jpg)
![[PR]「中部ミライノ物流EXCO 2025」事前来場登録受付開始!](https://online.logi-biz.com/wp-content/uploads/2025/09/bnr-chubu-2.jpg)
![[PR]「中部ミライノ物流EXCO 2025」10/24(金)開催!大手メーカーらに学ぶ物流課題解決の一手](https://online.logi-biz.com/wp-content/uploads/2025/07/39c24e22a0790f93df5ab770fdadd2cf.jpg)