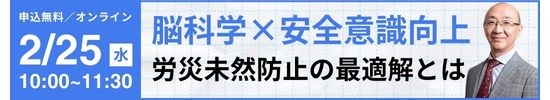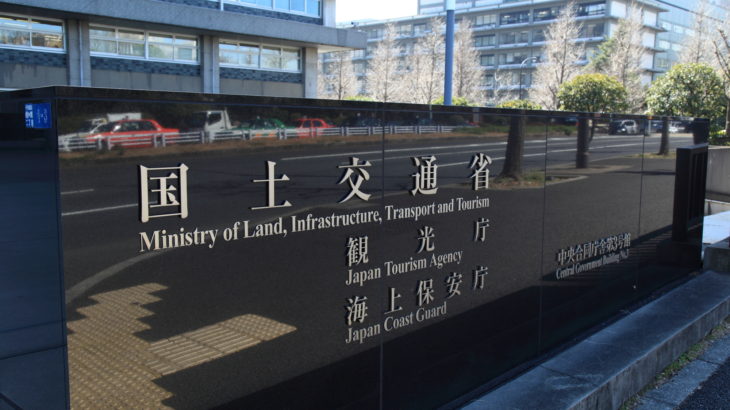物流事業者と荷主双方の取り組みを後押しへ
国土交通省は11月22日、東京・霞が関で、「共同物流等の促進に向けた研究会」(座長・矢野裕児流通経済大教授)の初会合を開いた。
人手不足に伴い物流業界で共同物流の重要性が高まる中、物流事業者に加えて荷主企業も積極的に取り組める環境を整備するための施策を議論。2019年以降の政策に反映させていくことを目指す。
20年の東京五輪に伴う交通混雑回避のための共同配送などの取り組み推進も念頭に置いている。

研究会の初会合
研究会は有識者と国土交通、経済産業両省の幹部らで構成。事務局は論点として、
①共同物流等を進める上での課題について
・荷主や物流事業者が共同物流等を進める上で、コスト、商慣行等の観点から障壁となっていることはあるか
・共同物流等に成功している例におけるキーポイントは何か
・共同物流等に至らなかった例においては何が原因だったのか
②課題を克服するために必要な取り組みについて
・①の課題を克服するために必要なことは何か
・そのために国に期待される役割は何か
――を提示。
今後の検討の進め方として、共同物流などを
▽荷主間の共同物流(コンテナラウンドユース、中継輸送など)
▽物流事業者間の共同物流(幹線での共同輸送など)
▽その他の取り組み(モーダルシフト、貨客混載など)
に分類し、それぞれ事業者からヒアリングして事例を集め、議論のたたき台としていくことなどを打ち出した。
初会合の冒頭、メンバーに名を連ねる国交省の松本年弘物流審議官は「共同のモーダルシフトなどで着実に成果が表れている一方、まだまだ促進の余地はあると考えている。さまざまな事例を研究して課題を抽出するとともに、今後官民が進むべき方向性の検討を行いたい。活発なご議論をお願いしたい」とあいさつ。
矢野座長は「商品は競争するが物流は協調、という意識は前から少しずつあったが、非常に高まってきた。コストだけでなくサービスを維持するために共同化へ取り組まざるを得ない状況だ。物流の共同化は着荷主が重要だが、その意識が相当変わってきている。これまでにもさんざん議論されてきたテーマだが局面が変わっており、非常に重要な課題。施策も含めていろいろ議論いただきたい」と共同物流促進に強い意欲を示した。
(藤原秀行)

会合の冒頭に発言する矢野座長