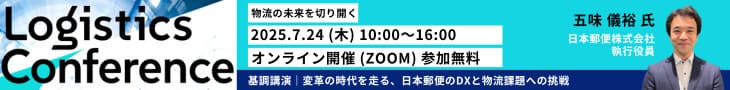日野自動車・小木曽社長独占インタビュー(前編)
日野自動車の小木曽聡社長はこのほど、ロジビズ・オンラインの単独インタビューに応じた。
小木曽社長は、運輸・物流領域の地球温暖化対策が強く求められる中、トラックの脱炭素化に向け、EV(電気自動車)やFCV(燃料電池車)など多様な技術を組み合わせるとともに、既存車両の性能を高めて実現を目指す方針を強調。
トヨタ自動車と日野自動車、いすゞ自動車、スズキ、ダイハツ工業の5社が共同出資している新会社「Commercial Japan Partnership Technologies」(CJPT)でトラックの電動化や自動運転技術開発を加速させるのと同時に、商用車メーカー間の競争関係も維持し、トラック運行の効率化などを後押ししていきたいとの考えを示した。
インタビュー内容を前後編の2回に分けて紹介する。

インタビューに応じる小木曽社長
「個社だけでやっていてはスピードが足りなくなる」
――まさに商用車業界は脱炭素化に向けた電動化など大変革の時代に入っていると思います。まず、そうした時期に経営トップとなられたことへの率直な感想をお聞かせください。
「当社は1942年の創業から来年で80周年を迎えます。トラックやバスなどで人流、物流を支えるという大きな先人の志を受け継いできた歴史ある会社の社長となるのはやはり重責ですが、そうした大役に任命いただけたことは本当に光栄でもあります」
「仰る通り、カーボンニュートラルや物流業界のトラックドライバー不足への対応など、今はやるべきことがたくさんあります。必死に取り組んでいきたい。1人ではできることにも限界がありますから、会長に就任した下(義生氏)ときっちり二人三脚でやっていきたいと思います。ツートップの2人がばらばらになると、会社の他の人たちがたまったものではないでしょうから、2人でしっかりと向いているベクトルを合わせていきます」
――小木曽社長はトヨタ自動車時代、世界初の量産型HV(ハイブリッド車)となった初代プリウス(1997年発売)の開発に携わり、コンパクトHVの初代アクア(2011年発売)はチーフエンジニアとして開発責任者も務められました。18年には社内カンパニーの中で商用車を扱う「CVカンパニー」のプレジデントに就任しました。これまでの経験は御社でどのように生かしていきますか。
「下会長は人流と物流の両方で経験も知見も豊富です。一方、私自身はご指摘の通り、CVカンパニープレジデントの際に商用車も見ていましたが、トヨタは商用車といってもハイエースとかプロボックスといった(ワンボックスなどの)車種が大半です。そういう意味ではあまり物流という感じではなかったので、まだまだ物流全体に関する経験が足りないと自覚しています」
「ただ、18年の終わりごろから当時の下社長とトヨタグループの商用車分野のところは、これからの時代は一緒につながって取り組んだ方がいいよねという話をずっとしていたんです。日野の現状に関しても随時情報を共有してきました。私自身、エンジニアとしての経験を生かしながら、下会長との二人三脚を含めて、日野の社員、販売店の方々、その他さまざまなパートナーと連携していきたいと考えています」
――下会長との役割分担は?
「明確には分けていません。とにかく二人三脚でやっていきましょうということですね。当然、会長には大きな枠組みや事業の方向性を一緒に入って考えてもらい、自分はやや執行側の立ち位置で、計数的なものなどを見ていくのかなと思います。当社全体に関わるところは下会長と2人で一緒に決めていきますが、会長としてもう少し広い立場で経営を見てもらう。物流が重要という価値観、ベクトルは2人とも全く一致していますので、その点はご安心ください」
――21年第1四半期(4~6月)の決算は、新型コロナウイルスの感染拡大が直撃した前年同期に比べればかなり良くなっているように見えます。どう評価されますか。
「当社はもともと、18年に『チャレンジ2025』という形で、25年に目指すべき姿を公表しています。その中で新車販売台数を17年度の18万台から25年度には30万台へ伸ばすという目標を立てました。競争力強化をきっちりやってお客様に喜んでいただきながら収益もしっかり出して行くという計画なのですが、コロナ禍で経営環境が非常に厳しくなる中、昨年の10月にはチャレンジ2025達成の前提として、22年までに新車販売が年間15万台レベルであっても安定的にしっかり稼げる体制を確立する方針を新たに打ち出しました。構造改革を進めるため、競争力強化や新規ビジネス展開、原価低減といった50にわたる様々なプロジェクトに取り組んできた結果が、第1四半期に一部現れてきたのだと思います」
「今年はまだ、通期の業績見通しを変えておらず、新車販売台数は15万台と設定しています。今申し上げた通り、しっかり収益を出せるようにする台数の前提と同じ水準です。その中で何とか、4~6月期の営業利益率(4・7%)が出せたということは、取り組んできたことがある程度実を結べているのではないかなと感じます」
「昨年のように資金の流出防止でとにかく費用を抑えるというだけではなく、デジタル化やCASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)にまつわるようなところには少し、昨年に比べてリソースを投じるようにした上で、第1四半期の経営成績のような形になっています。しかし、まだまだチャレンジ2025で掲げた『利益率10%』という目標の半分程度にしか達していません。そこは引き続き、課題です」
――商用車のCASE対応や電動化を進めていく上で経営基盤はかなり強化できてきましたか。
「十分強化したというところまではまだ行っていません。強化し始めた、という表現が正確でしょう。下会長がずっと繰り返し申し上げている通り、これからのCASEや電動化は、何でも昔のエンジン車のように自前で進めるということは難しい。個社だけでやっていてはスピードが足りなくなってしまいます。状況に応じてアライアンスパートナーと組み、コンポーネントを共通化できるところは共通化しながら技術開発を進めていく必要があるでしょう」
「ただ、EV(電気自動車)ではモーターや電池といった主要なコンポーネントを社外から調達するため内製比率は下がりますが、単に調達した何かを組み立てるだけの受け身の姿勢では日野のオリジナリティがなくなってしまう。お客様のことを知り抜いた上でどんな車を造りたいのかビジョンを明確に立て、必要なシステムやユニットの企画をわれわれが主体的に取り組む。そうした企画の部分はもっともっと強くしていかなければいけません」

「このままでは物流が成り立たないとの危機感があった」
――4月に御社とトヨタ、いすゞ自動車の3社が共同出資し、トラックの電動化などに取り組む新会社「Commercial Japan Partnership Technologies」(コマーシャル・ジャパン・パートナーシップ・テクノロジーズ、CJPT)を立ち上げました。7月にはさらにスズキとダイハツ工業も合流を発表しました。商用車で長年のライバルと組むのはかなり思い切った決断との印象をうけました。それくらいしないと生き残っていけないという危機感があったのでしょうか。
「確かに、そのくらいまでやらないと完成車メーカーとして生き残っていけないという危機感が背景にあります。それに加えて、私たちの主要な顧客の物流業界がトラックドライバー不足や脱炭素化といった課題に直面し、このままでは物流も成り立っていかないかもしれないという危機感がありました。5社が入った枠組みであれば、発表記者会見の場でも説明がありましたが、大型トラックから小型トラック、ラストワンマイルを担う軽トラック、軽バンみたいなところまで一気通貫で情報がつながることにより、より物流の改善に対して貢献できるのではないかと感じたのです」
「さりとて、お客様の下でメーカー同士が競争し、切磋琢磨することは大切にしていかないといけません。CJPTに5社が参加したからといって、全員で同じ商品を、販売店も一緒にして売りに行くわけでは全くない。うちといすゞさんのライバル関係を含めて競争はしっかりある上で、これからのCASEや物流で一緒にやった方が世のため、人のためになる、もしくは業務をまとめることによって効率化できるものがあれば効率化しましょうということで、組み合わせを考えて判断しているところがあります」
「CJPTは『共同企画会社』とご説明している通り、サプライヤーではなく、トラックの電動化などを効率的に実現できる共通の規格を作り上げていくことがメーンの仕事です。メーカーをまたいで車両の走行実績や積載している荷物の種類といった情報や技術を共有、活用できるようになれば大変使いやすくなる。その技術を生かした製品化のためにどこへ部品類を発注するかなどの部分は各社の判断になります。例えばモーターを発注する先は国内だけでもさまざまなところがありますから、まず共通の規格を策定するということです。電池などに関しても一緒です」
――いすゞと組むことに抵抗や躊躇はなかった?
「もともといすゞさんとは合弁でバス製造のジェイ・バスを設置したくらいですから、CASEの基盤の部分で協調すべきところがあれば協調した方がいいと感じていましたから、下会長も含めて、全然違和感も、躊躇することもありませんでした。CASEの技術もたくさん持っているトヨタが接着剤となり、各社の先進技術をつなげていくという今回のスキームは大変ポジティブな話だと思います。先ほどお話したように、最終的な製品、サービスの部分でライバルであることは、お客様のためにもわれわれのためにも必要なことです。ただ、CASEを中心とした基盤のところで協調するのはウェルカムなことだと思います」

7月の会見後、撮影に応じる(左から)トヨタ自動車・豊田章男社長、ダイハツ工業・奥平総一郎社長、スズキ・鈴木俊宏社長、CJPT・中嶋裕樹社長(YouTube会見画面よりキャプチャー)
――CJPTの中での規格を統一するタイムスケジュールのイメージはありますか。コネクテッドのプラットフォーム推進についてはいかがでしょうか。
「大変申し訳ないのですが、私はCJPTの正式メンバーではありませんので、詳しいことは多くはお話できません。ただ、企画会社ですので、その都度、いろんなことを5社で相談しながら計画を作成し、スケジュールを立てて具体化していく流れになると思います。コネクテッドに関しても、お客様から見れば今お使いのトラックに装着してほしいとのご要望はあるかと思いますが、どのような段取りで対応していくかについても、今後5社で協議していくことになるでしょう」
――トラックのカーボンニュートラルのアプローチとしてはEVやFCVなど、多様な技術が存在しています。どの技術に収斂していくことになるのかは、トラックドライバーにとって大きな関心事だと思いますが、どのように展望していますか。
「率直に申し上げて、どれか1つの技術に収斂していくというのはなかなか難しいでしょう。私がトヨタに在籍していた時も、初代プリウスが世に出た97年ごろから既に環境車はハイブリッドかEVか、FCVか、それともディーゼルなのかといったように様々な議論がありました。国のエネルギー事情もありますし、お客様によって車両の使い方も全く異なってきます。車両によって特徴も違います。日本でもふんだんにカーボンフリーの電力だけがあって、完璧な電池充電設備があればいいが、そうでないとすると、やはり効率の良いハイブリッドは必要ですし、幹線輸送を担う大型トラックやトレーラーは燃料電池の高いエネルギー密度が有効でしょう。カーボンフリーの水素やバイオディーゼルも使えるでしょうし、ラストワンマイルの近距離を走る小型トラックはバッテリーEVが有力ではないかと感じています」
「日本自動車工業会の豊田章男会長(トヨタ社長)も内燃機関車の必要性を指摘されています。当社も温室効果ガス排出削減などの方向性を示した『日野環境チャレンジ2050』の中で、車両自体でCO2排出抑制を追求するに当たり、EVやFCV、PHV(プラグインハイブリッド車)など“次世代のクルマ”づくりにチャレンジするのと併せて、ディーゼルエンジンシステムなど既存技術の高度化も積極的に進める方針を示しています。何か1つの技術に収斂するとは思っていません」
「これからは走行時のCO2排出削減だけではなく、製造時などを含めたライフサイクルトータルでCO2排出を削減していく方により規制も変わっていくでしょう。走っているときだけ電動車だからよし、と言える時代では恐らくなくなってくる。CJPTとしてどういうスタンスになるかはまだ分かりませんが、少なくとも日野自動車としては引き続き、ライフサイクルトータルを重視して考えていきます」

「日野環境チャレンジ2050」のうち、走行時のCO2排出削減の方策(日野自動車ウェブサイトより引用)
(本文・藤原秀行、写真・中島祐)