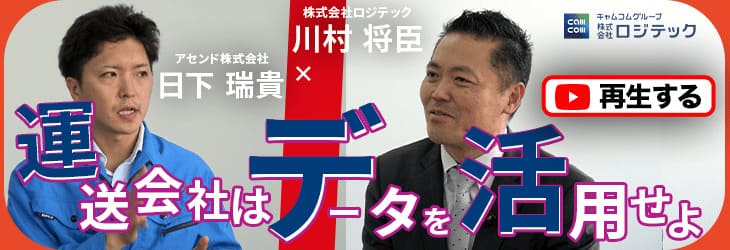ロボット活用やビッグデータ生かした新サービス開発など推進、「協創」にも重心
三井倉庫ホールディングスの古賀博文社長は12月8日、東京都内の本社で記者会見した。
古賀社長は、2017年度(18年3月期)から5年間を対象とする現行の中期経営計画の進捗状況を振り返り、ゴールとなる21年度(22年3月期)の業績目標を前倒しで達成したことなどを踏まえ「われわれの進んできた道は間違いではなかったと実感している」と語った。
同時に「ようやくスタートラインに立つことができた。(22年度=23年3月期からの)次期中計がわれわれにとって非常に重要な意味を持つ。持続可能なサプライチェーン構築に貢献することが求められている」と指摘。次期中計は業務のDX推進によるサービスの多様化やレベル向上、ESGへの対応が重要な柱になるとの見解を示し、ロボット活用といった庫内作業の自動化・機械化やビッグデータを生かした新サービスの開発などを進める意向を強調した。さらに、他企業と連携する「協創」にも重心を置くと語った。

会見する古賀社長
現行中計「グループに一体感生まれてきた」と評価
古賀社長は現行中計について、M&Aした企業ののれん価値見直しによる評価損計上などで悪化した業績を立て直すため、投資対象の絞り込みやコスト削減で財務体質改善を図るとともに、ヘルスケア領域専用の物流拠点新設など持続的成長に資する投資については積極的に取り組み、ソニーグループとの新たな業務提携によるSCM強化への貢献や海外子会社の譲渡など経営体制の変革も進めてきたと総括。
営業利益が最終年度の21年度には過去最高の205億円を見込むなど、利益水準や利益率が大幅に改善した上に、事業会社から改善提案が起こるなど社員の意識と行動に変化が出てきたと説明。「グループとしての一体感も生まれてきた」と満足感を示した。
一方で、新型コロナウイルスの感染拡大や人手不足深刻化などを考慮し、環境の変化へ積極的に対処して自ら変革することが必要と力説。その一環として、次期中計をにらみ、顧客の物流領域のCO2排出量可視化と削減のための業務設計などサプライチェーンの持続可能性を高めるためのサービス「三井倉庫SustainaLink(サステナリンク)」といった施策を展開していることに言及した。
具体的な成果の例として、大手ビール会社の輸送効率化のため、複数の工場付近に専用の出荷拠点(門前倉庫)を構え、いったん原材料を集積した上で、使いたい時に使いたい量だけ各工場へ運ぶ方式に変更。各トラックの積載率を高め、CO2排出量を年間1000トン、トラックの台数を4000台以上減らせたことなどを紹介した。
加えて、今年11月に公表したグループのDX戦略を引用し、顧客の輸配送や入出荷といったビッグデータを収集、分析できる「SCMデジタルプラットフォーム」の構築などを進め、自社業務をデジタル技術で最適化する「守りのDX」と、事業内容を変革して顧客へのサービスレベルを高める「攻めのDX」を並行して展開していくことにあらためて強い意欲を見せた。
DX戦略の中で明記している、庫内作業を自動化・省力化する「デジタルウェアハウス」対応に関しては「通販向けはロボティクスを中心に展開していくのが必然的であり、推進していく」と解説。一方で原材料などの保管はまだまだ自動化が難しい部分があるとの見解を示し、取り扱う荷物によってきめ細かく対応することが重要とアピールした。また、「在庫の可視化は全ての倉庫で進めていく」と明言した。
DX戦略が24年度までに約100億円を投資する方向性を打ち出している点については「内訳はまだ明確に決めていない」と語った上で、クラウド活用のための費用が現時点で全体の3~4割程度を占めるとの見通しを示した。
また、海外事業に関連し、タイでグループ企業のオフィスを一本化し、営業活動なども各社間で連携して進める取り組みを進めていると紹介。国内でもグループの事業会社が担っている機能ごとに取り組みを集約し、業務を効率化・迅速化していきたいとの考えを語った。
ESG対応の中で、サプライチェーン上で児童への労働強制など人権侵害のリスクを把握・防止することを求める動きが世界的に強まっている点については「問題意識を持っており、特に海外事業に関しては対応を指示している」と述べた。
(藤原秀行)