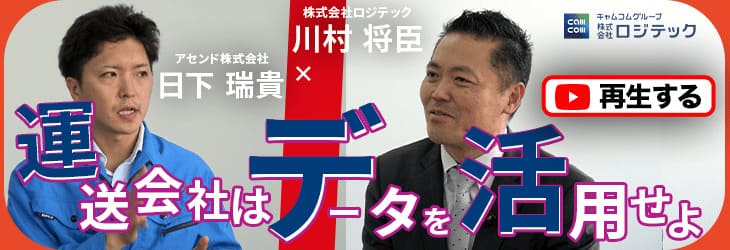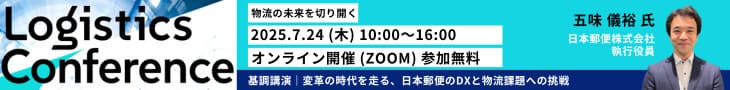特別調査委が報告書で認定、社側調査でエンジン5機種に新たな性能未達確認も
日野自動車は8月2日、日本市場向けのトラックとバス用ディーゼルエンジンの排出ガスや燃費に関する認証申請に不正行為があった問題で、社内に設けた第三者による特別調査委員会(委員長・榊原一夫元大阪高等検察庁検事長)の調査報告書を公表した。
報告書は、国土交通省から2016年、道路運送車両法に基づき認証取得時の排出ガス・燃費試験に関する不適切事案がないかどうか報告を求められた際、日野自動車が不適切事案はない旨の、虚偽の説明をしていたと認定。
車両用ディーゼルエンジンについては、排出ガス関連は平成15年(2003年)排出ガス規制以降の幅広い機種で主に劣化耐久試験に関する不正行為が、燃費関連は重量車燃費基準が導入され税制優遇制度の対象となった平成17年(2005年)排出ガス規制以降、主に大型エンジンで燃費測定に関する不正行為がそれぞれあったことが分かったと指摘した。
産業用ディーゼルエンジンについても、排出ガスの面で、平成23年(2011年)以降の幅広い機種で、やはり主に劣化耐久試験で不正行為が判明したと説明している。不正行為は2000年代から続けられており、悪質さと深刻さが浮き彫りになった格好だ。
なお、日野自動車が特別委の調査と並行して技術検証を進めたところ、3月時点で公表した内容に加えて、車両用ディーゼルエンジン2機種、産業用ディーゼルエンジンも3機種で新たに性能が規制で定めている水準に達していないことが分かったという。
日野自動車は「経営が現場に寄り添えず、適正なプロセスよりもスケジュールや数値目標が優先されやすい環境と仕組みになってしまったことが背景にあったと考えている。内向きで保守的な組織風土も相まって、一人ひとりが当事者意識と一体感を持って仕事に取り組むことができない状態に陥ってしまっていた。会社組織としての業務マネジメントの意識・仕組みも十分ではなく、経営の責任は重大であると認識している」との見解を表明。
その上で、今後の対応について「全社横断での品質マネジメント体制構築、組織・風土といった企業体質の改善、管理監督機能の強化をはじめとする健全なガバナンス体制確立について検討し、推進に向けた執行体制も含め3カ月をめどに取りまとめる」と説明している。
(藤原秀行)