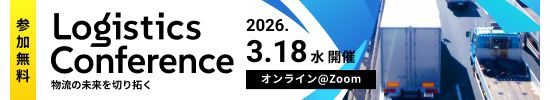第24回:「日鉄のUSスチール買収NG」が映す米国の心情
シリーズの記事はコチラから!
ビニシウス氏(ペンネーム):
世界経済や金融などを専門とするジャーナリスト。最近は、経済安全保障について研究している
超大国のプライドが経済合理性の判断を不可能に
バイデン米大統領は退任直前の1月3日、日本製鉄による米USスチールの買収に対して中止命令を出した。以前からバイデン氏は買収に難色を示していたが、中止命令に関する会見で、この買収は米国の象徴的鉄鋼メーカーを外国の支配下に置くもので、米国の国家安全保障やサプライチェーンにリスクをもたらすと指摘、米国の象徴的な鉄鋼メーカーを保護することは米国大統領としての責務だと強調した。
米大統領が同盟国・日本の企業に対して買収の中止命令を出したのは初めて。これで日本製鉄による買収は暗礁に乗り上げたが、同社は手続きが不正として、命令が出た後、即座にバイデン氏らを相手取って訴訟に踏み切っており、徹底抗戦の構えを見せている。
今日、多くの日本企業関係者がバイデン氏の決断に不信感を抱いていることだろう。近年、日本企業による米国企業の買収案件は増加傾向にあったが、今回の件がその勢いに冷や水を浴びせる可能性すらある。しかし、我々はこの結果を冷静に踏まえ、バイデン氏が買収阻止の決断に至った背景を探る必要があろう。

日本製鉄のUSスチール買収は混とんとしている
今回の件でまず押さえておかなければいけないのは、日本と米国の間で論点が大きく異なっているということだろう。これまでの日本製鉄や日本企業の反応、メディアの報道などを見ていると、日本側の認識は、経済合理性の観点から日本製鉄によるUSスチール買収は理に適ったものであり、米国にも大きな経済的利益をもたらすことが確実なのに、同盟国・日本の企業による買収を安全保障上の理由で阻止することは理解できないというものだ。確かに、この認識に至るのは自然に考えれば当然だろう。
しかし、米国側は経済合理性の観点でこの問題を議論しているのではなく、表面的には企業活動の問題であるものの、政治紛争の一環なのだ。無論、今回の買収によって米国に利益がもたらされることは十分に認識しているだろうが、そうした経済的利益を超越する米国のプライドこそが大きな問題になっているのだ。
今日の米国は、1990年代や21世紀初頭の米国ではない。当時の米国は、ブッシュ(息子)政権が自由や民主主義など米国流の価値観を世界に普及させると明言しているように、超大国として世界を主導し、外国の紛争を解決させる上でも一役を買うという存在だった。しかし、今日の米国にそのような姿は見えないばかりか、USスチール買収問題に象徴されるように、中国企業による買収をことごとく阻止し、外国による自国への介入や吸収に過剰に抵抗する一種のアレルギー症状を発しているように映る。
米国の政治・経済的な影響力が相対的に低下しているのは、様々なデータから明らかである。米国自身もそのことは無意識のうちに理解しているからこそ、非介入主義、自国第一主義を打ち出している。しかし、同時に、世界最強国である米国としての自尊心やプライドといったものは依然として根強く持っている。そこに米国は強いジレンマを感じており、同盟国企業による経済合理的な買収だったとしても、冷静に対応することを難しくしているのだ。
極論となるが、日本製鉄による買収企業がUSスチールほど同国を代表する企業でなければ、バイデン政権の対応も変わっていた可能性も考えられる。対象が中堅企業だった場合は、社会的にもそれほど大きな話題とならず、買収が円滑に行われる可能性が高いが、象徴的な大企業ほど国家とイコールで考えられ、米国の国家としてのプライドを掛けた問題として定義されやすいとも言えよう。そして、何より、我々はこういった姿勢がトランプ政権になってより先鋭化する可能性が大きいことを念頭に入れておく必要があろう。
(了)