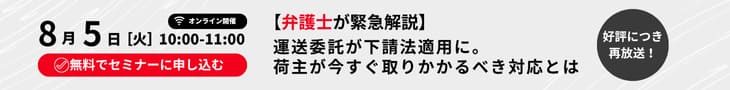災害時に緊急物資届ける「ドローン物流」実現を強く期待
日本の観測史上初のマグニチュード9・0を記録し、2万人を超える死者・行方不明者(震災関連死含む)を出した東日本大震災の発生から3月11日で10年を迎えた。北海道から東北、関東に至る広域を襲った激しい揺れや津波は物流にも深刻なダメージを与え、旧来の常識を転換する契機になった。その後の10年でも未曾有の災害が続発したことで大きく様変わりした物流の歩みの一端を振り返る。

震災発生から約2週間後の岩手県宮古市の様子。大量のがれきで埋まり、JR貨物のコンテナが流されてきている(以下、震災当時の写真はいずれも弊社「月刊ロジスティクス・ビジネス(LOGI-BIZ)」2011年5月号掲載のものを引用・刈屋大輔氏提供)
地元自治体との防災協定締結が広がる
「トラックバースを多数完備」「広い庫内」「屋上に太陽光発電パネルを搭載し節電や売電が可能」…。震災が起きた2011年3月より数年前に関東エリアで完成したある大型物流施設の当時の紹介資料を見ると、免震構造で地震に強いことをうたっているものの、それ以外には防災の機能について特段触れてはいない。オペレーションの効率改善や環境負荷低減の話が目立つ内容だ。
震災発生から約1カ月後の国土交通省の集計を見ると、破損や水没、荷崩れなどの被害が出た営業倉庫は関東で約720件、東北で約80件に上った。深刻な状況は物流施設開発にも大きく影響。現在では賃貸物流施設の着工や竣工を伝えるデベロッパー各社のプレスリリースには「非常用電源を完備」「衛星電話導入」「備蓄を十分確保」「過去の水害や津波の程度を考慮し地盤をかさ上げ」「災害時にも使える自家給油設備」など、災害対応を意識した機能を説明する言葉があふれている。
あるデベロッパーの幹部は「テナント候補の企業が物流施設を選ぶ際、防災機能は優先順位がかなり上位になっている。この10年で本当にニーズが様変わりした」と明かす。

行方不明者の捜索を続ける自衛隊員

壊滅的な打撃を受けた堤防に近いエリア

橋に流されてきた漁船が突き刺さっている
デベロッパーは防災面の取り組みを拡充して入居企業のニーズに応え、施設の付加価値を高めようとさまざまな工夫を凝らしている。例えば、プロロジスが国内で開発に着手したり、開発を終えたりした施設としては節目の100棟目に当たる「プロロジスパーク猪名川1・2」(兵庫県猪名川町)は大型施設を2棟建設。1棟目は21年、2棟目は22年に完成をそれぞれ見込んでいる。大きな特色となっているのが、ふんだんに盛り込んだ防災対策だ。
周辺住民が使える約4000平方メートルの公園と約8000平方メートルの防災広場を整備、このうち防災広場はドクターヘリ発着や災害時の防災活動・避難拠点として使うことを想定している。他にも緊急地震速報や72時間程度稼働可能な非常用電源などを備える予定だ。
同社の山田御酒社長は「当社から防災対策を押し付けるのではなく、あくまで入居されるカスタマーや地域住民の皆様にとって何が良いのかを考えた上で対策を進めることが基本」と強調する。

「プロロジスパーク猪名川1・2」の完成イメージ。左側が「猪名川1」(プロロジス提供)
最近は地震や台風の際、大型物流施設を避難場所として地域住民に開放できるよう、デベロッパーが地元自治体と協定を結ぶケースも増えている。日本GLPは昨年12月、佐川急便と災害時協力協定を締結。災害が起こった時に両社が地元自治体と連携しながら物流施設を避難所として開放するとともに、佐川が迅速に救援物資を物流施設に送り届けることを打ち出した。
既に第1弾として、日本GLPが大型物流施設計8棟を順次開発している千葉県流山市が3者による防災体制に加わった。日本GLPの帖佐義之社長は「他の自治体にも参加を働き掛けていくことで、より物流施設が社会に貢献できるようになる」と意気込みを語る。
大和ハウス工業も今年2月に新たな物流施設「DPL岩手北上Ⅲ」の工事を始める岩手県北上市と、地震などが起きた際、施設の共有スペースを支援物資の一部保管や集積場所として提供することをうたった協定を結んだ。他の地域でも協定を複数結んできており、同社の浦川竜哉取締役常務執行役員は「地域住民が避難できる場所として使っていただくのに加え、物資集積という物流の面でもお役に立てる意義は大きい」と指摘する。
デベロッパーの中には物流施設を生かした新たな防災対策として、災害時に救援物資の保管や仕分けをすぐに引き受けられるようにするため、平時から100%稼働にせずバッファーとしてある程度空きスペースを残しておくことを検討するなど、さらにレベルを高めようとする動きも見られる。この10年でまさに物流施設は地域住民を被害から守るとともに、自らも稼働を止めず物流を持続させ、社会生活が混乱しないようにするという2つの側面で「防災の砦」に進化した。不測の事態に備えたデベロッパー各社の準備はこれからも決して止まることはない、と期待したい。

協定を締結した佐川急便の本村正秀社長(左)と日本GLPの帖佐社長(日本GLP提供)
21年は「ドローン災害活躍元年」になるか
東日本大震災からの10年間、甚大な被害をもたらす大規模災害が続いてきた中で、注目度が高まっているのがドローン(無人飛行機)だ。
震災当時にはまだ広く一般的に知られた存在とは言えなかったドローンだが、被災状況を上空から素早く把握できる点に加え、医薬品など緊急で求められる物資を、人手を介さず届けられることへの期待値が高まっている。
ドローン開発を手掛けるプロドローン(名古屋市)の河野雅一社長は、震災で津波に巻き込まれた人たちの存在を知り「ドローンで空を飛ぶことができれば多くの人が助かったのではないか」との思いを抱いたという。そのことが、人が立ったまま乗り込んで遠くへ飛ばし、安全な避難場所まで連れていけるドローン「SUKUU」(スクウ)」開発の背中を押した。
直接物流と関係があるわけではないが、ドローンを災害現場で有効に使いたいとの思いは共通している。プロドローンはSUKUUの実用化に向け、バッテリーの稼働時間改良などに取り組んでいる。
政府は22年度にドローンが人口の多い都市部上空を自律飛行する「レベル4」を実現するとの目標を掲げ、安全規制の整備などを加速させている。レベル4が解禁となれば、ドローンが宅配の荷物を運ぶ「ドローン物流」が広がることが見込まれる。

19年の国際展示会「JapanDrone」に出展されたSUKUUのプロトタイプ
災害時の救援物資輸送はドローン物流普及の前段として早期の実現が望まれており、大手企業やスタートアップ企業が積極的に取り組んでいる。ドローンの機体開発などを手掛ける自律制御システム研究所(ACSL)とA.L.I.Technologiesは昨年11月、安全なドローン運搬システムの構築で連携を開始したことを発表。両社の技術を組み合わせ、災害時の緊急物資輸送など、物流以外でも物を運ぶ用途に投入できる機体や運航管理システムの確立を目指している。
テラドローンは昨年11月、日本航空(JAL)や宇宙航空研究開発機構(JAXA)と連携し、兵庫県養父市でドローンによる物資輸送の公開実験を行った。滑走路を使わず少ないエネルギーで長距離飛行が可能な小型固定翼ドローンを投入。災害応援支援物資を運ぶとともに、JAXAの協力を得て災害時にドローンと有人飛行機が双方の位置情報を共有、衝突を回避する運用手順が有効かどうかも確認した。
「空飛ぶクルマ」の開発などを手掛けるSkyDriveは昨年12月、愛知県豊田市で開かれた大規模地震時の物流に関する訓練に参加し、同社が販売している産業用ドローン「カーゴドローン」を使った孤立集落への物資運搬訓練を実施。500ミリリットル入りペットボトルの飲料水24本を搭載、会場の運動広場内の2地点間を無事飛行した。今後は愛知県や豊田市と連携し、災害時に孤立集落の居住者が生活必要物資を居住区でスムーズに受け取れるよう、法令基準を満たした安全なドローンの開発を本格化させる方針だ。

「カーゴドローン」による実験参加の様子(SkyDrive提供)
産業用ドローンの普及促進に取り組んでいる日本UAS産業振興協議会(JUIDA)でも、19年に陸上自衛隊東部方面隊と大規模な災害発生時のドローンを活用した救助活動の応援に関する協定を締結するなど、ドローンの災害関連用途に早くから着目してきた。
JUIDAの鈴木真二理事長(東京大名誉教授、東京大未来ビジョン研究センター特任教授)は21年のドローン普及の目標として「ドローン災害活躍元年」を掲げ、災害時の援助物資輸送や上空からの被災状況把握、被災者救出などの領域でドローンが広く使われるようJUIDAとしても後押ししていく方針を示している。
鈴木理事長は「普段はどこがドローンを保有しておくのかや、いざ使う場合にはどのような手続きが必要か、といったルールを平時に定めておけば、緊急時にすぐドローンを投入できる」と指摘、国など関係者間で議論が早急に本格化することに強い期待を示した。待ったなしの災害対策でドローンが活躍し、被害を最小限に食い止め早期復旧につなげていくことが21年中に実現することを強く願いたい。それはドローン物流の確実な実現にも道を切り開いていくのは間違いないのだから。
(藤原秀行)