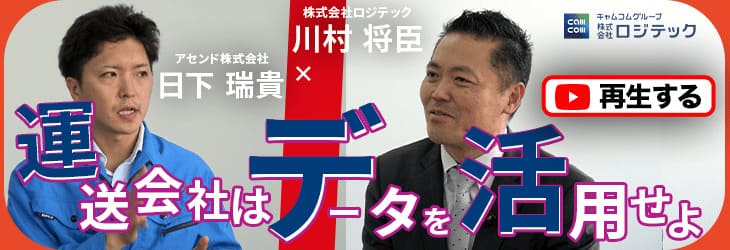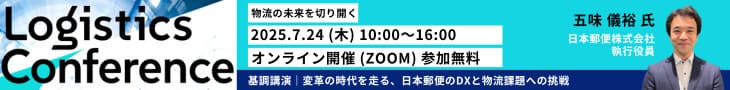全6回の特集記事掲載、担当幹部や共同物流の取り組み紹介
経済産業省は6月4日、同省が所管する経済産業分野の様々なトピックを取り上げ、最新の動向などを国民に紹介する政策ウェブマガジン「METI Journal ONLINE」で、「物流クライシス 突破の処方箋」と題した全6回にわたる政策特集の記事掲載を開始した。
ウェブマガジンは特集の狙いについて「企業や団体の優良な取り組み事例を取り上げながら、その課題と解決策を探っていく。これらの事例は、日本の未来の物流を占う試金石となる」と説明。物流業界が今後進むべき方向性を示唆することを目指している。荷主業界に強い影響力を持つ経産省がどのような処方箋を示すのか、注目したいところだ。

政策ウェブマガジンのサイト
6月4日に掲載の第1回は物流の課題と取り組みに関して、経産省の畠山陽二郎商務・サービス審議官にインタビュー。発言内容から「物流需要と輸送能力(供給)のバランスが崩れて危機的な状況にある」との問題指揮を表明、トラックドライバーの労働環境改善と効率的な配送網構築を並行して進めることを訴えた。
畠山審議官は10年後、20年後の物流の未来像を問われ「通信の世界がインターネットによって飛躍的に変わったように、物流もネットワーク革命が起きる可能性がある」と展望。そうした状況で日本企業が成長を果たしていくために「物流事業者だけでなく、荷主事業者や消費者も含めて、物流にかかわるステークホルダーみんながサステナブル(持続可能性)な物流システムをつくる意識を共有化することが大切」と締めくくった。
第2回は6月9日に公開。事務機器メーカーなどの業界団体「JBMIA(ビジネス機械・情報システム産業協会)」で会員企業間の共同配送を準備している動脈物流委員会の酒井祐史委員長と松田和也副委員長が登場した。
両氏への取材を基に、共同配送の背景として、物流を従来の「競争」から新たに「共創」領域と位置付け、持続可能な社会の実現に貢献するとともに「運べないリスク」という社会的な課題を解決していく狙いがあると説明。同委でまずは複合機のラストワンマイル配送の部分を対象に進める計画を立てており、各社でばらばらな納品基準の標準化に取り組んでいるという。他の業界との連携も視野に入れている。
第3回はロボティクス分野の先進事例として、Rapyuta Robotics(ラピュタロボティクス)や楽天グループ、パナソニックを取り上げる予定という。第4回以降にも期待が持てる内容だ。
(藤原秀行)