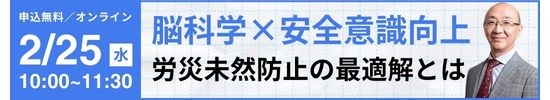「長距離のトラック輸送」回避、今後は輸入コンテナのラウンドユースなど検討
イケア・ジャパンは、物流のサステナビリティ(持続可能性)向上に注力している。配送車両にEV(電気自動車)を順次投入。商品の配送に「置き配」を採用したり、大型商品を購入者が好きなタイミングで引き取ることができる専用ポイント「商品受け取りセンター」を各地に設置したりとラストワンマイル配送の負荷を軽減。
さらに、愛知県弥富市の基幹倉庫から全国の店舗へ商品を届ける際の輸送は鉄道貨物や内航海運を積極的に利用。トラックドライバーの長時間労働規制強化に伴う物流現場の混乱が懸念されている「2024年問題」がクローズアップされる前から、なるべくトラックを長く走らせないことを優先させており、今後も継続していく構えだ。他社との共同物流も視野に入れている。
商品受け取りセンターは全国24カ所に拡大
イケア・ジャパンは現在、自社配送で6台、大型商品配送で1台それぞれEVを活用している。大型商品配送用のEVトラックはSGホールディングスグループのSGムービングがイケア・ジャパンの配送業務へ優先的に投入している。
イケアグループは日本を含む世界の各エリアで、2025年までにラストワンマイルのゼロエミッション(温室効果ガス排出実質ゼロ)配送100%を実現することを目標に掲げている。イケア・ジャパンCustomer Fulfilmentの岡本有加Fulfilment Sourcing Managerは「決して楽な目標ではないが、順次台数を広げていきながら達成できるよう努めていく」と強調する。

商品配送に投入している三菱自動車製のEV
置き配は既に全国で展開しており、現状では配達全体の約4割で使われているという。岡本氏は置き配に関して「デフォルトにはなっておらず、お客様の受け取りサービスの選択肢の1つとしてお選びいただく設定」と解説。置き配による再配達抑制で温室効果ガスをどの程度減らせているか、効果を計算しているという。
商品受け取りセンターは2019年3月の札幌からスタートし、現在は青森や福島、静岡、茨城、広島、山口、熊本など24カ所に拡大。300kgを重量の上限と設定しており、大型商品などを受け取る際の料金は通常配送より割安に設定。利用が広がっている。
岡本氏は「お客様にとっても安く商品を受け取ることができるし、われわれとしても配送コストを抑えることにつながる。双方にとってプラス」と効果を強調する。

輸送時に使ったストレッチフィルムの100%リサイクルをスタートした
2009年ごろから「脱長距離トラック輸送」
イケア・ジャパンは2001年、名古屋港から10数kmと近接した愛知県弥富市に倉庫を開設した。現在の延床面積は約5万5000㎡。中国などのサプライヤーから輸入した商品をいったん集めた後、首都圏など各地の大型店舗へ発送している。弥富の倉庫は売れ筋の商品を中心に取り扱っており、それ以外の商品は店舗があるエリアの近隣港へ直接輸送している。
イケア・ジャパングループで倉庫の運営を手掛けているイケア・ディストリビューションサービスSupply Chain Operationsの川合健一Supply Operations Developerは「トラックの長距離輸送は非常にドライバーさんの負担が大きく、今の時代には合わない。できるだけインターモーダル(異なったモードの輸送組み合わせ)を考えながら効率的に商品を運ぶことができる仕組みを考えている」と説明する。2009年ごろからそうした考えの下、鉄道貨物や内航海運の利用に取り組んできた。
基本的な輸送ルートは関東向けの場合、名古屋港からRORO船を使って川崎港まで搬送した上で、各店舗まで陸送している。名古屋から直接トラックで運ぶよりもドライバーの拘束時間を短くできる上、温室効果ガスの排出も抑えられるとみている。
福岡に大型店舗がある九州向けの場合はJR貨物とRORO船の2本立てで輸送。仙台に大型店舗を構えている東北向けは名古屋港から北海道の苫小牧港向けフェリーを使い、途中の仙台で降ろして店舗へ陸送している。海上輸送は天候に左右されるため、悪天候が見込まれる場合はなるべく前倒しで、一部のコースをトラック輸送で代替するなどの対応を講じるよう努め、混乱を回避している。
2024年には北関東で初となる大型店舗を群馬県前橋市にオープンさせる予定。新店舗への商品供給も名古屋港から内航船で川崎港まで運んだ上で陸送するという基本パターンを踏襲する方向だ。ただ、川崎港~前橋市は距離があるため、川合氏は「1回当たりのトラック輸送が長距離にならないよう、何らかの工夫が必要」と指摘している。

前橋市の新店舗イメージ。地上2階建て、店舗面積は約1万㎡の予定(イケア・ジャパン提供)
今は物流の持続可能性を高める新たな施策として、輸入コンテナのラウンドユースを検討中だ。名古屋港などで商品を降ろした後の空コンテナを別の輸出企業などに再利用してもらうことを想定している。川合氏は「ラウンドユースは試験的にやったことはあるが、いろいろと考えなければいけないポイントがあるので、他の企業と協力していきたい。トラックドライバー不足にも対応できればいいと思っている」と語る。
イケア・ジャパンは昨年11月、千葉県船橋市の大型店舗「IKEA Tokyo-Bay」に付随している倉庫を、国内のイケア店舗で初めてオートメーション化すると発表。ノルウェーのAutostore(オートストア)製自動倉庫型ピッキングシステムを採用し、関東圏の4店舗で担っていた小物配送のピックアップ業務をIKEA Tokyo-Bayに集約し、より効率良く商品を発送できるようオペレーションを修正している。
オートストアの採用で作業スタッフは倉庫内を歩き回る必要がなくなり、作業負荷を大きく減らすことができた。イケア・ジャパンBusiness Developmentの平山絵梨Country Sustainability Managerは「当社で働こうと思っていただける現場にしていきたい。ロジスティクスの現場は男性に加えて女性も活躍できる場にして、多様性のある組織にする必要がある」と強調している。

取材に応じる(左から)岡本、平山、川合の各氏
(藤原秀行)