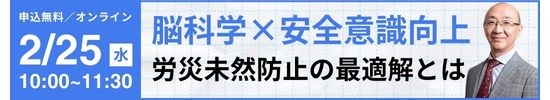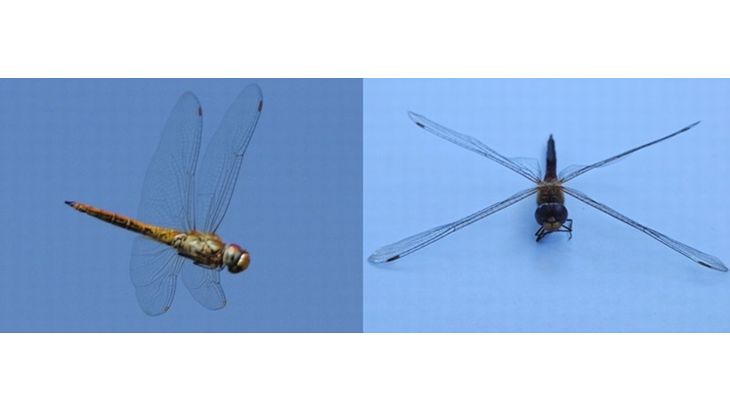第21回:緊張高まる台湾情勢、頼総統の主張や行動をチャンスと捉える中国
シリーズの記事はコチラから!
ビニシウス氏(ペンネーム):
世界経済や金融などを専門とするジャーナリスト。最近は、経済安全保障について研究している
威圧的な大規模演習、就任5カ月で既に2回
中台関係で緊張が続く中、中国軍で台湾を管轄する東部戦区は10月14日、台湾本土を取り囲むような形で大規模な軍事演習を行った。今回の軍事演習には陸海空軍、ロケット軍に加え、中国海警局も参加し、海上封鎖や実戦を想定した訓練などを実施、中国海軍の空母も台湾の東側海域での演習に参加した。
今回の軍事演習には戦闘機やドローン、ヘリコプターなど125機、艦船34隻が参加し、1日の規模としてはこれまでで最大となった。なぜ、中国はこの時期に最大規模の軍事演習に踏み切ったのか。その背景には、中国への対抗姿勢を強める台湾の頼清徳政権を牽制する狙いがある。
頼総統は10月、台湾では建国記念日と位置付けられる双十節の式典で演説し、北京政府には台湾を代表するような権利は一切なく、台湾は国家主権を堅持し、一方的な併合などを許さないと主張。今年5月の就任演説で打ち出した、台湾と中国は隷属しないとのメッセージを再び繰り返した。
さらに、中国は10月1日で国として75歳の誕生日を迎えたばかりだが、台湾はその数日後に113歳の誕生日を迎えるなどとも発言した。頼総統が語った一連の刺激的な内容を、中国側が独立に向けた意思を強く持っていると受け止めたであろうことは想像に難くない。
頼総統が5月に実施した就任演説の直後も、中国は今回のように台湾本土を包囲する形の軍事演習を2日間にわたって実施した。それ以前にも、2022年8月に当時のペロシ米下院議長が台湾を訪問した際、やはり同じく大規模な軍事演習を展開したが、その際は大陸側から弾道ミサイルも発射され、一部が日本の排他的経済水域に落下、大きな騒ぎとなったことはいまだ記憶に新しい。
台湾を包囲するような軍事演習はこれで計3回となったが、中国は台湾側の主張や行動の1つ1つに細かく反発、抵抗しているわけではい。その裏側ではチャンスと捉えている可能性が高い。すなわち、中国はいずれの軍事演習も台湾側の発言を挑発と捉えて突発的に対抗措置を取っているのではなく、むしろその機会を待望し、軍事演習を積み重ねることでいつでも実戦に対応できるよう尽力している。海上封鎖に関しても同様だろう。
やはり中国に対して毅然とした対応を取ってきた印象が強い蔡英文前政権だが、任期だった2016~24年の8年間で台湾を包囲するような中国側の軍事演習はわずか1回だった。頼政権下では極めて対照的に、就任から5カ月で既に2回繰り広げている。このことからも、中国は今後も頼総統の主張や行動を注視し、必要に応じて今回と同様か、それ以上の実戦に近い軍事的威嚇を示してくる可能性が高い。
今後、頼総統が対中発言のトーンを落としてくる可能性もあるが、これまでの主張は蔡前総統よりも、さらに中国側を意識して踏み込んだ内容の発言をしているようにも感じられ、一種の負のスパイラルに陥っていると言えよう。頼総統の発言がより中国を刺激するものになれば、中国も比例して厳しい対抗措置を取ってくることになる。
冷静に考えれば、今日、台湾有事が極めて差し迫った状況にあるというわけではない。しかし、日本企業としては上述のように中国が台湾統一をにらみ、むしろ好機と捉えて対抗措置を取っているという認識をしっかりと持つ必要がある。このような負のスパイラルが長期化すれば、戦闘機同士の衝突など偶発的な事件が生じ、軍事的緊張が一気に高まる恐れも念頭に置いておかないといけないだろう。
(了)