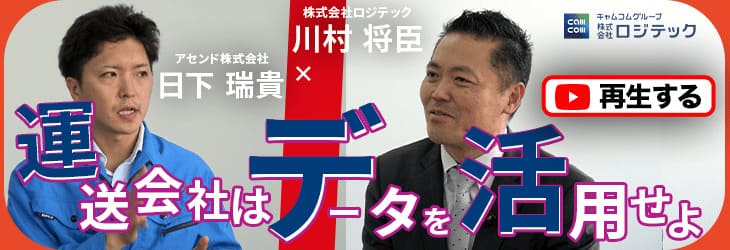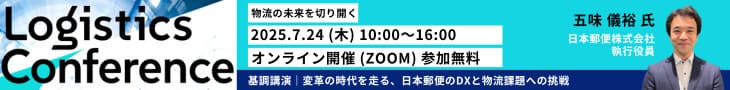4月発足の専任部署・佐伯部長、優れた技術持つスタートアップとの連携探究
リース大手の三菱HCキャピタルは今年4月、新たな部署「ロボティクス事業開発部」を立ち上げた。各部署の関連業務を集約し、ロボットを現場で使おうとする企業に最適な技術を最適な形で導入できるよう提案することに注力する構えだ。製造業や物流業など幅広い現場で自動化・省人化のニーズが高まっているのに対応する。
同部の佐伯孝志部長は今後10年程度を見据えながら「主要事業の1つに育てていきたい」と成長の可能性に懸けている。事業集積の規模100億円が1つの中長期的な目標になりそうだ。

取材に応じる佐伯部長
「ロボットサービスプロバイダー」が目標
三菱HCキャピタルは現行の中期経営計画の中で「ビジネスモデルの進化・積層化」を掲げ、中長期的な利益成長の柱の1つにロボティクスを位置付けている。長年のリース事業でさまざまな企業や団体と関係を構築できている点などを生かし、既に人手不足が顕在化している食品や施設管理、物流といった領域でロボット活用の実証実験へ積極的に参加するなど、施策を拡大している。
これまでにも、2022年に食品工場向けに総菜や弁当の盛り付けロボットを開発したコネクテッドロボティクスと資本・業務提携を締結したり、23年からビックカメラや山善とともに経済産業省が採択した物流施設でのロボット活用実証事業に参画したりしてきた。さらに全社的に取り組みを強化していくため、新組織発足に踏み切った。
佐伯部長は「ロボットの技術開発が発展し、多様な製品が世に出ているため、企業はなかなかご自身の用途に適した製品をご自分で選ぶことが難しくなってきている。当社は自らロボットを製造するわけではないが、さまざまなメーカーやシステムインテグレーター(Sier)の方々と組み、お客様のニーズを正しくつかんで最適なロボットを導入できるよう後押しする。まさに『ロボットサービスプロバイダー』として、ソリューションという形で提案していく」と狙いを説明する。
サービスの提供形態としては、ロボットを単体として提供するよりもむしろ、包括的にサービスとして展開することを重視しており、顧客にとってオーバースペックのロボットを薦め、結果として収益や現場のオペレーションに負荷をかけてしまう事態は回避することを最優先とする。佐伯部長は「システムインテグレーションやメンテナンスも含め、パッケージ化してソリューションを提供していきたい。そのためには、さまざまなプレーヤーといかにパートナリングをしっかりやっていくかが肝」と指摘する。
重視する分野は、既に手掛けている食品や施設管理、物流(倉庫)に小売、建設、インフラ・点検、製造、飲食を加えた計8つの領域を念頭に置いている。こうした領域で今後、ロボットの需要は飛躍的に伸びると期待しており、まさに多様な自動化・省人化のニーズに、的確に応えていく構えを見せる。
8領域はそれぞれ、求められる技術が異なってくるだけに、一律に対応するのではなく、各領域の現状をきめ細かに把握しながら、必要な技術を取りそろえていくことを優先させるという。
佐伯部長らが意欲を見せるのが、優れた技術を備えたスタートアップとの連携だ。先に言及したコネクテッドロボティクスや人工筋肉を応用したソフトロボティクスの実用化を図っているソラリスのほか、今年6月には小売店舗向けロボットのMUSE、9月には次世代の自動搬送システム開発を進めているLexxPlus(レックスプラス)とそれぞれ資本提携することを発表した。lexxPussとは自動化機器利用のハードルを下げるため、従量課金で自動搬送システムを利用できるサブスクリプションサービスの提供で協力することを念頭に置いている。
佐伯部長は他にも協力を検討しているスタートアップやメーカーなどが複数あることを明らかにした上で「先進的な技術の情報をより積極的に収集していきたい」と強調。今後も資本・業務提携を探究していくことに意欲を見せる。倉庫内のオペレーション改善は難度が高いが、「課題を克服すべき領域で意義は大きい。ぜひトライしていきたい」と意気込んでいる。

LexxPlussの次世代自動搬送システム(同社提供)
(藤原秀行)