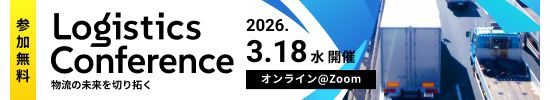日本GLP・帖佐義之社長独占インタビュー(前編)
日本GLPの帖佐義之社長はこのほど、ロジビズ・オンラインの単独インタビューに応じた。帖佐社長は千葉県流山市で稼働中の先進的な物流施設3棟に加え、さらに5棟を開発する大型プロジェクトに関連し、他社に先駆けて物流施設を建設、現在は集積地として高く評価されている埼玉県三郷市のように流山を“物流適地”へ生まれ変わらせていきたいと強い意欲を示した。
また、2018年に設立した子会社のモノフルで今後、物流業界向けに人材のマッチングシステムやロボットレンタルなどの独自サービスを拡充し、物流施設事業の付加価値を高めていく考えを明らかにした。インタビュー内容を2回に分けて紹介する。

インタビューに応じる帖佐社長
関連記事:日本GLP、千葉・流山でさらに物流施設5棟を開発へ
インタビューの後編記事:日本法人設立10年「立ち止まる瞬間がないほど激動だった」
より高いレベルで地域との共生を実現
―御社は4月、千葉県流山市で新たに大型の先進的物流施設を5棟建設するプロジェクトを発表しました。既に稼働している3棟と合わせると、延べ床面積は約90万平方メートルになる見通しです。物流施設開発としてはまさに国内最大級ですが、顧客企業の反応はいかがですか。
「すごくいいですね。(3棟開発の)『フェーズ1』は着工前にリースアップが決まったケースもありましたし、計約30万平方メートル全てが完成から間もなく満床となりました。プロジェクトとしては大成功だと思いますし、フェーズ1で吸収しきれなかったニーズもまだまだたくさんあるます。(5棟開発の)『フェーズ2』発表でまた引き合いが一層増していますし、これだけのスケール感があってこそできるような物流施設のコンセプトに関しても共感していただける方がすごく多いという手応えはあります」
―大型開発を流山で進めてきて気づいた点はありますか。
「物流施設のカフェテリアやコンビニエンスストアなどを館内で働く方々だけでなく、地域住民の方々にも開放することで親しみを持っていただき、働いてみたいと希望される方もいらっしゃるなど地域と施設と働く人々がうまく連鎖してオペレーションがなされています。そうした点は発見というよりもプロジェクトの狙いでしたが、うまく当てはまったなという印象を受けています」
―これだけの大型開発をする上では周辺地域とうまく付き合っていくのがより重要になってきているということでしょうか。
「当社では以前から施設を開発する際にはそうした点には非常に気を配ってきたつもりですが、やはり単体の開発と大規模な開発ではできることの幅や深さが変わってきます。より高いレベルで地域との共生が実現できているのかなと思います」
「流山市が掲げている『母になるなら、流山市。』という理念は、地域を重視する当社の開発コンセプトと非常に親和性があると思いましたので、かなり早い段階から行政とは打ち合わせを重ねて、より市民の方々にもメリットのあるような開発にしたいと思っていました。それに対し行政も非常に協力してくださっていますし、実際にふたをあけてみて多くの方々が物流施設で働かれていたり、施設が地域の中に溶け込みカフェテリアが憩いの場になったりしているのを目の当たりにされて、ますます協力体制が強くなったのではないでしょうか」
―フェーズ2はかなり早くから視野に入れていたのでは?
「フェーズ1の開発計画を発表した時にも申し上げましたが、『流山は次の三郷』だと考えていました。埼玉県三郷市も10数年前に初めて当社がBTS型施設を造ってからどんどん物流施設の開発が進んで発展し、今では物流の“プライム立地”として評価されています。流山は三郷に近接していますし都心へのアクセスが良く、かつての三郷と似ていて市街化調整区域が多くまだ物流施設は開発が進んでいません。確実に物流適地になるポテンシャルを秘めていましたから、流山を次の三郷にしていくという思いを持ってフェーズ1に取り組んでいましたし、次の事業機会をずっとうかがっていました」
―さらに次のフェーズへ進む可能性はありますか。
「既に十分大きなプロジェクトにはなっていますが、もしまだ物流施設の適地が出る可能性があるというのであれば、当然次の開発を考えていく場所になるでしょう」

流山で計8棟が完成したイメージ(日本GLP提供)
関係企業全てがメリット享受できるエコシステムを構築
―用地取得競争が激しい中、これだけ大規模な用地を押さえられた要因はどこにあると自己評価しますか。
「流山に関しては大きな面開発にしてスケールメリットを打ち出していきたいとの思いがありましたので、そういう強い気持ちで土地の交渉に臨んでいたのが奏功したのではないでしょうか」
―フェーズ2は企業と人、地域社会と共生していく物流施設との理念「Co-Solution」をキーワードに掲げ、庫内作業スタッフや輸配送のマッチングシステム、倉庫スペースのシェアリング、自動化・省人化へのコンサルティングなど多様なサービスや設備を提供する計画を示されています。先進的な施策がかなり含まれていますが、実現できますか。
「フェーズ2の中身はフェーズ1のさらに次のステージ版というところですが、フェーズ2で新たな取り組みにチャレンジすることでフェーズ1の魅力もさらに高まるのではないかと期待しています。既に実用化しているサービスもありますし、全てを実現するのは大変ですができないものでは全然ありません」
―フェーズ2のサービスや設備を展開していく中では、御社が18年に設立した子会社で新技術開発を担うモノフルが大きな位置を占めそうです。同社は現在どのような事業を手掛けていますか。
「4月にローンチしたトラックの入出庫管理『トラック簿』は非常に好評で、今どんどん契約件数を伸ばしています。IT企業ではなく、物流に熟知した会社が取り組んでいるITサービスということで、運送事業者の方々にとってかゆいところに手が届く内容になっていると自負しています」
―今後の展開は?
「既にローンチしているサービスをより広げていくということもありますし、併せて人材マッチングサービスとかロボットレンタルとか、かなりたくさん、いろんなサービスを今作っているところです。WMS(倉庫管理システム)のプラットフォームを提供するということもありますし、物流施設を利用する方たちが求める物流サービスを完全網羅し、関係する企業全てがメリットを享受できるエコシステムを構築するところまで事業は広げていきたいですね」
―物流施設のテナント企業のニーズはかなり変化してきているのでは?
「期待は非常に強いと感じています。当社も床をお貸しするだけではなくて、床プラスいろんな付加価値を提供することで、より幅広い需要を取り込めると思いますし、当社にとってはプラスの収益の源泉になりますから、お客さまと非常に利害は一致しているのではないでしょうか」

物流施設の付加価値向上について話す帖佐社長
“面開発”であらためて感じた物流施設の可能性
―同じ大規模開発という意味では、神奈川県の相模原市でも先進的物流施設を5棟、総延べ床面積約65万5400平方メートルという巨大プロジェクトを進行中です。進捗はいかがですか。
「今解体工事が行われていて、ちょうど今から1年後くらいに第1期となる一番大きな建物の着工を目指しています。流山と似ていて、それだけの大きなスケールだからこそ実現できるような、物流に付随するサービスを展開する予定です。おかげさまで流山と同様、非常にお客さまからの反応は良いですね」
―相模原のプロジェクトではかねて「物流と生産の一体化」をポイントに挙げています。独創的なアイデアはありますか。
「やはりサプライチェーンのかなり幅の広いところを需要層として取り込んでいきたいと考えています。一方、流山は開発エリアが全体的に細長い形なのに対し、相模原は全体的に丸い感じとなっているため、例えば中心部に大きな共用施設を整備しやすい。地域共生の面でも、館内で働かれる人たちの利便性を高めるという意味でも、相模原ではそうした取り組みに注力していこうと計画しています。大きな意味でのコンセプトでは流山と共通する部分が非常に多いと思いますが、同時に流山とは違った相模原の個性みたいなものもしっかりと出していきたい。今年の秋ごろには概要をお話できると思います」
―相模原でも街づくりの視点を取り入れますか。
「そうですね。やはり敷地が29万平方メートル超という大きな面開発ですし、キャタピラーさんが半世紀以上そこで工場を展開されてきた歴史もありますので、そうした貴重な財産を引き継ぎ、相模原市への貢献というところも考えて、今開発のコンセプトを練っているところです。市も非常に協力してくださっていて、期待の大きさを感じています」
―このような大規模な街づくり的開発は今後も可能性はありますか。
「やはり流山で実感しているのは、先ほどもお話しましたが、これほどのスケール感があって初めて実現できることがあるという点です。物流施設が持つ可能性のようなものをあらためて強く感じられました。面開発に関しても、また事業機会に恵まれることがあればぜひ取り組んでいきたいですね」

相模原の物流施設完成イメージ(日本GLP提供)
(本文・藤原秀行、写真・中島祐)