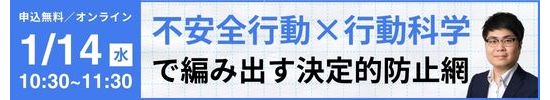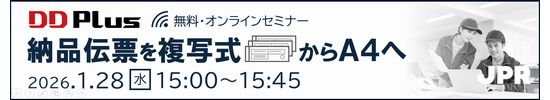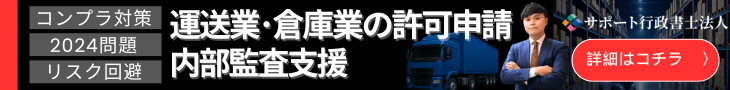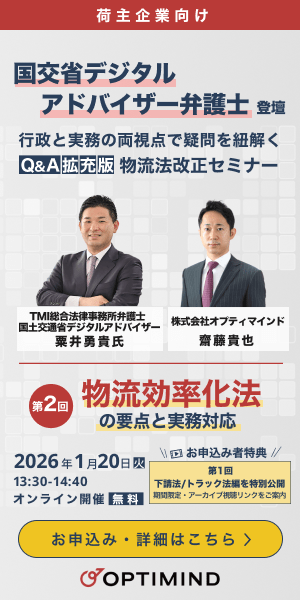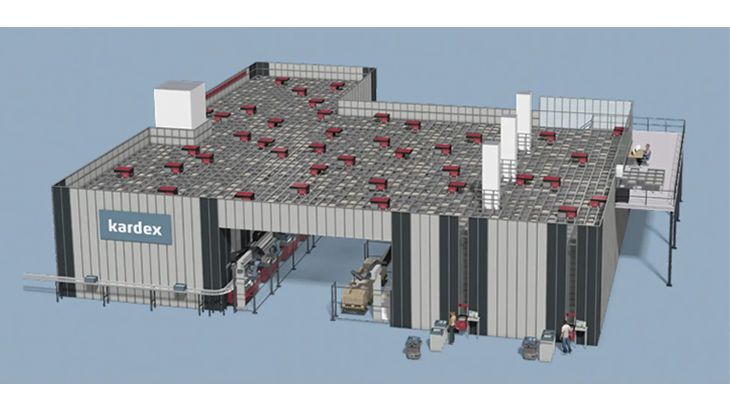仏Ocean WingsのスキャリットCEO会見、日本でも常石造船とプロジェクト展開
風力を活用した船舶の推進補助装置「WAPS」を手掛けるフランスのOcean Wings(オーシャンウィングス)のエマニュエル・スキャリットCEO(最高経営責任者)は11月26日、東京都内で記者会見し、これまでの事業の成果や今後の展望などを語った。
スキャリットCEOは、WAPSは代替燃料などと比較して経済的な効果が高いと説明。「気候変動問題への対応として最も資本効率の良い対策だ」と語った。さらに、日本でも導入の案件が進んでいることに触れた上で、2050年までに導入対象となるグローバルの船舶全体の20%のシェアを獲得したいとの考えを示した。
併せて、「日本の船主は脱炭素を依然重視されている」と述べ、日本市場を重要視している姿勢をアピール、引き続き海運会社などに採用を働き掛けていくことを強要した。

会見するスキャリットCEO
WAPSはコンテナ船などの甲板に硬翼帆を立て、正面や横からの風を推進力として用いることで、燃料消費量の削減と温室効果ガスの排出量抑制につなげられると見込む。
スキャリットCEOは、昨年秋に翼帆を4本備えたWAPSを搭載した1万重量トン型貨物船「CANOPEE(カノペ)」を実航海に投入した結果、大西洋を横断する航路で1日当たり燃料消費を25~50%減らせたことにあらためて言及。
続けて、日本でも常石造船が欧州の船主が保有しているばら積み貨物船にWAPSを搭載する準備を進めており、2026年5月の竣工を予定していると報告、その後も他の企業と契約が進んでいることを明らかにした。
「バルカータンカー、コンテナ船など世界で5万隻を(WAPS納入の)ターゲットにできると考えている。50年までにその20%、1万隻のシェアを取っていきたい」との意気込みを見せた。

常石造船製のばら積み貨物船にWAPSを搭載したイメージ(Ocean Wings提供)
国際海事機関(IMO)が10月の会合で、国際海運の船舶を対象とした新たな温室効果ガス排出規制案に関し、米国や産油国などの反発で採決を先送りしたため、海運領域の脱炭素化の先行きに不透明感が増している。
スキャリットCEOは新たな温室効果ガス排出規制の動きに関し「今回の結果で(温室効果ガス排出を抑えられる)代替燃料への投資が遅れてしまうだろう。当面は唯一の経済的な手段が風力推進装置になる。当社にとってはむしろ開発を後押しする状況になっている」と分析。「日本の船主にとっては風力推進装置と運航効率化のソリューションを選択していくことが現実的ではないか」と指摘し、WAPSの注目度が高まることに強い期待を示した。
WAPSの投資回収期間は平均で4~6年、今後はさらに3年まで短縮できるとの見通しを示したほか、CO2の排出量を1トン減らすのに必要なコストとしてWAPSは現在が太陽光発電や風力発電よりも安い30ドル(約4500円)に達し、さらに将来は半分の15ドル(約2250円)まで下げられるとの独自の試算を公表。代替燃料など他のソリューションと比較して導入のハードルが低いとの認識を表明した。
WAPSの翼などの製造に際し、部材の高騰の影響への対応を聞いたところ、スキャリットCEOは特定の地域に傾倒せず各地のサプライヤーと連携していることや、サプライヤーの工場など既存設備を活用して部材を製造してもらうことで、OceanWingsが自前で工場を構えるよりも効率的に製品を確保できていると説明した。

(藤原秀行)