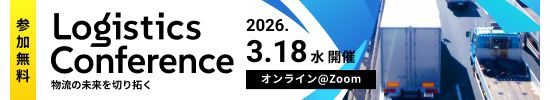総合10位ランクイン、ROIを赤字圏から2桁のプラスに改善達成
物流に携わる人の多くが関心を持ちそうなイベントがある。その名も「世界SCM競技会(Global Professional Challenge)」だ。世界各地から予選を勝ち抜いてきた企業のメンバーらがチームで参加。仮想空間で架空の赤字企業を経営し、災害など突発的に起こるイベントに対応しながら製造から調達、販売までをうまく回転させ、重要経営指標の1つとして広く用いられているROI(投下資本利益率)をどこまで改善できるかを競っている。
そんなエキサイティングな場に2021年、日本の江崎グリコが挑んだ。担当部署や経歴が異なる20代から60代の先鋭たち5人から成るチームを結成。日本代表の2社のうちの1社として、初参加ながら全約30チーム中、総合で10位にランクインする健闘ぶりを見せた。ROIをプラスに転換できず苦戦するチームも少なくない中、終始安定したROIの改善を果たした。
当時参加したメンバーのうち2人に、大会に参加した経緯や本番で経験したことなどを語ってもらった。2人とも口を揃えて「非常にやりがいのある大会だった」と当時の興奮を振り返った(以下、写真はいずれも江崎グリコ提供)。
20代の若手社員をCEO役に抜擢
「若い人にとっても非常に貴重な経験になったのではないかと感じている」。昨年11月に開かれた世界SCM競技会の世界決勝に進んだ江崎グリコのチームの1人、同社の飛田周二常務執行役員SCM本部長は今回のチャレンジについて、楽しそうに語った。
同競技会はSCM・サプライチェーンに関する人材教育を手掛けているオランダ企業のInchaingeが主催。同協議会の中では同社が開発、提供している実践型SCM・サプライチェーン経営人材教育プログラム「The Fresh Connection(TFC)」を活用、運営している。
TFCはSCMの教育プログラムとして国際団体のAPICS(American Production and Inventory Control Society)も認定。米国の著名な経済誌Fortune(フォーチュン)が選出している世界の収益が大きい主要企業「Fortune Global 500」の製造業トップ100社のうち、40%が採用するなど、欧米を中心に普及が進んでいるという。
TFCのシミュレーションソフトを駆使し、架空のフルーツジュースメーカー「The Fresh Connection」をセールス(営業)、調達、オペレーション、サプライチェーンの各担当役員とCEO(最高経営責任者)の計5人で経営していくとの設定で、最終的にROIの数値の良さで順位が決まる。サプライチェーンを効率的に運営する経営の擬似体験を通してSCMのノウハウを習得、実際の業務に役立ててもらうことを目的としている。
基本的に担う役割は、CEOが戦略の確認やKPI(重要業績評価指標)の設定、修正の指示など、サプライチェーン担当が物流網構築や適正在庫の設定など、オペレーション担当が生産ラインへの投資、稼働率最大化など、セールス担当がカテゴリーや顧客別の取り扱う製品数や販売促進など、購買担当が品質や納期の管理、原材料費の最適化などと明確に分かれている。
飛田氏は購買担当として参加した。そもそも競技会に加わろうと考えたのは、InchaingeとTFCの日本国内におけるサービス提供に関する契約を締結している日立ソリューションズ東日本からの紹介がきっかけだった。
江崎グリコはロジスティクスと需給計画、調達、生産の各部門が全てSCM本部の下に集結しており、以前からバリューチェーンをいかに確立、適正に運営していくかを重視するなど、平時からSCMに関する意識が高かったという。日立ソリューションズ東日本としても、世界SCM競技会は非常に価値ある経験になり、業務に生かせると見込んでいたようだ。
飛田氏は「通常業務でお付き合いのあった日立ソリューションズ東日本さんからこんなプログラムがありますよとお話をいただき、当社のチームメンバーは非常に頑張ってくれていると思っているが、客観的に見て自分たちが良いオペレーションをしているのかどうかを知りたくなった。他流試合をして、日ごろの仕事のやり方がどれくらい通用するのか、グローバルのベストプラクティスと比較してみたくなった」と語る。人材育成やキャリア開発のプログラムとしても魅力を感じたという。
今回のメンバーでCEO役を務めたのが、競技会当時はまだ入社間もなかった20代の、現在はグリコマニュファクチャリングジャパンで神戸工場の生産技術管理などを担当している古谷翔太郎氏だ。飛田氏は大抜擢人事について「彼は若いけれども情報収集力、まとめ方、判断力が抜きん出ていると、実は他の仕事を通じて観察した結果、感じていた。経営全体を目配りするという経験をぜひ若いうちにしてほしかった」と明かす。
他にもロジスティクスや生産などの現場で経験を積んできた精鋭のベテランたちを起用、20代から60代まで世代を超えた構成となった。「われながら、とてもいいメンバーだったと感じている」。飛田氏は笑顔を見せる。
古谷氏は入社前に大学院で技術系の研究を重ねており、そうした経験も人選に当たって着目されたようだ。「私自身はこれから工場の新しいラインを作っていかなければいけない人材。競技会に参加することで、経験が生きてくるのではないかと考え、指名されたからには精一杯頑張ろうと思った」と語る。


飛田氏(上)と古谷氏
「トレードオフとリスク」を学ぶ
日本の予選を無事クリアし、世界大会へ。経営は半年間を1ラウンドと設定され、1日当たり1ラウンド(2時間)で4日間連続、計4ラウンドにわたって開催された。約30チームが加わる中、江崎グリコの5人も赤字企業の立て直しに奔走した。なお、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、世界大会はアバター(分身)を使ったバーチャル空間で展開された。
 アバターを使った競技会の様子
アバターを使った競技会の様子
SCMの考え方に基づき、各チームは「経営環境の分析」→「戦略・施策の立案」→「実行」→「結果の分析」→「改善策検討」のサイクルを回す中で、どれくらい商品を製造・販売していくか、国際物流でどのルートを使うか、生産能力を増強するかどうか、どの市場をターゲットとして重きを置くかといった判断を重ね、製造量などの数値をTFCのシミュレーションソフトに入力していく。
当然ながら、どの程度の数値を入力すると他の工程などにどの程度影響が生じるかといったパラメーターの内容はオープンにされていないため、参加者は短時間のうちに仮定と検証、修正を迫られる。まさに現実の経営を体験できるようになっている。
例えば、生産を目いっぱい拡大すれば売り上げは伸びるが、設備の稼働や管理などのコストも増える。生産量を絞れば製造や輸送、保管などのコストを抑えられるものの、顧客へ約束したボリュームを届けられないリスクが生じる。様々な制約がある中、5人が意見を調整しながら、「個別最適」に陥らないようにする必要性がある。
その時々で、予期せぬイベントも発生するよう仕掛けられている。一例を挙げると、日本の予選では中東の海域で海賊が出現し、輸送中の船が乗っ取られたため物が運べなくなる事態が起こり、代替の輸送ルートや追加の調達の検討を余儀なくされたという。
飛田氏は「事後対応がかなり問われたが、そんな状況でもバックアップをしっかり確保しているチームは影響が少なく、逆にコストの安さだけを選んで輸送ルートなどを考えていると大きな影響を受けていた。そういう勉強が予選の段階でできたので、世界大会でも様々な要素のトレードオフとリスクを考えてオペレーションすることを意識できた」と指摘する。
世界大会でも、ラウンドが進むにつれて、外部の倉庫をより多く借りられるようになるなど、選択肢が増えてくるが、生産ラインを増やせば投下資本が拡大するため、ROIを下押しする圧力となり、外部の倉庫を借りれば在庫管理の難度が増すなど、まさにトレードオフとリスクの問題に直面した。メンバーは4日間という短期間ながら、SCMの難しさと面白さに触れることができた。
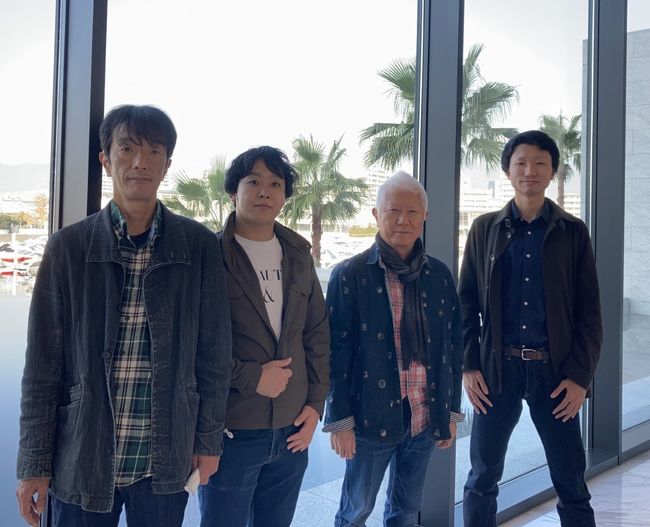 江崎グリコのチームメンバーら
江崎グリコのチームメンバーら
CEO役を果たす中で、古谷氏が強く意識したのがCO2排出削減だった。ROI極大化の目標達成に向け、チームメンバーと協議を重ねる中でも、意思決定をする上で必ずCO2の問題を意識するよう訴え続けたという。古谷氏は「世界中から参加者が集まる世界大会のような場で、当社が日本代表のうちの1社として参加している以上、CO2をガンガン排出して売り上げを伸ばそうとしているような印象を持たれなくはなかった。私自身、そうした仕事は決してしたくなかった。長期に契約して一緒に仕事をしたいと思ってもらえるような企業経営をしたかった」と狙いを強調する。
結果として、総合順位は第1ラウンドの12位から一時は7位まで到達、最終的にトップ10に滑り込むことができた。ROIは全チームの3分の1程度がマイナス圏から脱することができなかった中、18.35%と2桁のプラスを確保。そして、CO2排出量水準は最終の第4ラウンドでトップに躍り出た。「グリーン経営」ではまさに世界一位という快挙を成し遂げたと言える。
古谷氏は「中には、CO2を出してもいいから売り上げを伸ばそう、というスタンスのチームもあり、そうしたところがROIを伸ばしていたりしたので、本当に経営判断は難しいと感じた。より上位に行きたかったが残念」と語る。同時に、CO2排出量水準で首位になったことには「当社の環境重視という姿勢をアピールできたと思う」と満足そうだ。
飛田氏も「メンバー全員、フラットに話し合い、連携して取り組んでくれた。それぞれの持ち場で今回の経験を生かしてくれると期待している」と他のメンバーに感謝の言葉とエールを送っている。
江崎グリコは今後も、SCM世界競技会の日本予選へ継続して参加することを視野に入れているようだ。メンバーは参加を許されるのが一度きりのため、飛田氏や古谷氏は直接捲土重来を期すことができないが、飛田氏は「失敗してもいいから、ぜひ競技会の場で学んでほしい」と今後の参加者に要望する。古谷氏も「会社全体の経営という視点に気付くことができたのは非常に貴重な経験だった。他の人にも参加してほしい」と推奨している。
(藤原秀行)