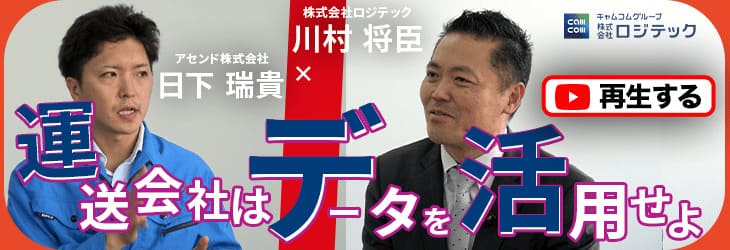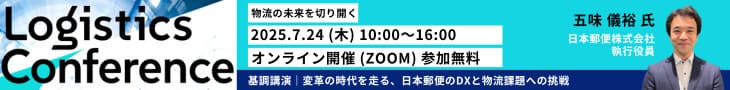第3回:大国間対立の激化で企業が直面するレピュテーションリスク
ウクライナ情勢は、中国と台湾の緊張関係に影響を及ぼす可能性があり、海を挟んで中台双方に隣接する日本としては決して目が離せません。サプライチェーンを抱える日本の物流企業や荷主企業はどう対処していくべきなのか。真剣に検討すべき時が来ています。
ロジビズ・オンラインは国際政治学に詳しく地政学リスクの動向を細かくウォッチしているジャーナリストのビニシウス氏に、「今そこにある危機」を読み解いていただいています。3回目は、大国の対立が企業にとって、レピュテーション(信用)毀損のリスクになり得るとの貴重な指摘です。ぜひご一読ください。
ビニシウス氏(ペンネーム):
世界経済や金融などを専門とするジャーナリスト。最近は、経済安全保障について研究している。
ロシアから撤退する動きは今後も続く
今日、世界では大国間の対立が先鋭化している。ロシアがウクライナに侵攻してから1年が経過するなか、4月に入ってロシアと1300kmにわたって国境を接するフィンランドが北大西洋条約機構(NATO)に正式加盟した。4月4日、ブリュッセルのNATO本部にフィンランドの新たな国旗が掲げられ、フィンランドのニーニスト大統領は我が国にとって歴史的に特別な日になったと表明した。
ロシアはこれに反論し、ペスコフ大統領報道官はロシアの安全保障と国益を脅かすもので対抗措置を取ると反発し、ロシア外務省もフィンランドは数十年にわたり国際情勢の中で堅持してきた軍事的中立を放棄したと強く非難した。プーチン大統領は軍事同盟国であるベラルーシに戦術核を配備する方針を明らかにするなど、欧米とロシアの亀裂は既に不可逆的なところまで来ている。プーチン大統領はウクライナから撤退する方針は絶対に取らないだろう。
一方、ウクライナ侵攻という大国間の対立は、企業活動にも大きな影響を与えている。この1年間で、マクドナルドやスターバックス、アップル、ナイキ、エイチ・アンド・エム(H&M)など世界を代表する欧米企業が相次いでロシアから撤退し、その影響は日本企業にも拡がっている。日立エナジーは今年1月、ロシアで展開してきた事業を売却したことを明らかにし、ロシアで約2000人の従業員を抱えるガラス大手AGCも2月上旬、ロシアを取り巻く情勢から同国でビジネスを展開することが難しくなったことを理由に、ロシア事業の譲渡を検討すると発表した。
他にも、大手自動車メーカーのマツダがロシアでの事業を現地の合弁会社や自動車研究機関に売却したほか、トヨタ自動車も現地での生産を停止。「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングはロシア国内の全店舗で営業を停止、閉店にする方針を表明している。
そして、外国企業の撤退が相次ぐなか、ロシア政府は3月末、ウクライナ侵略以降にプーチン政権が非友好国に指定した欧米や日本などの企業が資産を売却して撤退する場合、一定金額を寄付金としてロシアに政府に納付するよう義務付ける方針を明らかにした。ここまで来ると、もはやロシアで純粋なビジネス活動を行うことはできず、今後寄付金を払ってでもロシアから撤退を進める企業の数が増えることだろう。

中台の緊張が高まれば、日本にも影響が(イメージ)
米中亀裂すれば現地でビジネス継続が危うくなる恐れ
最近では、ロシアから撤退した欧米企業の間で、「またこの会社はロシアでビジネスしているのか」という疑念が拡がっており、正にウクライナ侵攻が企業のレピュテーションリスク(評価を棄損する危険性)を誘発する状況になっている。ウクライナ戦争の長期化はこうした傾向を一層強めることになろう。
一方、このレピュテーションリスクは台湾や中国を巡る情勢でも深刻化する恐れがある。そして、中国や台湾情勢から生じるレピュテーションリスクの方がはるかに日本企業にとっては厄介な問題だ。
周知のとおり、日本にとって最大の貿易相手国は中国であり、多くの日本企業が進出し、中国と全く取引、関係がないという企業の方が少ないだろう。そして、米中が安全保障や経済、サイバー、先端技術などの分野で競争を繰り広げるなか、今日台湾問題によって米中の対立がさらにエスカレートする恐れがある。
4月、米国カリフォルニア州で台湾の蔡英文総統とマッカーシー米下院議長が会談したが、中国はこれに強く反発し、中国人民解放軍の空母を中心とする艦隊が台湾南東部からバシー海峡を通過して西太平洋まで航行、台湾海峡を挟んで台湾に近い中国福建省の海事当局は台湾海峡で海上パトロール活動を開始した。これも米国や台湾への対抗措置であるが、仮に有事になれば、中国に展開する日本企業の経済活動にも大きな影響が出ることは避けられない。
そればかりか、米中の亀裂が決定的になれば、中国でビジネスを展開すること自体が日本企業にとってレピュテーションリスクになる恐れもある。具体的には、中国から撤退を進める欧米企業を中心に、「中国でビジネスを展開するべきではない」などと疑念が広がり、それが日本企業と欧米企業との間で摩擦を生じさせる恐れがある。実際、そのようになる可能性は低いと思われるが、ロシアのケースを教訓に、日本企業は大国間対立の激化で生じるレピュテーションリスクをさらに意識する必要があろう。それがかえって企業に不利益を与える可能性がある。
(次回に続く)