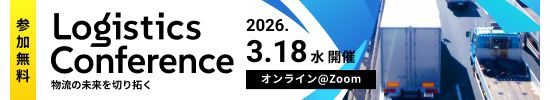第32回:世界を揺るがす「トランプ関税」の変化を読み解く
シリーズの記事はコチラから!
ビニシウス氏(ペンネーム):
世界経済や金融などを専門とするジャーナリスト。最近は、経済安全保障について研究している。
「ピンポイント」から「全方向」へ
トランプ米政権の再発足から早くも半年が経過したが、「トランプ関税」は諸外国に大きな混乱や動揺を生じさせている。今後、どのようなトランプ関税が発動されるかは未知数だが、1期目との違いが見え隠れする。1期目のトランプ政権は主に中国を標的にした関税措置が注目を集めたが、2期目ではその形態が変化している。
その変化を理解するためには、1期目と2期目の政策を比較することが不可欠だ。1期目の関税は、比較的焦点を絞ったものであり、経済的な合理性を強く帯びていたのに対し、2期目はより包括的で、政治的な駆け引きを前面に押し出している。
より詳しく見てみよう。1期目のトランプ政権は、「アメリカファースト」のスローガンの下、貿易不均衡の是正を掲げて関税政策を展開した。この関税は、主に中国をはじめとする特定国や特定品目に絞り込まれていた。例えば、中国からの輸入品に対する関税は、知的財産権の侵害や不公正貿易慣行を理由に課せられ、鉄鋼やアルミニウム、電子機器などの特定のセクターに集中していた。これは、関税は発動するためのツールとして位置付けられており、脅しや交渉の手段というよりは、実際に貿易赤字の解消や国内産業の保護を目的とした実質的な措置だった。
そして、このアプローチの経済合理性は明らかだ。トランプ政権は、関税を通じて米国内の製造業を活性化させ、雇用を創出することを狙っていた。対象を限定することで、米国の同盟国や友好国への影響を最小限に抑えつつ、中国のような競争相手にピンポイントで圧力をかけることが可能だった。
例えば、EU(欧州連合)やカナダ、メキシコに対する関税も一時的に課せられたが、これらは主に交渉の末に撤回や調整が成され、全体として貿易赤字の構造的な問題解決に寄与する形を取っていた。関税の設計は、WTO(世界貿易機関)のルールに準拠しつつ、米国の経済利益を最大化するよう工夫されており、政治的なパフォーマンスよりも政策の効果を優先した側面が強い。
その一方、第2次トランプ関税は、1期目の手法を基盤としつつも、明らかに進化した形態を示している。2期目のトランプ政権は中国を強く意識しているが、国を特定しない一律関税や相互関税を打ち出している。カナダやメキシコ、中国からの輸入品に追加関税を課し、さらに国家を特定せず、あらゆる国からの輸入品に10%の関税を課す一律関税を導入したことはその証左だろう。1期目が「特定国・特定品目」のピンポイント攻撃だったのに対し、2期目は「全方向型」の包括的関税へシフトしており、貿易相手国全体に圧力をかける戦略が見て取れる。
この変化の核心は、関税の「目的」の転換にある。1期目が発動を前提とした経済政策だったのに対し、2期目は政治的ディールや脅しの要素が顕著だ。トランプ氏は、関税を武器に貿易相手国から譲歩を引き出すことを公言しており、例えば中国からの投資誘致や技術移転の停止、さらには同盟国からの軍事負担増大を交渉材料にしている。
これは、関税を「実行」するより「脅威」として活用するアプローチで、経済合理性が相対的に弱まっている。なぜなら、一律関税は米国内の物価上昇やインフレを招くリスクが高く、国内産業の保護という観点から見ても、非効率な側面があるからだ。一例を挙げれば、輸入依存の産業(自動車や電子機器)では、コスト増が消費者価格に転嫁され、米経済全体の成長を阻害する可能性がある。1期目ではこうした副作用を最小限に抑えるための対象絞り込みがあったが、2期目では政治的な成果(貿易協定の再交渉)を優先し、広範な影響をいとわない姿勢が強い。
ただ、足元では米国の物価上昇のペースが強まる兆しも見えるなど、景気動向の先行きに経済界などから懸念が広がり始めている。2026年には中間選挙を控え、こうした2期目のより強硬なスタイルがどこまで堅持できるのか、注目どころでもある。
(了)