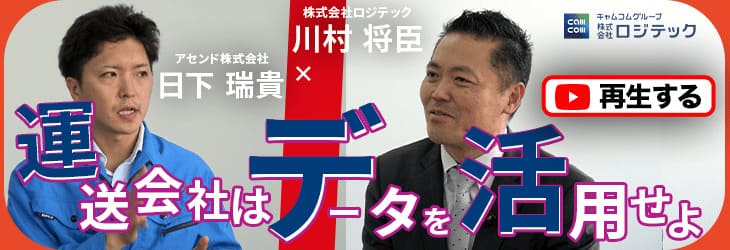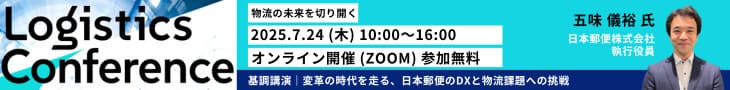共同配送の有効性など報告
ヤマトホールディングス(HD)系シンクタンクのヤマトグループ総合研究所は2022年11月1日、東京都内で、世界を大きく変えたインターネットの形を物流の世界で再現し、業務効率化や省人化などを図る考え方「フィジカルインターネット」の実現を後押しするためのシンポジウム(後援・一般社団法人フィジカルインターネットセンター)を開催した。オンラインでも併せて、視聴できるようにした。
官民からの登壇者は、実際に物流の現場で導入している共同配送などの取り組みと成果を報告したり、内閣府の「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」が推進している物流業務革新の国家プロジェクトの研究状況を語ったりした上で、人口減少に歯止めがかからない中、フィジカルインターネットの概念に基づき、物流の在り方を大胆に変えていくことが不可欠とのスタンスを明示した。
シンポジウムに登壇した有識者らの発言内容の概要を全3回に分けて掲載する。なお、同総研はシンポジウム終了後の22年11月30日付で解散し、フィジカルインターネットセンターが活動を継続している。

シンポジウムの会場(ヤマト総研提供)
官民有識者らが物流効率化実現へ取り組み加速訴え
共同配送は可視化できるメリット、標準化、ルールづくりの3つが必要
シンポジウムの中盤では民間企業の担当者が共同配送などの取り組みの進捗状況を報告した。まず、日清食品の深井雅裕取締役は「持続可能なサプライチェーンに向けて」と題し、自社で展開している共同配送の状況について紹介した。
深井氏は自らの経験を基に「共同配送は可視化できるメリット、標準化、ルールづくりの3つが必要。何かしらのメリットを数字で示すことにより、社内外から協力を得られる効果がある」と解説。同社の場合、飲料メーカーと商品を積み合わせることでトラックの台数を20%、輸送コストを18%抑制との効果を引用した。
また、標準化として商品を納める段ボールケースの外装表示を合わせるとともに、将来の電子化をにらんで伝票もA4判の縦に統一。用いるパレットはT12型とT11型に集約し、積み付けるパターンも統一することなどを決めたと言及。T12型パレットを利用することで積載率を改善できたという。
併せて、ユーピーアール(upr)の協力を得てパレットを回収するシステムも構築。パレットの洗浄を自社工場と外部の委託業者で使い分け、適宜済ませた後でまた出荷に用いるとの流れを明らかにした。
同氏は「ルール作りは一番難しい。業界ごとにオペレーションが異なる中、参加者に公平なメリットを出すことで取り組みを拡大する必要がある。各社に歩み寄り、協力によるルール作りが必須。納品場所や倉庫、バース、付帯作業を標準化しなければ難しくなってくる」と実体験を語り、「業界の垣根を超えた協力関係の中で一歩一歩、実績を積み上げていこう」と聴衆に呼び掛けた。

深井氏(オンライン中継画面をキャプチャー)
セイノーホールディングス(HD)グループのセイノー情報サービスの早川典雄取締役は「物流クライシスを乗り越える新しい協働化のスタイル」と題し、同社も参加している内閣府の「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」が推進する国家プロジェクト・第2期スマート物流サービスの「地域物流」の実情を取り上げた。
早川氏は地域物流のプロジェクトが「時間指定の緩和」「直前運送依頼の解消」「異業種による共同化」「輸送工程の分割」の4つの課題の解決に向けて関係者が取り組んでいると紹介。「運送依頼が直前になっていて、無理して運んだり無駄に運んだりといったばらつきが発生している。未来の生産・販売・在庫情報を早めに物流事業者と共用し、輸送リソースを平準化する」と狙いを語った。
具体策として、商流情報(PSI)を事前に関係者が共有化することで輸配送の物量の平準化を図ったり、納期回答後の出荷計画に基づいた早期の運送依頼情報を共有し、突発的な輸送案件を減らして計画的な輸配送へ転換していったりすることを目指していると言及した。
併せて、プロジェクトの展開でエリア内の共同輸送促進で積載率向上やCO2排出量抑制が期待される上、輸配送工程を集荷と幹線、配達にはっきりと分割することでドライバーの分業を実現することにも触れた。
各課題の解決を図る実例として、共同集荷や幹線輸送集約などを進める「配送計画サービス」を展開。「SIP地域物流ネットワーク化推進協議会」も立ち上げ、「中ロット・貨物パレット共同輸配送」の構築などを展開しており、22年月末時点で124会員に達したことなどを報告した。

早川氏(オンライン中継画面をキャプチャー)
標準化が国際物流の発展につながった
JR貨物の石田忠正相談役(元会長)は「陸海空運『モーダルコンビネーション』の実現」に焦点を当てて講演。海上コンテナの取り扱い発展の歴史などに触れた上で、各モードが連携した輸配送の重要性をアピールした。
冒頭、「海運は世界の大半の航路がコンテナ化され、コンテナもISO(国際標準機構)で統一された。コンテナ輸送発展の秘訣、原点はまさにコンテナサイズの統一にあった。これがなければ絶対実現できなかった」と指摘。
さらに、空運も世界各国の主要な航空会社がほぼ3大アライアンスに集約され、貨物輸送船も共同輸送の仕組みができていると分析。航空輸送用のコンテナも世界標準規格で統一されていると語り、国際輸送の標準化促進の歴史を振り返った。
JR貨物も、ビール大手4社が鉄道貨物を使い共同輸送を展開していることや、ハコベルと組み輸送手段のマッチングに注力していることなどに言及。作業の自動化・機械化・デジタル化を図り、効率を改善した新たなスマート貨物ターミナル駅の整備にも着手しており、その一例として仙台の「新仙台貨物ターミナル駅」の機能を引用した。
石田氏は「貨物鉄道はプラットフォームの1つとしてフィジカルインターネット拡大の一翼を担っていきたい。企業が(物流機能を)統一することを通じてメリットを得られると実感できる日本にならなければいけない」との決意を語った。JR貨物としても、鉄道貨物ターミナル駅構内に開発する物流施設「レールゲート」を仙台や名古屋、大阪、福岡などに拡充していくことや、貨物新幹線の研究を進めていくことなどを表明した。

石田氏(オンライン中継画面をキャプチャー)
内閣府のSIPスマート物流サービス研究推進法人でプロジェクトマネージャーを務める金度亨氏と鍵野聡氏も登壇。「日本型フィジカルインターネットの実現、これからの課題について」に焦点を当てて解説した。
金氏は米国や中国、欧州で進められている、関係者が物流に関するデータを共有、業務効率化へ有効活用しようとする「オープンデータ戦略」の概要を報告。日本としては、ごく一部の巨大企業による強力な全体統合システム化を図っている米国や、政府による強力なトップダウンで各分野の情報分断解決を目指している中国よりも、民間企業同士の協調によるデータ主権を尊重する権限分散型システム化を推進する欧州のやり方が親和性は高く、日本におけるフィジカルインターネットの実現に有効との認識を示した。
その上で「ガラパゴスにならず日本の強みを生かすためにも欧州と連携していく必要がある。サプライチェーンに参加する各企業の合意形成による日本型フィジカルインターネットを実現していくことが重要」と述べ、欧州委員会との連携などを図っていく必要性をアピールした。

金氏(オンライン中継画面をキャプチャー)
鍵野氏は、生産年齢人口が20年後に約20%減少し、積載効率は約25%低下すると見込まれる中、物流分野で温室効果ガス排出低減のSDGs目標を達成していくには、20~30%の生産性向上が必要と指摘。「スマート物流サービスは30%の生産性向上を実現する」と狙いについてあらためて公開した。
SIPの研究で核となっている物流・商流データ基盤について「多くの企業をつなぐ1つのデータ基盤が必要。クラウド上にデータを受け入れるバケツを作るというもので、ここが研究の中心。省力化・自動化に資するデータを自動的に収集する技術を開発していく」と表現した。
これまでのSIPの活動を通じ、日本型フィジカルインターネットの実現へ、「一番必要なのは『錦の御旗』的なもの。これがないと今後も活動を続けられない」と指摘し、明確な目標と筋書きの設定の重要性を重ねて強調。議論するフェーズは既に終了しており、地に足の着いたグランドデザインを描く旗振り役と、実行するプレーヤーが必要。モチベーションも大切などと見解を述べた。
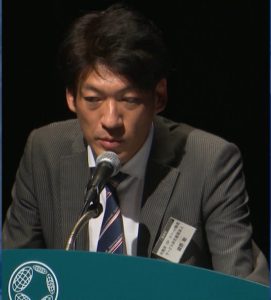
鍵野氏(オンライン中継画面をキャプチャー)
(後編に続く)
(藤原秀行)