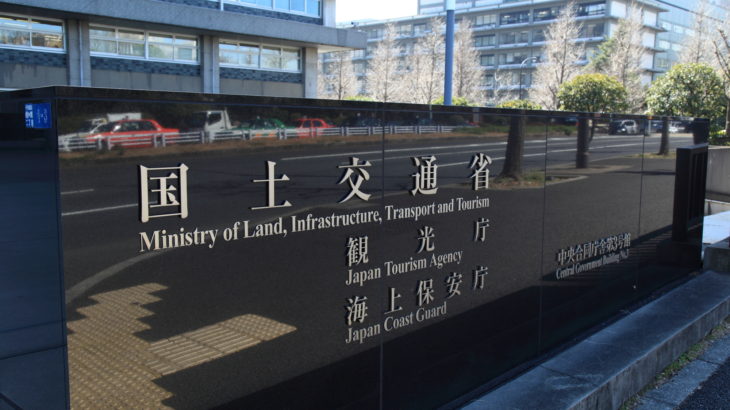国交省が審議会で本格導入時の要件案提示
国土交通省は11月30日、東京・霞が関で、社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会の物流小委員会(委員長・根本敏則敬愛大教授)を開催した。
トラックドライバー不足などを踏まえ、官民で利用拡大を検討している「ダブル連結トラック」に関し、同省の担当者が本格導入する際に設定する要件の原案を提示。ドライバーに一定以上の技能を求めることや、ダブル連結トラックが2台連続して道路を走るのは安全確保の観点から禁止することなどを盛り込んだ。
同省は今後、関連法令の改正などを進め、近くダブル連結トラックの使用を解禁。普及に向けた安全確保などの環境整備を後押ししたい考えだ。

小委員会の会場
「あと10年で日本の幹線輸送は息絶える可能性」と危機感
同日の小委員会では冒頭、根本委員長が「諸外国に比べて日本国内を走るトラックが小さいのではないか、もっと大きなものが走ることができるようにすべきではないか、ということでトラックの大型化に取り組んできている。この1年、(国交省の)道路局が非常にスピード感を持って新しい施策を展開しており、心強く思っている」と語った。
続いて、ヤマト運輸の福田靖ネットワーク事業開発部長が出席し、同社の取り組み状況などを説明。背景として、幹線輸送もドライバー不足が深刻化していることを挙げ、「ラストワンマイルが苦境に立たされて大変だとされているが、そこに(荷物を)送り込む幹線輸送も非常に担い手が少なくなっている。昨今は平均年齢が50代で、このまま行くと10年くらいで日本の幹線輸送は息絶える可能性がある」と強い危機感を表明した。
同社が2017年から東名阪の大型拠点「ゲートウェイ」間で試験的に日々2台運行しているダブル連結トラックの様子を動画で紹介。交差点で右左折しても内輪差がほとんど生じないことなどをメリットとして指摘した。
さらに、同社も加盟している業界団体の全国物流ネットワーク協会が17年7月、ダブル連結トラックの共同利用を検討する研究会を立ち上げ、討議を重ねていることに言及。関東~関西間で同社のゲートウェイを使い、19年3月にダブル連結トラックを活用した共同輸送を始める予定を明らかにした。
「新東名道の海老名~豊田東」が過半含まれる経路が条件
国交省の担当者は、新東名道で16年に運送事業者らと連携して実施した21メートルのダブル連結トラック走行実験の検証結果を報告。必要なドライバー数の削減や燃費改善、実際に運転したドライバーの疲労低減などの効果があったと説明した。
同時に、車両が長く追い越しに注意が必要と周囲に喚起する表示を後部に取り付けるなど、安全面の配慮が必要と強調。併せて、高速道路の非常駐車帯内からはみ出したり、SAに設けた専用駐車エリアを他のトラックが気付かずに使ってしまったりする課題も明らかにした。
実験結果も踏まえながら取りまとめた要件の案として、
①対象区間は実証実験にも使った「新東名道の海老名~豊田東」がおおむね50%以上含まれる経路とする
②ドライバーは大型自動車運転業務に直近5年以上(場合によっては3年以上)従事していることなどを条件とする
③実技訓練として右左折時の車両挙動や軌道の把握などを充実させる
④21メートルを超える車両が2台連続して運行するのを禁じる
⑤非常停止時は後続車両に分かりやすく知らせるため、停止表示機材を板状と灯火式の両方用いる
――といったポイントを挙げた。
これに対し、出席した委員からは、高速のSAでダブル連結トラックが安全に駐車できるよう配慮することなどを求める意見が出た。

ダブル連結トラック(国交省中部地方整備局ホームページより)
自動車運搬車両で積載可能な台数増へ基準改正案
小委員会ではこのほか、自動車運搬車両の特車通行許可基準を一部見直し、1台で運べる自動車の数を増やせるようにする改正案についても審議した。
日本陸送協会の永井高志会長は、ドライバー不足などで自動車運搬も経営環境が非常に厳しくなっていると説明。「物流の効率化、生産性向上と労働時間短縮を両立させるテーマとして取り組んでいる」と語り、改正の必要性を訴えた。
国交省は自動車運搬車両に関し、貨物が積載されていない場合の長さは17メートル、積載している際は後部からはみ出した部分を含めて18メートルまでとする規定を新たに設ける方向性を示した。
(藤原秀行)